
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年08月18日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク |
33 |
19/08 |
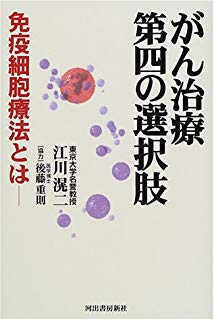 |
江川滉二 |
河出書房新社 |
◎ |
副作用がなく、有効性は抗がん剤に劣らない治療法◉はじめに ・「活性化自己リンパ球療法」を中心とした「免疫細胞療法」 患者さん自身の免疫細胞、とくにリンパ球を体外に取り出して、培養しながら刺激を与えて活性化させ、かつ増殖させたうえで患者さんの体内に戻すことによって治療しようとするもの。 世界的にみても質量ともにトップレベルの治療法 ・がん治療の三本柱となっている外科(手術)療法、抗がん剤療法、放射線療法は、いずれもがんを外力で取り除こうとするものであり、対して、生体に内在する自然治癒力を利用する治療法が、免疫療法である。 3――「免疫細胞療法」を臨床の場でスタート 免疫療法はどういう治療法か ・免疫細胞にはもともとがん細胞に対抗して、これを抑え込もうとする力があるわけです。 ・たまたまがん細胞がなにかの理由で免疫細胞の監視をくぐり抜けて増殖をはじめると、力のバランスががん細胞の側に傾き、免疫細胞が抑えきれずに、がん細胞がどんどん増殖してしまうということになります。 ・このとき、力のバランスを再び免疫細胞の側に傾けるためには、がんの力をそいでやるか、免疫細胞の力を強力に増強してやるほかありません。 ・がんの力をそそぐことを目的にしたのが、いまでの通常療法です。その中でも、抗がん剤などは、がんの力もそぐけれども免疫の力も弱めてしまうので、力のバランスを免疫側に傾けることにはなかなかなりません。 ・これに対して、免疫療法は、免疫細胞の側の力を強めることによって、力のバランスを免疫細胞の側に傾けようとするものです。 ・しかし、がんそのままそこにあるのですから、免疫の力をよほど強めてやらなければ、力のバランスが免疫のほうに傾くことにはならないでしょう。ここが、免疫治療の難しいところです。 4――現在のがん治療、その問題点は何か 「縮小率による評価」が抱える多くの問題点 ・「効いた」患者さんが、どのくらいの割合でみられるかは、一般に「奏効率」として表現されています。 ・この奏効率は、その治療によってがんを治せる割合とはまったく違います。 ・抗がん剤の場合は、だいたい3割以上の患者さんで効いた場合、有効であると考えることが多い。 ・つまり、半数以上の患者さんにとっては、なんの利益にもならず、かえって不利益だけが生じ、ごく一部の患者さんだけに、がんの一時的な縮小をもたらすような治療法が、有効な治療法だと判断されているわけです。 5――瀬田クリニックでの治療の実際と、その成績 なぜ、いま免疫細胞療法か ・生体に侵入してきた外敵や、内部に生じた反乱者から、個体の命を守ろうとするのが免疫細胞の働きです。 ・いい換えれば、感染症とがんから命を守ることを目的としているのが、免疫細胞だということです。 免疫細胞療法はどのように効くのか ・免疫細胞療法が抗がん剤より優れているのは、副作用がほとんどないために、どんな病状の患者さんに対してもおこなうことができる点と、体にやさしく、元気なままで治療が長期にわたって継続でき、効果も長期にわたって維持しやすいことです。 ・抗がん剤療法でがんは多少縮小しても、体がずっと弱ってしまい、効果も継続しないのでは、なんのための治療かわかりません。 気持ちの持ち方と病状の関係 ・がんの病状に対して、気持ちのもち方というのは、驚くほど影響するものです。 ・がんの場合には、たいていの患者さんはひどく落ち込んでしまうので、落ち込まない患者さんとの差が大きいのだと思われます。 抗がん剤の効果判定とは ・治療効果としては、消失または縮小が4週間以上つづいた場合を、それぞれ「完全寛解」または「部分寛解」、治療前後で不変だった場合を「不変」、増大した場合を「 ・そして全体のうちで完全寛解と部分寛解の占める割合を「奏効率(有効率)」と呼んでいます。 ・しかし、この奏功したということ、あるいは完全寛解したということと、治癒とはまったく違います。 ・いろいろな治療法をうまく組み合わせてやっていったほうが、高い効果が得られる可能性がある。 6――がんを抑える免疫細胞をいかに活性化するか がんに対するリンパ球の働き ・たとえば、体に傷ができて、そこから細菌が侵入したとします。そうすると、まず白血球の一種である多形核白血球がその場に集まってきて、細菌を取り込んで分解してしまいます。 ・つまり、細菌を食べてしまう形になります。ですから、多形核白血球も食細胞の仲間です。 ・細菌を食べた白血球はその結果、自分も死んでしまいます。この死骸が ・もう少し時間がたつと、リンパ球が働きはじめて、その細菌を認識するリンパ球だけが莫大に数をふやして、その細菌に対する抗体をつくりはじめます。 ・これによって、細菌は強力に殺されるだけでなく、同じ細菌が再び侵入してきたときに、即座に撃退することができるようになるのです。これが獲得免疫です。 ・タンパク質というのは、いろいろな種類のアミノ酸(20種類ある)が鎖のように連なってできているものです。 ・ウイルスのタンパク質の一部は、細胞のタンパク質分解酵素の働きで断片化されます。断片化されたタンパク質、つまりアミノ酸が数個から十数個ぐらいの鎖になったものは「ペプチド」と呼ばれます。 ―― 完 ―― |