
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年11月20日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き&コメント |
39 |
19/09 |
「自分の死」入門 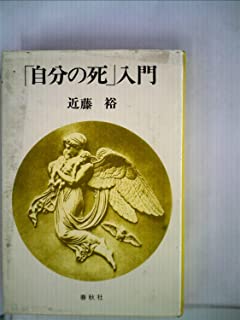 |
近藤裕 |
春秋社 |
☆ |
はじめに ・死との対面、それは、平凡な人間には恐怖心を呼び起す。 ・しかし、思うに、死が呼び起す恐怖心というものは、死後の世界に関するものよりも、死のプロセスに関わるものではなかろうか。 ・肉体的な痛み、心理的、精神的な苦痛、愛する者、家族や友人らとの離別、人生の終焉に伴う喪失体験。肉体の死と共に訪れてくるこれらのすべてが、人間を不安のとりことし、恐怖のどん底に落し入れるのだろう。 「自分の死」入門 死を考え、死に関わることを忌み嫌い 死を語ることをタブーとし 死に背を向けた生き方 死が呼び起す不安や怖れの心に うちまかされたままの消極的な生き方 ――そのような受身な生き方はやめよう! 死にゆく人の心理や 死にゆく過程におけるケアーの在り方を 科学的に究め 死と対話し、「自分の死」を考えたうえでの 生きる意味を考え、設計し かけがえのない有意義な人生の日々を そして、かけがえのない「自分の死」を準備しよう! プロローグ――死、昔と今 1 死と同居していた昔 ・世の宗教は、死の恐怖の故に死を忘れ、死に背を向けた生き方をする人間に、死と対面し、死の恐怖を克服する道を提供する。 ・この、多くの宗教に共通して見られる死の恐怖を克服する手段に関する教えは、死の向うに永遠の生命を信ずるという思想である。 2 死と別居した時代 ・昔は物理的にも、精神的にも死と同居していた状況が見られる。 ・医学がまだ充分に発達していない頃は、病死する子どもや早や死にする大人も多かった。昔の人はそれだけ身の周辺において死と出会うことが頻繁であった。 ・そこに、死を恐れ、死を考え、また死と取り組まざるを得ないという必然性があった。 ・これに反して、現代は死に背を向け、死と別居した時代であるようだ。 ・医学の進歩、宗教の影響の弱体化、物質文明の繁栄などといった近代社会の傾向が、人間をますます死から遠ざけている。 4 死との対話のすすめ ・死を見つめた生き方とは、死を終始おののきながら消極的な人生を送るというのではなく、やがて死ぬべき身であり、しかも、いつ死に出会うか分からないという自覚に立ちながら、しかも、一日一日を有意義に送るという生き方である。 1章 死のスタイル 3 ライフ・スタイルと心臓病の関係 ・死のスタイルを選ぶということは、人生の生き方や生活のスタイルを選ぶということでもある。 ・人間は皆「生きてきたように死ぬ」。 ・つまり、日々の生活のスタイルが死のスタイルを決めるのである。 ・暴飲暴食をする人はそれなりに自分の死ぬ時と死に方を選んでいる。車を無謀運転する人は、ただ自分の死ぬ時と死に方を選んでいるばかりか、自分の死ぬ場所さえも選んでいることになる。 ・がむしゃらに働く猛烈サラリーマンは、それなりに自分の死ぬ時と死に方を選んでいる。 ・一方、健康管理につとめ、ストレスを適切に処理し、心にゆとりと平和を保ちながら生活をしている人は、それなりに自分の死ぬ時と死に方を選んでいるわけである。 5 死――来世への移行の時 ・評論家である松田道雄氏曰く、 「たくさんの人の死に、医者として立ち会う機会があったが、信仰をもっている人ほど荘厳なものはない。信仰は、もしそれをもちえたならば、晩年における最高の武装である。信仰とは、つねに死とむきあってたじろがぬ力を人にあたえるものであるからだ」 6 死――別れの時 ・人間の生のスタイルが死のスタイルを決める。 2章 なにが「死に方」のスタイルを決めるか ・「生き様が死に様を決める」 ・つまり、個人の人生の生き方が死に対する考え方や、死に臨む態度にも反映され、結局、人間は死に直面したときに、これまでに生きてきたように死に臨んでいくということである。 2 死に方のスタイルを決める要因 (二)過去と現在の人間関係 ・今日、癌などのように致命的なものとして恐れられている病名を、医師は患者自身に告げないということが一般的な慣習となっている。と同時に、患者の家族が病名を知らされるというのが常識となっている。 ・このことは長所よりも短所の方が多いようである。 ・長所としては「癌」という病気に対する今日の一般通念があまりにもネガティブなもの(癌 ‐ 即 ‐ 死という受けとり方)であるために、癌の病名を本人に告げることが心理的なショックを与え、治るものも反って治らないという事態が生ずるのを防ぐとか、そのような不必要な心理的な負担を患者に与えない方が治療にプラスになるといった点が考えられる。 ・一方、短所としては、患者が自分の病気と戦う力や、死に向う姿勢を信頼されていないということから生ずる相互の不信感が、病期と戦うこと自体に苦闘している患者の心にもう一つの重荷を加えることになる。 ・このような心の重荷が病人の闘病生活にはプラスにならないことや、病人から癌と戦うチャンスを奪ってしまうことはいうまでもない。 ・最大のマイナスの点は、そのような状況が患者の人生の最後の日々における家族との関係を、嘘と偽りに充ちたものにすることにある。 ・癌患者にも自分の死を覚悟し、自分自身の残る余命と家族との生活を、もっとも有意義に生きる自由と権利がある。 ・この自由と権利が医師や家族の者から奪われた状況の中で死に臨む患者の心には、さまざまなネガティブな感情を引き起こすことになりかねない。 ・死を間近に控えた末期患者は、医療関係者の態度によって、自分の死期が間近かであることを感知することができるようである。 ・もし、治る見込みがないという判断から治療が控えられたり、医師や看護婦が患者と過す回数が少なくなり、また、時間が短くなったりすると、それによって、自分は医療関係者から見放されたという意識を患者の心に生じさせる。 ・このような状態はさらに患者を絶望感と孤独感に落し入れる。 ・このように考えると、医療関係者は、患者の病態が絶望的であったとしても、また、 ・むしろ、臨終に近くなればなるほど、すなわち cure の可能性がなくなればなくなるほど、病人に対する care の量は増し加えられるべきものであろう。 3章 死に臨む心理 1 死への適応 (三)理性的適応―死の学習 ・患者が死を予想する時に病気の状況や影響について学ぼうとする言動が多くみられるが、これも死への適応メカニズムの一つである。 ・致命的と思われるような病気に罹り、そこに死を予知するような場合には、その不安は大きく、そして、その不安を取り除くための理性的適応傾向はいちだんと顕著となる。 ・自分の病気がどういう状態にあるかということを知り、また治療の内容や根拠などを知りたいという患者の願いは、自分の生命に対して主体的に生きようとする姿勢から生ずるものである。 ・つまり、理性的に死に適応しようとする傾向は正常な適応メカニズムなのだ。病気に圧倒されず、逆に病気をコントロールしようとする積極的な態度の表れでもある。 2 死に臨む過程における感情的反応 (六)安らぎ ・自分の人生は、たとえ不満足や不完全な点があっても、それなりに自分や他人にとって、また、社会全体に対しても、価値あり意義あるものであったと認識する時に、その人生の終焉を意味する死を積極的に受容することが容易となるのである。 ・キュープラー・ロス 「一般的にいって、教育程度が低く、知性の低い、社会的な絆と職業上の義務の少ない単純な人のほうが、物質的な豊かさ、快適な生活環境、多くのつきあいと人間関係とを失うこととなる富裕な階級の人々よりも、この最終危機に困難な苦に直面することができたようである」 「一生を苦労とはげしい労働のうちに過ごした人、子どもたちを育てあげた人、自分の成し遂げた仕事に満足している人々のほうが、平安と威厳をもって死を受容することが容易であったようだ」 「これに対して、一生を野心的に環境を支配してきた人、物質的な財を蓄積してきた人、社交的なつきあいは非常に多数にのぼりながらも、生の終りにあたって助けとなるような有意義な人間関係の少ない人ほど、死の受容が容易ではないようであった」 4章 「自分の死」を死ぬこと 3 病気の実体を知る ・死を予知する故に、残された日々を一つの信念をもって、価値あることにエネルギーを集中し、燃え尽きるまで生きつづける、死を知ったが故にこのような生き方を歩み、人生の最後のドラマを主体的に演じて、自分の死を死んだ人は、現に多くいる。 4 自律的に死ぬ ・一日一日を人生の最後の日であるかのように、有意義に送るように努めている者にとっては、不慮の事故などにより突然死ぬというようなことがあっても、その者の死は「自律的な死」であったということができるのではなかろうか。 エピローグ――「死を知り生を知る」 ・「今日、死ぬかのように、今日を生きる」ということばがあるが、いつ訪れてくるかもしれない自分の死を意識した日々を送るということは、それは、死を脅えながら生きることではない。 ・避けることのできない、しかも、いつ訪れてくるかもしれない自分の死を、意識的に考え、対話をすることが可能なときに、かけがえのない自分の死を、また、かけがえのない人生の日々の営みを有意義に送ることができるのではないかと思う。 ・「死を考える」ことなくして「生を考える」ことはできない。 ・「自分の死」を一度死ぬことができた人(死に対する自分の考えや気持ちを整理できた人、といってもよい)こそ、「自分の人生」を本当に生きることができるというものだ。 ―― 完 ―― |