
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年12月04日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き&コメント | |
45 |
19/11 |
日本語の起源 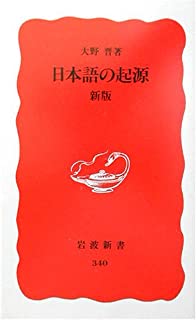 |
大野 晋 |
岩波新書 |
☆ |
第一章 同系語の存在 二 探索の方法 音韻の対応 ・英語の d とドイツ語の t のような整然たる関係は偶然の鉢合わせとはいえない。 ・英語とドイツ語との間には、基礎的な単語の間に整然とした関係を示すことができる。この状態を、「音韻の対応がある」という。 ・ ・「音韻の対応」が成立するのは、その二つの言語が、昔あるときに同一の言語であった結果である。 ・ラスクというデンマークの言語学者は、一八一四年、大西洋の北部の島、アイスランドの言語と、何千キロ離れたギリシャ語・ラテン語との間に、音韻の対応があることを三五二の単語によって具体的に立証した。 ・それは、つまりこれらの言語が大昔に同一の言語から分れたのだということを証明したことであった。これが「比較言語学」の誕生だった。 ・「音韻の対応」が言語学の手法によって確認されると、それはその二つの言語の祖先は同一だということの基本的資料となる。 ・「音韻の対応」とは二つの言語の同系を証明する、それほどに強力な方法である。 タミル語とは ・インド亜大陸の南端にタミルナードといわれる州がある。そこにタミル人が住んでいる。またスリランカの東部北部にもタミル人が住んでいる。そのタミル人、総計五千万人が話している大言語がタミル語である。 ・タミル語は、紀元前二世紀から紀元二世紀にわたる四〇〇年間の歌を集めたサンガムという歌集を持っている。 ・紀元前二世紀という古い時代の言語の記録を確実に現在に伝えているのは、サンスクリット語、古典ギリシャ語、古代ヘブライ語などに準ずる古さで、タミル語とはそれほど古い記録のある言語なのである。 ・その文法構造は、朝鮮語、ツングース語、モンゴル語、トルコ語とおよそ同じで、言語学でいう 比較の範囲・語根 ・日本語の動詞には活用があり、第四番目の音素は、変化する。だから、安定しているのは最初の三音素の部分までである。 ・第三音素までが安定した「語根」なのだ。 ・だから外国語との比較に当っても最初の三音素までと意味とが厳密に対応するかどうかを見る。それが必要で十分な条件となる。 四 単語の対応――語根の比較 日本語とタミル語 ・ばらばらに認識されて来た日本語の単語を形によって群としてまとめ、タミル語の単語群と突き合わせることによって、日本語の語根とタミル語の語根とが、その派生語と共にまとまって対応することが判明した。 ・タミル語と日本語を比較すると、ただ断片的に単語がたまたま類似形を持つということではなく、対応は語根に及んでいる。 ・この二つの言語を一対に並べてみることによって、一方の言語だけからの推論では証拠不十分と思われる事柄が、相手の言語にも共通に発見され、それによって証拠不足が解消される場合も少なくない。 五 文法の比較 日本語とタミル語の文法 ・日本語とタミル語の文法構造は、全体として非常に似ていて、大部分が共通である。 ①名詞の後に助詞を使う。 ②動詞の後に助動詞を加える。「花咲きぬ」「花咲かむ」のように。 ③「雲は山を隠す」のように題目語―目的語―動詞の順に配列する。 ④「雨降るか」「共に行かむ」のように疑問や勧誘などは文末に助詞を加える。 ⑤関係代名詞を持たない。 ⑥代名詞は日本語がコレ・ソレ・アレのような三つの区別を持つに対し、古いタミル語も近・中・遠の三つの区別を持つ体系をなしている。 ⑦相違点としては、タミル語は動詞の後に人称接辞をつけるが、日本語はこれを持たない。 ・①から⑤にわたる性格は、実は朝鮮語、モンゴル語、トルコ語などとおよそは共通である。 ・しかし、同系を立証するにはこのような構造上の特徴が共通だということだけでは不足で、個々の助詞や助動詞の、音韻が規則的に対応し、その上、用法も同一であることが示されなければならない。 ・日本語とタミル語の助詞と助動詞とを全面的に比較すると、基本的な助詞・助動詞はほとんどすべて鮮明に対応する。 六 五七五七七の韻律 ・日本では後に五七五の十七音節による俳句が成立するが、これは和歌の上の句を独立させるという歴史的な発展の結果生じた形式で、季語を設定し、漢語を交えることによって一句に包含できる内容の不足を補うという手法を発明したことが関係している。 ・五七五七七を中心とする和歌の形式と同系の歌が、古典時代のタミル語に多数存在することが明らかになった。 ・単語の音韻の対応、文法の構造、助詞・助動詞の対応、歌の韻律の一致は、日本語とタミル語の同系を証明する証拠である。 第二章 対応語と物の世界 一 稲作のはじまり 農耕に関わる言葉 ・日本語の農耕・農産食品に関する単語が、タミル語と数多く対応する。 ・耕作地、作物名、食品名、動作その他、併せて二十数語がある。 (畠、田んぼ、畦、焼畑、稲、粟、早稲、米、糠、粥、餅、蒸かす、藁、穂、へら…) 「稲」を歌う ・弥生時代の日本の稲作と、南インドの巨石文化期の稲作との間には、①単語の上で対応が多数あり、②実物について、類似する稲粒の併行的存在が認められる。 ・これほど多数の農耕の単語の対応は、朝鮮語との間の農耕具の対応をはるかにしのぐ。 新年の豊作儀礼 ・ことは一月十五日の小正月の行事である。一月十五日は古い暦法では満月の日で、満月の日は月のはじめ ・タミルでは今でも暦の一月一日には何のお祝いもせず普通に働く。ポンガルの日、十五日が新年なのである。 ・日本では今は一月十五日は小正月とされている。 ・稲の豊作を祈願する元日の行事は、南インドと日本で細かい点まで併行的に行われており、そこで発せられるタミル語の祈願の詞と日本のホンガ、あるいはホンガラという単語は使い方の上でも、音韻の上でも対応している。 (ホンガ―青森地方の歌言葉。ホンカ゜ラ―江戸時代の歌言葉。) ・これは日本とタミルの稲作が単に行事として平行するだけでなく、起源的に一致するものであることを証する有力な証拠であろう。 二 墓と墓地 「墓」と「忌み」 ・ハカ(墓)という単語と、「死の穢れ」を表わすイミ(忌み)という単語とに、日本語・タミル語の対応がある。 ・日本の考古学は、外国といえば朝鮮をまず取り上げ、それとの交渉を第一に、むしろ、もっぱら扱っている。しかしハカ(墓)とイミ(忌み)という死と埋葬に関係する最も基本的な単語に対応があるのだから、日本とタミルの間に、具体的な「墓」と「墓地」について平行する事実があるのではないか。 墓の遺跡 ・南インドの巨石時代には、日本の弥生時代の「物」と似ている「物」が多く存在する。 ・南インドのマイソール大学考古学科主任グルラージャ・ラオ教授曰く、 「九州に特有の支石墓、甕棺が南インドの巨石文化のものとよく似ている」 「箱式石棺にも似たものがありました。単に類似しているのではなく、系統的な関係があるように思う」 「その場合は、南インドから海沿いに東南アジア、韓国を経て、日本に伝わった可能性が考えられる」 南インドの巨石文化 ・南インドの紀元前一〇〇〇年から紀元三〇〇年くらいまでの文化期の墓に巨石を使うものがあり、それがヨーロッパ各地にある巨大な石を使う墓と類似があるので、それを指標として、その時期の名をヨーロッパの学者が「巨石文化」と呼んだのである。 弥生時代の墓制 ・弥生時代の墓制の特徴の一つは巨大な集合墓地が作られたことである。 ・こういう集合墓地は、農耕生活の進展ときわめて密接な関係がある。 ・集合墓地の成立には、定住、もしくは安定した一年周期の生業を持つことなどが必要な条件である。 ・穀物生産の開始が紀元前一万年ともいうメソポタミア地域に較べて、紀元前五〇〇年前後というほどにはなはだしく遅かった日本は、集合墓地の形成においても最もおそい地域の一つなのだ。 ・集合墓地は北九州から始まった。 ・日本では最も早く農耕の開始された北九州の弥生時代の墓制 ①支石墓 ②土壙墓 ③甕棺墓 ④箱式石棺墓 ⑤木棺墓 ⑥墳丘墓 ・南インドの巨石時代の墓制 ①支石墓 ②土壙墓 ③甕棺墓 ④箱式石棺墓 ⑤― ⑥墳丘墓 ・日本の考古学は弥生時代の北部九州の墓制をもっぱら朝鮮と比較するが、その主要な部分は、タミル地方を中心とする南インドの巨石時代の墓制の中におよそ見出される。 ③甕棺墓 ・支石墓や箱式石棺は、日本の内部から、内部だけで発達したものとは考えられず、どこか外から来たもので、縄文時代には存在しなかった埋葬の方法である。 ・とすればそれと複合して墓地を形成している「大型の甕棺に葬る」という観念もまた、新しく外から来たものと見るべきものだろう。 ・日本では縄文時代にすでに一万年に及んで土器を作って来たのだから、「大型の甕棺に収めて埋葬する」という新しい考え方が外から入って来たとき、甕そのものは当時の人々が自分で作ることができただろう。 三 グラフィティと記号文 ラグパティ博士の示唆 ・南インドの巨石文化期の特徴は、土器にグラフィティがついていることだ。 ・壺や甕棺を焼き上げた後、または焼き上げる前にその口縁部、頸部、腹の部分につける。 ・記号をグラフィティ・落書きと呼んでいる。 ・ところがこれと同じ形の記号が日本の弥生時代の土器にも存在することが明らかになって来た。 農耕に関するグラフィティ ・狩猟に関しての祈願、農耕の方策に関しての祈願、それをこめて狩りへの出発に当って、壺に酒を入れて神に供して祈る。あるいは遺体を葬る甕棺や、墓に食糧を供える壺に、その記号をつけて一緒に埋める。 ・つまり、自分たちの狩りや農耕の収穫の豊富を祈り、またあの世で食糧を豊かに得る生活ができるように願う。そのような広い意味の「吉祥」を祈るのがグラフィティであり、また記号文であったのではあるまいか。 ・日本では弥生中期以降には漢字が次第に流入した。 ・この種の記号は韓国のほぼ同時代の無文土器その他には発見されない。 ・壺の同一の部位に同形の記号が、南インドと日本とに平行的に多数存在する事実そのものは確実である。 四 金属の使用 日本の金属使用 ・銅はアナトリアでは紀元前六〇〇〇年紀に利用され、エジプト、メソポタミア、パレスティナなどの地域では、およそ紀元前四〇〇〇年紀には利用されていたらしい。 ・日本では縄文時代、一万年にわたって金属の利用は行なわれなかった。 ・それが弥生時代になると一挙に銅と錫の合金である青銅と鉄が登場する。 ・日本の突然の金属使用は、輸入に始まったと見るしかない。 ・その時期を見ると、青銅と鉄がほぼ並んで証跡を残している。 ・日本では青銅器から鉄器へという文明の展開を、順次に経験したのではなく、すでに出来上がった青銅、鉄の文明をほぼ同時に受容した。 南インドの金属使用 ・日本の青銅の製品の中で顕著なものは銅鐸である。 ・それは朝鮮の馬鐸から発展したと考えられて来たが、その文様、砂岩を用いる鋳型などを考慮して、中国中・南部から東南アジアに注目すべきだ。 金属に関する言葉 ・銅をタミル語で kan という。 ・日本語には、カナまたはカネがある。これが金属の代表名となっている。 ・これを銅、鉄、金、銀と使い分けたいときにはアカガネ、クロガネ、クガネ(コガネ)、シロガネと、その前に形容詞アカ、クロ、ク(黄)、シロをつけた。 ・またカネは、そのまま「鐘」でもあり、タミル語 kannan が「鐘青銅の職人」であるのと対応して、カネは打ち鳴らす「鐘」の名となった。 ・つまり日本語 kan₋a、kan₋e は、タミル語の kan と音も意味も対応する言葉である。 ・日本語のタカラが金銀財宝を指すのは、タミル語の taka‐ が金、錫、ダイヤを形容することと平行的な事実である。 ・日本語の金属にかかわるカナ、カネ、タカラという言葉と物は、タミル語の kan 、takaram と音の上で対応するだけでなく、物自体においても平行的であるといえよう。 ・一つの社会の文明または文化にとって、全く新しいものが到来するときには、その物をはじめてもたらした国、つまりそれの輸出地のその単語を、物と共に受け取る。 ・そのことを考え合わせると、カナ、タカラという金属は、南インドに由来すると考えられる。 五 ハタという言葉 ・ハタはまず「生地・布」を意味したもので、それが転じてその布を織る機械を指すように変った。 ・日本語のハタという単語は、布、旗、凧の三つの意味を持っていた。 ・ハタが凧を意味するのは昔は凧を布で作ったからだろう。 ・タミル語で pat₋am を見ると、『タミル語大辞典』に、 "着物の生地、大旗、布製または紙製の凧" とある。 ・日本語 pat₋a とタミル語 pat₋am の対応は明瞭である。 カセという言葉 ・日本の弥生時代を特徴づける文明の事実、稲作・墓制・金属使用・機織に関係する対応語を取り出して、その文明事実を検分した。 ・すると、文明にかかわる「物」を表現する単語は、単に「言葉」だけがタミル語と対応するのではなく、その言葉の表わす日本の物、あるいは事は、およそ南インドに具体的に平行する物や事として見出された。 第三章 対応語と精神の世界 一 生活の慣習 結婚に関する慣習 ・奈良時代の結婚は、「妻問い婚」といわれるように、男が夜になると女の家を訪れて結婚し、翌朝自分の家に帰って働くのが普通だったようである。 ・女は男の来訪を待つ生活を営んでいた。 ・ともかく日本の古代の結婚の仕方は「妻問い婚」で、そう考えて読まないと理解できない歌が万葉集に多くある。 ・ところがサンガムの歌を見ると、やはり男は女を訪問して結婚し、朝になると男は自分の家に帰る歌がある。 ・スリランカ北部のタミル語地域で、或る夫人の親戚の男性は、現に、夜になると妻の家に行き、朝帰って来て自分の生家の畑で働いている由である。 ・結婚の方式は、サンガム時代と日本古代では平行している。 カラスの報らせ ・万葉集に、好きな人の来訪についてカラスが予言的な泣き方をすることがあるという習俗があったことが歌われている。 ・タミル語の古典、サンガムの中にも、恋人の来訪をカラスが予告する習俗の存在を示す歌がある。 ・日本の場合はカラスをののしり、タミルではカラスに感謝しているが、底には平行する習俗がある。 「 ・古代の社会には今日は亡びた占いの法がいろいろある。日本の古典にユフケ(夕占)という呼び方で見える方法はその一つである。 ・これは家の門前や家の近くの街路で、夕方に行う占いである。 ・このユフケの仕方として、最初に、呪文をとなえる。次に道に境を造り、米を撒き、櫛の歯を三度鳴らした後に、その境界線の中に入って来た通行人の口にする言葉をきいて吉凶を占うとある。 ・サンガムの歌にある「ユフケ( viricci )」は。神意をひらく意と思われる。 ・タミルでは愛人の動静、戦争の成り行きなどを占う。それは町はずれ、村はずれなどで、道に米と花と水を撒いて、その中を通りかかる人の言葉を聴く。 髪に櫛を入れずに待つ ・夫が旅に出ると妻はその間、髪に櫛を入れない習俗が万葉集に歌われている。 ・これと同じ習俗がタミルにあった。 三 精神生活の根幹 ・奈良時代およびそれ以後の日本人の生活の中でその精神的生活の支点となっている単語 「アメ」(天) 「カミ」(神) 「マツル」(祭る) 「コフ」(乞ふ」 「ノム」(叩頭) → 日本語の古語「首をたれて祈る」の意 「ハラフ」(祓ふ) 「ホク」(祝く) 「ウヤ」(敬) 「アガム・アガル」(崇む・上る) ・これらの宗教関係の語例を見ると、日本人の基本的宗教観念を表わす語の大部分がタミル語と対応する。 ・これらは漢語以前の日本人の世界把握の観念の表現であり、かつ漢語を受け入れたのちも今日に伝わる基本的宗教認識である。 ・日本人の情趣・情意の表現に深くかかわった単語 「アハレ」 「スキ」(好色) 「サビ」(閑寂) 「ハヂ」(恥) 「ワルシ」(悪し) ・これらはみなヤマトコトバとして認められて来た。 ・ところがこれらには対応語がタミル語にたしかに存在することが知られた。 ・西南太平洋の言語の中に、あるいは中国語の中に、これらの対応語を求めることはできない。 第四章 南インドの言語・文明と日本・朝鮮 一 日本語とタミル語の同系 ・日本語とタミル語の比較 (1)すべての音素にわたって音韻の対応がある。 (2)対応する単語が基礎語を中心に五〇〇語近くある。 (3)文法上、ともに膠着語に属し、構造的に共通である。 (4)基本的な助詞・助動詞が音韻と用法の上で対応する。 (5)歌の五七五七七の韻律が共通に見出される。 ・以上の五ヵ条は、日本語とタミル語が同形の言語であると考えることによってはじめて理解できることである。 ・これによって日本語について比較言語学が要求している条件にかなう、一つの同系語を特定できるようになったといえるだろう。 日本語とタミル語の相違 ・原始日本語では母音の数は四個であったと推定される。 基層言語 ・ある地域に一つの言語が使われていたとする。そこに別の言語が入ってくる。それは多くは文明的に、あるいは軍事的に強い集団の言語である。 ・受け入れ側の人々は生活の利益のためにその新しい言語を覚えて行き、何世代かの間にはやがて以前の古い言語を忘れて新しい言語に同化して行くことがある。 ・しかし、以前の古い言語が持っていた音韻の特徴、造語法あるいは文法形式の一部分などがすべて消え去ることはなく、それらが新しい言語体系の中に生き残って行くことがある。 ・その場合、以前の言語を「基層言語」という。 ・南方にオーストロネシア語族と一括される言語がある。 ・オーストロネシア語族は、インドネシア語、メラネシア語、ポリネシア語などに分れて西南太平洋に広く分布している。 ・その最古の母音体系はa、i、u、e の四個であった。 ・これは原始日本語の四母音とほぼ一致する。 ・つまり、日本に非常に古く、基層言語としてポリネシア語族の一つに近い音韻組織を持っていた何らかの言語があったところへ、タミル語が 日本語の成立 ・日本語とタミル語の音韻体系の根本的な相違は、それまで日本の地で行われていた言語がタミル語を受け入れ、それに同化して行く際に、在来の言語の音韻の特色が、タミル語のもっていた巻舌子音、母音の長短の別、子音終りの単語の受け入れを拒否した結果なのではないか。 ・この考えを進める上で重要なのは、新しく拡大してくる言語の先導役をした文明の力である。 ・文明の力が大きければ、相手をその文明に巻き込むと同時に言語をも巻き込むようなことが起こる。 ・当時の日本とタミルとの文明的事実を比較すると、新しい食糧としての粟作、稲作、金属の使用、機織の開始、新しい墓地と埋葬の方法、また、未だ文字に至らない記号を土器に刻むという慣習、これらの文明に関する事実について、日本語とタミル語の間には、「平行事象」が多くあった。
・七〇〇〇キロも離れた地域ではあるが、同時代に見出されるこの平行は人間生活の根幹にかかわるものについてである。 ・数々の平行現象は偶然の類似と見るにはあまりにも広汎で、質が重大ではないか。しかも ・それらは単に「物」が似ているというだけではない。それらの「物」にまつわる言葉が一緒についている。 コメ、アハ、ハタケ、タンボ、アゼ、クロ、モチ、ヌカ。ハカ。カネ、タカラ。ハタ、オル。 ・これらの単語は、今日、日本語の基礎語として生きている。 ・それが二〇〇〇年以上前のタミル語と対応し、日本にあった「物」が同時代のタミル社会の「物」と平行している。 ・平行とは直ちに両者を結びつけず、単純に同趣の物が存在する現象として把えようとした表現である。しかしこれは単なる平行だろうか。 ・対応語の数は約五〇〇種である。基本語は二〇〇〇語はあるといわれる。 ・五〇〇語は少ないとはいえまい。 ・そして大切なのは対応語の中味、それが質的にどんな役割を果たしているかを見ることであろう。 ・日本人の精神生活の基礎をなすヤマトコトバ、そのあるものは日本人の宗教生活に深くかかわり、現代日本にまで生きている。 ・あるものは日本人の美意識、倫理意識の根底にかかわる言葉として日本人の精神生活の支点となっている。 ・それらのヤマトコトバがタミル語に対応する。 ・これらの「言語」と「物」と「こころ」の対応と平行とは、個々に、ばらばらに成立したと考えることはむつかしいという結論に達した。これらの状況は、包括的に、統一的に理解されるべきものである。 ・南インドのタミル語と共にあった文明が、日本でいう縄文時代の終末期に日本に入って来た。 ・安定的な、美味な、滋養に富む食糧の生産の技術、強力な武器と工具を作る金属の使用に象徴される新しい文明。 ・それらを受け入れた日本人は、ついでその文明の基盤であった当時のタミル語を聞き入れ、使用しはじめ、その五七五七七という歌の形式まで取り入れたのではないか。 ・その時期を、縄文晩期から弥生時代とここで限定するのは、イネ、コメ、ハタケ、タンボ、カネなどの言葉の実体が日本に現われて定着したのが縄文晩期から弥生時代にかけてだからである。 ・これらの「物」は縄文時代、一〇〇〇〇年もつづいたその時期には日本に存在しなかった。 ・縄文時代の文明が衰えて、晩期後半という時期になったから、そこに新文明が入って来たのではない。 ・新文明が「物」として入って来て広まったから、縄文時代という生活体系が終末を迎え消滅したのである。 ・実態のないところに単語だけがひとり歩きすることはあり得ない。単語のあるところ、それに対するモノやコトがあるはずである。 ・地域としては北九州に、時間としては縄紋晩期後半に、南インドのモノやコトが日本に到来し展開した。 ・それらを表わす言語もそれに伴って日本化されて広まった。 ・この激変は、北九州に始まり西日本から東日本へと拡がって行った。 ・これが「葦原の瑞穂の国」つまり今日いう「日本」の言語と文明の誕生である。 二 私の説に対する質疑 東南アジア各地の巨石文化 ・南インドの巨石文化が、東南アジアに広まって行った。 ・その広まりの範囲は、インドシナ、マレーシア、ジャワ、スマトラ、セレベス、ボルネオ、フィリピン、台湾に及んでいる。 ・調査項目は、支石墓、箱式石棺、石碑、石塚、石臼、甕棺、ロクロ、壺、グラフィティ、刻み目、鉄器、青銅器、ビーズ、貝輪、 ・南インドの巨石文化波は台湾にまで及んでおり、台湾から北上する力は、最近のベトナムあるいは南中国からのボートピープルの日本への到来ぶりを見れば、いかに強く、可能なものであったかが推測される。 文化伝播は舟による ・古代では、むしろ陸上交通は道路が整備されずに困難であったに対し、海上交通は天候さえよければ沿岸の航行は容易で、想像以上に遠距離を航行していた。 ・弥生時代の土器に描かれた船の絵は数多くあり、古代の交通路はむしろ海路が中心であるという。 ・そして古代の舟の大きさが想像を超えること、日本の弥生時代の巨大な舟の実在の可能性が十分考えられる。 ・現にローマ皇帝アントニアヌスの使者は、紀元二世紀に南インドを経て中国の皇帝に親署をもたらした。 ・当時の東南アジア、西南太平洋の海上交通の盛んなさまを想見することができる。 タミル人は日本に来たか ・来た。 ・タミル語には pul‐am (村・区域)という語があり、広く使われていた。 ・ところが、日本書記にフレという語があり、この fur‐e は、タミル語の pul‐am とまさしく対応する単語である。 ・このフレを村の意で使う地域が日本で一つだけある。 ・それは長崎県、壱岐の島である。 ・壱岐には、 東 など、フレという地名が一〇〇例ある。 ・壱岐にタミル人が住んでいたことの証拠とすることができよう。 ・現に壱岐の島には、弥生時代の巨大な遺構が次々に発見されている。 ・また、日本の方言の中にアッチャ(父)、アヤ(父)、タンダ(父)、アーヤ(母)、アッチャ(母)、アッパ(母)、アンマ(母)、アンマー(母)、アンニャ(兄)、アンネ(姉)などの家族名称が青森県、沖縄県をはじめとする各地にある。 ・これらすべてに対してタミル語にはぴったりと対応する単語がある。 ・ということは日本へタミルから、文明的な「物」だけが輸入されたのではなく、家族単位の移入が存在した結果であると思われる。 ・つまりタミル人は家族として日本に来て住んだし、集落を形成した地域もあると考えられる。 ・タミルと日本の間には両者の言語の仲介地となるような場所があるか。実は朝鮮語がタミル語と約四〇〇という対応語を持つのである。 対応語の内容 ・私は稲作に関する単語が日本語とタミル語との間で二十数語対応することによって、日本の稲作の開始と南インドとの関連を推定した。 ・同じ論法によって、朝鮮における稲作も、南インドからの伝来にはじまると考えられるのではないか。 ・二〇〇〇年の隔たりの後で、なおこのような対応語が生きている。 ・これらの単語は朝鮮の稲作農業の由来を南インドからと証言しているのではないか。 ・では、約四〇〇語の対応だけによって、朝鮮語とタミル語・カンナダ語とが言語学上同系だといえるのか。それは未だ言えない。 タミルと日本と朝鮮の文明史的関係 ・タミル語など南インドの言語と、朝鮮語との同系説はなお言語学的な立証が困難であるとしても、朝鮮語と、タミル語・カンナダ語の間の文化語を含む単語の約四〇〇語の対応は確実である。 ・ということから、巨石時代の南インドと朝鮮との文明の関係はたしかに存在したと考えられる。 ・つまり日本とタミルとの文明史的関係は、わずかな、孤立した関係ではなく、朝鮮を含めた「三角関係」として成立しているのである。 ・だから弥生時代にかかわるすべての学問は、これからは南インドの巨石時代を視野に含めた上で、東シナ海、黄海、渤海をめぐる地域の動きとして、時には中国の浙江省を含めてそれを考察しなくてはならないだろう。 ・朝鮮の文明史を青銅器によって区分すると、初期・前期・後期に区別される。 ・後期になると、鉄器の出現、土壙墓、多数の集合した甕棺墓が南部にある。 ・つまり前期のある段階から墓制は南インドの巨石文化と類似する様相を帯びてくる。 ・この時期に南インドの文明と言語とが朝鮮半島に波及したのではあるまいか。 ・揚子江下流地域には紀元前五〇〇〇年紀に稲作があった。それは日本にも朝鮮半島にも長い間伝来しなかった。 ・中国の石包丁と類似のものが雑穀や稲の穂積みの道具として日本や朝鮮に使われているけれども、穀物栽培に関して言葉の上では中国語からは単語が何一つとして伝来していない。 ・それに対して、日本にも朝鮮にも稲作関係の南インドの単語が多く見出される。 ・南インドの人々は、進んでこの極東の地に住む場所を求めて進出して来た。 ・東南アジア各地に南インドの墓制が広まっていることも、日本・朝鮮への文明の波及は、同じ源に発するのであろう。 ・朝鮮の言語に対して南インドのタミル語・カンナダ語が流入した期間は、青銅器時代の前期以後、楽浪四郡の設置以前の間が中心をなしたのではなかろうか。 ・それ以後は南インドの影響は次第に薄れて行き、やがて途絶えたものと考えられる。 ・楽浪四郡の設置によって、中国の直接の出店をもった朝鮮半島は、日本に対して優位を確立し、以後の文明的関係が進んで行ったと見ることができよう。 ・私は言語上の事実から南インド・日本・朝鮮という「三角関係」が成立した事情を以上のように推測する。 ターミナル ・一つの仮説 「日本には縄文時代にオーストロネシア語族の中の一つと思われる、四母音の、母音終りの、簡単な子音組織を持つ言語が行われていた。そこに紀元前数百年の頃、南インドから稲作・金属器・機織という当時の最先端を行く強力な文明を持つ人々が到来した。その文明は北九州から西日本を巻き込み、東日本へと広まり、それにつれて言語も以前からの言語の発音や単語を土台として、基礎語、文法、五七五七七の歌の形式を受け入れた。そこに成立した言語がヤマトコトバの体系であり、その文明が弥生時代を作った(その頃、南インドはまだ文字時代にはいっていなかったので、文字は南インドから伝わらなかった)。寄せて来た文明の波は朝鮮半島にも、殊に南部に日本と同時に、同様に及んだが、中国が紀元前一〇八年に楽浪四郡を設置するに至って、中国の文明と政治の影響が強まり、南インドとの交渉は薄れて行った。しかし南インドがもたらした言語と文明は日本に定着した。その後紀元四、五世紀に日本は中国の漢字を学んで文字時代に入り、漢字を万葉仮名として応用し、紀元九世紀に至って仮名文字という自分の言語に適する文字体系を作り上げた」 ―― 完 ―― |