
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年11月17日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き&コメント |
47 |
19/11 |
幕末維新の民衆世界 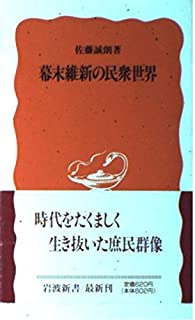 |
佐藤誠朗 |
岩波新書 |
◎ |
序章 庶民日記に歴史を読む 庶民は脇役だったか ・黒船=ペリー艦隊が浦賀に来航したのは一八五三(嘉永六)年。この事件を契機に幕末動乱の時代がはじまる。 ・庶民は庶民なりに、情報を交換し、暮らしや生業への影響を察知し、時代認識を深めていったのである。 ・庶民は決して幕末維新期の脇役などではなかった。 ・庶民日記をたんねんに読み込むなかで、庶民たちの歴史を見る確かな視点と、領主世界とは異なる自立した庶民世界の広がりが見えてくる。 庶民日記の世界 ・ここには、いままでの教科書的歴史像とはまったく異なる幕末維新史があり、そして豊かな庶民世界がある。 幕末動乱への視点 ・庶民日記のなかで、幕末動乱はどうとらえられていたか。 ・庶民は、戦いに血道をあげる武士たちの喧騒に決して同調しなかった。 ・民衆は領主たちの動向を的確につかみ、ときには人足の挑発を拒否し、各地で庄屋らを打ちこわしたのである。 識字率の高さと学習熱 ・寛政期から天保期、すなわち一八世紀末から一九世紀全般にかけて、庶民の読み書き能力や学習熱はいちじるしく高まった。 ・中下層農民の男女の場合は、寺子屋で学ぶことが奉公にでるための条件になっている。 ・〔寺子屋に行けなくとも〕古盆の上に灰をのせて文字を書いては消し、消しては書いて「いろはにほへと」(仮名文字)を親から教えられた。 ・商家や職人に奉公にでれば、いやでも文字を学ばされた。 第四章 戦と世直し 五 戦が終わる 武州騒動を見聞きする ・家持・家主・ ・独身の窮民に銭一貫九〇〇文、二人暮らし以上は三歳までの小児を除き一人につき銭一貫一〇〇文を、救銭として与えると町会所より触れた。 【私見 : 『打ちこわし』の被害にあった窮民に施しをするという習慣があったことに驚く。「ノーブレス・オブリージュ」という言葉があるが、江戸時代の日本人には(貴族でもない富裕層が)、すでにこのような振る舞いができる風習が完成されていたのだ!】 焼き芋、大流行 ・俳優市川小団次の葬送で、深川浄心寺地中玉泉院へ見送る者や見物人がおびただしく、見送り人に差し出した菓子は四〇〇〇人前に上ったという。 終章 庶民にとっての御一新 異人が女や牛を奪いに来る ・盗みや掠奪の禁止、放火の禁止(火の用心)、殺傷の禁止、この三つが近世における百姓一揆の規律・作法であると言われる。 ・打ちこわしをともなう一揆においては、家財道具や諸帳面を持ち出して、庭先や道路で焼き捨てる例は数多くみられるが、居宅・土蔵などをまるごと焼き打ち(放火)するようになったのは、一八六六(慶応二)年以後のことのようである。 明治政府の開化政策 ・明治五・六年に政府は、氏神の祭礼とその行事(地芝居・手踊り・花火)、盆会、五節句、道祖新祭り、虫送り、雨乞い、寒参り、闘牛など、先祖から受けつぎ、農業に密着した習俗を、開化の今日にふさわしくないと矢つぎばやに禁じた。 ・村びとの多くは、県官や村役人・知識人から「旧弊頑愚」とそしられようとも、これらの布達を受けいれなかった。 ―― 完 ―― |