
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年7月1日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
9 |
19/03 |
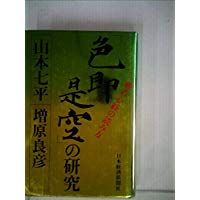 |
色即是空の研究 |
山本七平 増原良彦 |
日本経済新聞社 |
◎ |
1 いま、なぜ「般若心経」なのか ■釈迦が説いた「苦集滅道」 ・般若心経に出てくる「苦集滅道」言葉は、釈迦が説いた「四諦」、つまり四つの真理である。 ・その真理の第一が「苦諦」。人生は苦であるという認識から、すべては始まるというわけだ。 ・これは人間の真実の状態を、正しくみきわめることである。 ・第二に、それではその苦はどこからくるのかという原因探求が始まる。それが「 ・釈迦の説いた「集」とは原因という意味だが、では「苦」の原因、つまり「集」はいったい何か。それは本質的には、私たちが欲望、煩悩を持っていることだと、釈迦は教えているのである。 ・第三の「滅諦」は、この「集」つまり苦の原因をなくしてしまえば、結果としての苦がなくなるということである。 ・仏教においては、その理想態は「 ・そして、第四の真理として「道諦」が説かれているが、これはその原因をなくす方法と言うわけである。 ・具体的な方法としては、八つの方法「八正道」が説かれている。 ・すなわち、正しいものの見方(正見)、正しい思索(正思惟)、正しい言葉づかい(正語)、正しい行ない(正業)、正しい生活(正命)、正しい努力(正精進)、正しい意識(正念)、正しい精神統一(正定)がこれである。 ■仏塔信仰から生まれた大乗仏教 ・釈迦の死後、釈迦の後継者として、二代目の病院長を立てなかった。集団指導制をとった。みんなで協議し合いながら、釈迦の教え、彼が残してくれた処方箋を守っていった。これが、小乗仏教と呼ばれる上座部仏教なのである。 ・一方、在家の信者たちは、釈迦に対して非常な人間的魅力を感じていた。 ・釈迦亡きあとは、二代目の病院長というべき魅力的な人物がでてこなかったということもあって、教団からは離れてしまった。 ・彼らは釈迦の遺骨を収めた仏塔(ストゥーパ)をつくって、これにお参りすることによって、聖者崇拝、聖物崇拝の中で自己の宗教的な癒しを求めていった。 ・そうすると、その仏塔の維持とか管理を受け持つ人が必要になってくる。 ・また、釈迦亡きあと百年、二百年もたつと、いったい釈迦とはどういう人物だったのか、お参りにくる人々も知らなくなるから、釈迦の生涯についていろいろな「伝説」がつくられるようになった。 ・釈迦の超人的な能力を声高らかに、参詣人たちに語り聞かせるわけである。 ・こういう中から出てきたのが、大乗仏教である。つまり、大乗仏教は仏塔信仰の世界から生まれ出てきた。 ・大乗仏教の仏陀が非常に超人化されて、超人間的な神格化された仏陀なのは、この経緯からである。 ・これに対して、小乗の仏陀はあくまでも人間=釈迦であるというところが違っている。 ■インドにもあった仏陀待望論 ・仏陀というのはすべての人を救うものであって、小乗のいうようにたんに出家者を救うだけでは、仏陀ではない。 ・大乗の説くように、出家も在家もともに救うものこそ本物の仏陀である、というわけである。 ・ストゥーパ崇拝、聖遺物崇拝といつた習俗的なものを、大乗仏教という宗教に高める背景になったのが、いわゆる「空」の思想だ。 ・そして、その「空」の思想を要約的に示したのが、般若経なのである。 ・般若経というのは、経典群のグループ全体の名前だが、その膨大な般若経典類のエッセンス、中心という意味なのが般若心経である。 2 「方便」――結果にこだわるな ■成仏をさまたげる「三毒」 ・親鸞は、私たちが念仏を称えようと思う心を起こしたとき、その瞬間に救われているのだという。 ・だから、念仏はヘルプミーではなく、サンキューになる。仏陀への感謝である。 ・自分が救われたことを感謝するのが、念仏なのだ。 ・これは、目的と手段の逆転である。いいかえれば、仏になるためではなくて、仏である自覚を持って生きろということだ。 ・空海と道元と親鸞という日本仏教の三大傑人がたどりついてのは、いずれもこの境地だった。 ・鈴木正三は、「勝つ」ということを、戦国のように敵に勝つことではなく自分に勝つことだとして、次のように言っている。 「己に勝つを賢とし、己が心に負けてなやむを愚とす。己が心に勝得時は、万事に勝て物の上と成て、自由なり。己が心の負時は、万事に負て物の下と成て、うかぶ事あたわず」 ・人々がみんな即修行のつもりで働くから、経済成長という結果が生まれるのだ。 ・これは一九六〇年代の高度経済成長にも、あてはまるだろう。あのころ、たしかに人々は即仏行のようなつもりで働いたのである。 ・これは、たとえば『戦艦大和』の著者、故吉田満氏の『戦中派の死生観』や『平和への巡礼』に現われている。 ・これらの人は廃墟の日本を何とかその状態から向上させようとした。そして、これは当時まるで不可能な幻想のように思われた。それを、働くことを「方便」すなわち、その行程自体を目的化して行い得たといえる。 3 「布施」「縁」――恩義は忘れよ ■「三輪清浄の布施」 ・相手がかわいそうだから、何かものをあげるというよりも、まず自分が喜んで捨てるという気持、これが喜捨あるいは布施の原点なのである。 ■縁とは相互依存関係 ・縁というのは、たしかに仏教から出た言葉だが、では仏教が教えている縁とは何か。それは、相互依存関係のことである。 ・因果というのが、時間的相互依存関係、これに対して、空間的相互依存関係が縁、もう一つ論理的相互依存関係が空なのである。 ■恩義を忘れよ ・「 このことわざは、ある意味では非常に利己的な考え方に立っていて、情は結局は自分に戻ってくるものだから、かけてやりなさいということをいっている。 ・結局は、自分のためだからという考え方には、相手は入っていない。 ・多くの国人たちにとっては血縁だけが信頼できるものなのである。 ・ところが、日本人は血縁以外にもいろいろ縁をつくれるというところがある。情で縁をつくるわけだ。 ・受けた恩を忘れろと命じているのが宗教である。 ・キリスト教やユダヤ教では、神に感謝するというのが特徴である。 ・恩をほどこすにしても、情をかけることにしても、それを保証するものとして神がいるということなのだ。 ・日本人にはそれがない。保証がなくて、あるのは個々の恩、個々の情という事例だけである。 ■「三綱五常」の大原則 ・日本人がよく口にする言葉で「だれだって平和を望んでいるのだから」というのがある。これには外国人の多くが、そうとう頭にくるらしい。 ・彼らにいわせると、「どうしてそんなことがいえるのだ。戦争を望んでいるソビエトがいるではないか」というわけである。 ・もう一つ、外国人が反発を感じる言葉に、「嘘をつくのは悪いことだから」というのがある。 ・彼らにすると、仲間をだます嘘は悪いが、敵に嘘をつくのは当然ではないかということになる。 ・結局、彼らには、いつも敵と味方が、何が絶対的な中心か、がはっきりしているのである。 ・中国では、「三綱五常」という大原則があり、まず父子親ありで、これは絶対。次が君臣義あり、それから夫婦別あり、長幼序あり、朋友信あり、と五つ並んでいる。それもプライオリティーがあって、父子のためなら君臣の義は否定してもいいのである。 4 「因果」――運命に耐えよ ■「自業自得」の原則 ・因果については、仏教では原則がはっきりしている。自業自得というのが、動かすことのできない大原則だ。 ・仏教の基本思想は「縁起」ということで、これは相互依存関係を示している。いわゆる縁である。 ・この中に、論理的相互依存関係、空間的相互依存関係、時間的相互依存関係があるが、この時間的相互依存関係が因果であり、自業自得の法則である。 ・では、仏教のいう「悟り」とは何か。この時間的、空間的、論理的相互依存関係の法則が、ちゃんとあらわに見えるのが悟りだ、ということができる。 ・時間的相互依存関係については、因果の法則、自業自得の法則がちゃんと見えることが悟りである。 ・では、どうしたら見えるか。自分に欲があったら、それは見えない。あるいは、自分があれだけ恩をかけてやったのにという気持ちを持っていては見えない。 ・それが見えるようになるのは、あらゆる執着を断ち切って無我の状態になり、「空」の状態に立ってはじめて可能なことであ。 ・それでは、見えない、悟れない凡夫はどうしたらいいのか。 ・そこに出てくるのが、「信」という問題である。 ・自分には見えないけれども、自業自得の法則は厳然として存在するのであって、自分のいまあることはすべて自分のまいた種子の結果であると信じる以外にないのである。 ・ところが、自分はちっとも悪いことはしていないのに、どうしてこんな目にあわなければならないのかということがよくある。実はそのときはもう、信が失われているのである。 ・自分の運命をあくまでも自分ものとして受けとめるのが、仏教の信なのだ。 ・だから、信じることは耐えることである。自分のいま置かれている運命に耐えることが、仏教の生き方である。 ■「顕教」と「密教」のちがい ・仏教には、顕教と密教がある。これはどう違うのか。 ・仏教の基本にあるのは宇宙仏で、宇宙そのものを仏と呼ぶわけだが、密教ではこれが大日如来である。 ・ところが、顕教では ・宇宙仏を表から見ると毘盧遮那仏で、裏から見たら大日如来なのである。 ・この毘盧遮那仏は、沈黙の仏で、自分ではしゃべらない。 ・それで、人間の言葉をしゃべれる化身仏を派遣するのである。 ・毘盧遮那というのは太陽という意味だが、太陽が光を投げかけるように釈迦牟尼仏を十方世界に派遣して、それによって語らせる。 ・この人間の言葉で釈迦牟尼仏が説いたのが、顕教である。 ・一方、大日如来は雄弁の仏であって、自分でしゃべって教えを説く。 ・では、それなのになぜ密教なのか。じつは、大日如来がしゃべっているのは、宇宙語なのである。人間にはわからない。 ・ちょうど電波を発しているようなもので、受信機を持っている者にしかわからない。そこで、受信機を持てというのが、密教の主張なのである。 ・あるいは、受信機がほこりをかぶっているから、雑音が入って聞きとれない。ほこりを払って清らかな心になれば、正確に電波を受けとめられるというのが、密教の主張である。 ・密教は宇宙語である。あるいは象徴言語であるといわれるのは、このためである。 ・それは、私たちに理解できるような因果律の世界の言語ではない。象徴言語だから、その秘密を解さないとわからないのである。 ・因果という明確な面と、象徴言語という世界にない言葉の世界があるという二面性は、非常に興味深い。 ■過去世―現在世―未来世 ・仏教は徹頭徹尾、個人の救済を問題にしている。 ・社会だとか部族だとかは知るものか、という立場である。 ・しかし、個人の救済というのは、時間内では完結しないから、どうしても因果で説かざるをえない。 ・小乗仏教には、細かな戒律が、男子の出家者に対して二百五十、女子の出家者に対しては三百四十八と定められていた。 ・このような戒律を守らなければ、悟りはないとされていたのである。 ・大乗仏教は、そんな細かな戒律は無視してよいと主張した。そんな細かな戒律にこだわることを不可としたのである。それが「空」の教えである。 5 「知慧」――何事も度を過ぎるな ■ベン・シラの知恵 ・般若心経の「般若」という言葉は、知慧という意味である。 ・そして「深般若波羅密多」というが、「深般若」というのは「六波羅蜜」を実践すること、つまり宗教実践(仏道修行)することによってえられる知慧という意味だ。 ■「秩序」を意味する知恵 ・儒教などは封建道徳で、六道輪廻などは迷信だ、といった考え方をし、さらに現在では居丈高な西欧批判やキリスト教批判が横行している。 ・だが、三千年後まで読みつがれる何らかの思想を創造したのか、と問われれば、おそらくゼロである。 ・いわば「からっぽ」なのだが、否むしろ「からっぽ」なるがゆえに、異常なほどの傲慢さが見られる。 ・この状態がつづけば、いずれは「高ころび」という「決算」をするであろう。 ・「知恵」とは、一口でいえば、何らかの「秩序」それも「社会的秩序」だけでなく、「心的秩序」を意味する言葉、ないしは「それを知ること」「それを守ること」といってよい。 ・そして、これは神が最初に創造した。いわば「 ・その「内的・外的秩序」に対して、人間がいかにすべきかを示されたもの、といってよいであろう。 ・非常に簡単にいえば「セルフ・コントロール」の意味に使ってもよいし、知恵があるというのは、一芸一能に秀でていることを意味している場合もある。 ■全員一致の決議は無効 ・ユダヤには、「全員一致の決議は無効にする」という定めがある。 ・このほかに、有罪判決の場合、無罪との差が一票しかない場合は、その判決は無効で無罪になる。二票差で、はじめて有効、その場合は有罪である。 ・とうことは、有罪のときは反対が一票少なくても無罪になるが、有罪は賛成票が二票多くなければならない。 ・さらに民事は、公判をしてすぐ判決を下してよいが、死刑の場合は無罪ならそれでよいが、有罪は一晩おいて、翌日に下す。 ・一晩、頭を冷やせということである。というのは、無罪の場合は再審はできないが、有罪の場合はできるから、その前に、頭を冷やしてもう一度考えさせるのである。 ・裁判は神の代行をしているわけだから、誤審はぜったいに許されないのである。 ・それが多数決で行われる場合は特に危険であり、彼らは絶対に「多数絶対」とはしないのである。 ・現在のイスラエルの国会でも、同じである。全員一致だと、その決議は無効になる。 6 「精進」――努力すべからず ■「遊牧型」の文化 ・イギリスは、インドから三百年にわたって、ものすごい富の収奪をした。その富の蓄積で産業革命が行われた、というのが定説である。 ・とすると、それ以前の段階でインドは非常に豊かな国だったということになる。 ・だから、逆に生産から遊離した人口を抱えることもできたのではないかと思われる。 ・これはいずれの社会でも同じで、「軍隊」という生産から遊離した人口を抱えることは、どの時代でも、豊かな国にのみ可能なことである。 ・精進というのは努力だが、日本人がなぜこんなに勤勉なのか。 ・努力主義者なのかというと、基本的には、やはり稲作民族だからにほかならない。 ・せっせと肥料をやり、草とりをし、怠けることができないからである。 ■在家中心の修行 ・インド仏教では、出家者というのは社会から飛び出した者である。そういう出家を許すだけの、社会の余剰の富があった。 ・同時に、飛び出た者は自分の欲望を抑えること、いわゆる小欲知足によって、できるだけ社会に負担をかけないように努力するわけだ。 ・だから、仏教の基本は満足することで、これでいいのだと、できるだけ自分の欲望をへらすことにある。 ・それが日本では、逆に欲望をふくらます「精進」になっている。これがいわゆる日本流仏教である。 ■「中道」は「中庸」にあらず ・仏教の精進では、もうひとつ「中道」の精神がある。苦行でも楽行でもだめである。苦行と楽行のちょうど中間をいくということだ。 ・「中庸」の基本的な定義は、「喜怒哀楽未だ発せざる、これを中と謂う、発してみな節に ・この場合は、精神が喜怒哀楽といったものに動かされていない状態のことで、平均値ではない。いわば「平静」に近い意味で、その状態でいれば「物ごとの節度と合致する、これを和と謂う」という意味である。 ■ユダヤ教に聖職者はいない ・聖書には「精進」という言葉はない。 ・イスラム教にも、聖職者はいないし、祭司階級はない。 ―― 完 ―― |