
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2020年05月09日 土曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |
11 |
20.05 |
奇跡のごとく 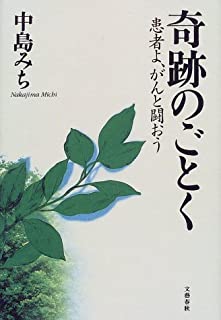 |
中島みち |
文藝春秋 |
◎ |
Ⅰ もう一度、白衣を着たい! ●一日を、ひとの倍生きられる病後 ・身体じゅうの細胞の一つ一つまで酸素を行きたらせるような昂然の気というか、生きる意欲を持つことは、免疫力にも関係するように思えます。 ●一生に一度くらいは奇跡のようなことが ・今の医学の常識では治らないとされているような進行がんを、抗がん剤で治そうというような治療をした場合、感染症の併発はリスクとして必ず存在する。 Ⅱ のたうつ食道、からくも命得て ●食道がん手術から七年余 ・病気に対して前向きに治療を受けられた方、常に生きようと努力されている方、心を明るく持とうとされている方、そういう方が長生きしておられます。 ・明るい方は長生きする、落ち込んで鬱になる方は転移もしないうちに手術しても再発する。 ・「病気を対極に置いて、病気があるから自分が生きているようなことになったのでは、逆でしょうね。やはり自分の中に病気というものを取り入れて、病気である自分がどのように生きたらよいのかを考えてみたほうがよいのでは。それには、一日一日のことをなおざりにせず、ちゃんと決まったことはキッチリやること、お日様が昇って沈むがごとく自分の一日も一歩一歩をきちんと踏みしめる」 Ⅳ 消滅した巨大な転移巣 ●大腸がんからの復帰 ・食物繊維を食べると、便の量が増えて腸の中での停滞時間が短くなって、発がん物質が腸の粘膜に接する時間が減ってくるので、大腸がんの予防には非常に良いと考えられている。 ・また、繊維そのものが腸内の細菌に影響を与え、発がん物質ができるのを抑えるという説もある。 Ⅴ 「諦めたら、そこで終わりです」 ●ホクロのがん・メラノーマの肺転移手術から十五年 ・植物は病原菌に侵されても免疫力によって自分で病気を治す力を持っています。 ・動物の場合にも身体の免疫機構さえしっかり強化されていれば病気に負けない。 Ⅵ 肺がん、そして、がんと闘う患者学・医者学 ●我々が治療をして、あとは神が治し給う ・がんとの闘いというのは、肉体的な闘いだけではなく精神的な闘いでもあり、今のがん医療が「こういう治療をすればこうなりますよ」と患者に明確に応えられない以上、患者に課される精神の闘いの部分はより大きくならざるを得ない。 ・人間というのは、自分を ・閉じこもってしまった人も、なんらかのアプローチで周りの社会へ引っ張りだし、何かしら目的を持たせることに成功すると、治療もうまくいくんです。 ・がんという病気のつらいところは、いつも転移や再発の不安に晒されているところでしょう。 ・がんは転移していても、未来永劫、静かにしているものもあるでしょうし、身体の具合によって、ストレスによって呼び覚まされるものもあるかもしれない。 ・人間の身体の中に、目には見えないけれど、例えばストレスというようなもので、免疫抵抗を揺るがしたり昂めたりしているようなメカニズムがあるのではないかという研究もされています。 ・ストレスが中枢神経を刺激して、脳幹から脳下垂体を刺激して、内分泌が大変乱れて、そのためにT細胞などのリンパ球の勢いが落ちるということは生物学的に証明されています。 ・笑いは免疫力を高めるという説もあります。 ・毎日幸せに生きているということは、身体の中で一生懸命リンパ球が働いていてくれるから。 Ⅶ 尊厳ある生のためには、告知はどのように ●「病名告知」は必要、「余命告知」は慎重に ・「患者の権利」の源流は、アメリカの公民権運動や女性解放運動、消費者運動などの一連の展開の中で一九七三年に採択された、アメリカ病院協会声明「患者の権利章典」等から発する。 ・見逃せないのは、訴訟社会であるアメリカの医師や病院にとっては患者に全部伝えて治療法まで選ばせるほうが、訴訟防衛に有利であるということである。 ・また、医療費が日本とは桁違いに高額な上に、いまだに国民皆保険の悲願はならず、国民の六人に一人が全く何の医療保険にも加入していない無保険者であるという不安定な状態の中では、本人が費用を頭に置いて治療法を選択するのは当然のことである。 Ⅷ 宣言・「患者よ、がんと闘おう」 ・日本での化学療法の問題点というのは、臨床で患者を受け持つ化学療法の専門家が極度に少ない点にあると思う。 ・そもそも、日本の医学教育では臨床腫瘍学の講座はほんの一部の大学にしか置かれていない。 ・年に四十万人余もの人にがんが発見されるという今日、化学療法の専門家すなわちメディカル・オンコロジストを育てることは、患者側からも切実に望まれることだと思う。 ・がんにどう対応できるかは、つまり、一生をどう生きてきたかにかわる。 ・人間、幸せに恵まれつけると、幸せに生き続けるための努力をすることに不精になる。失うもの大きさに較べれば、その努力は、ほんのささやかなもので済んだはずであったのに。 ―― 完 ―― |