
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2020年06月10日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |
15 |
20.06 |
松下村塾 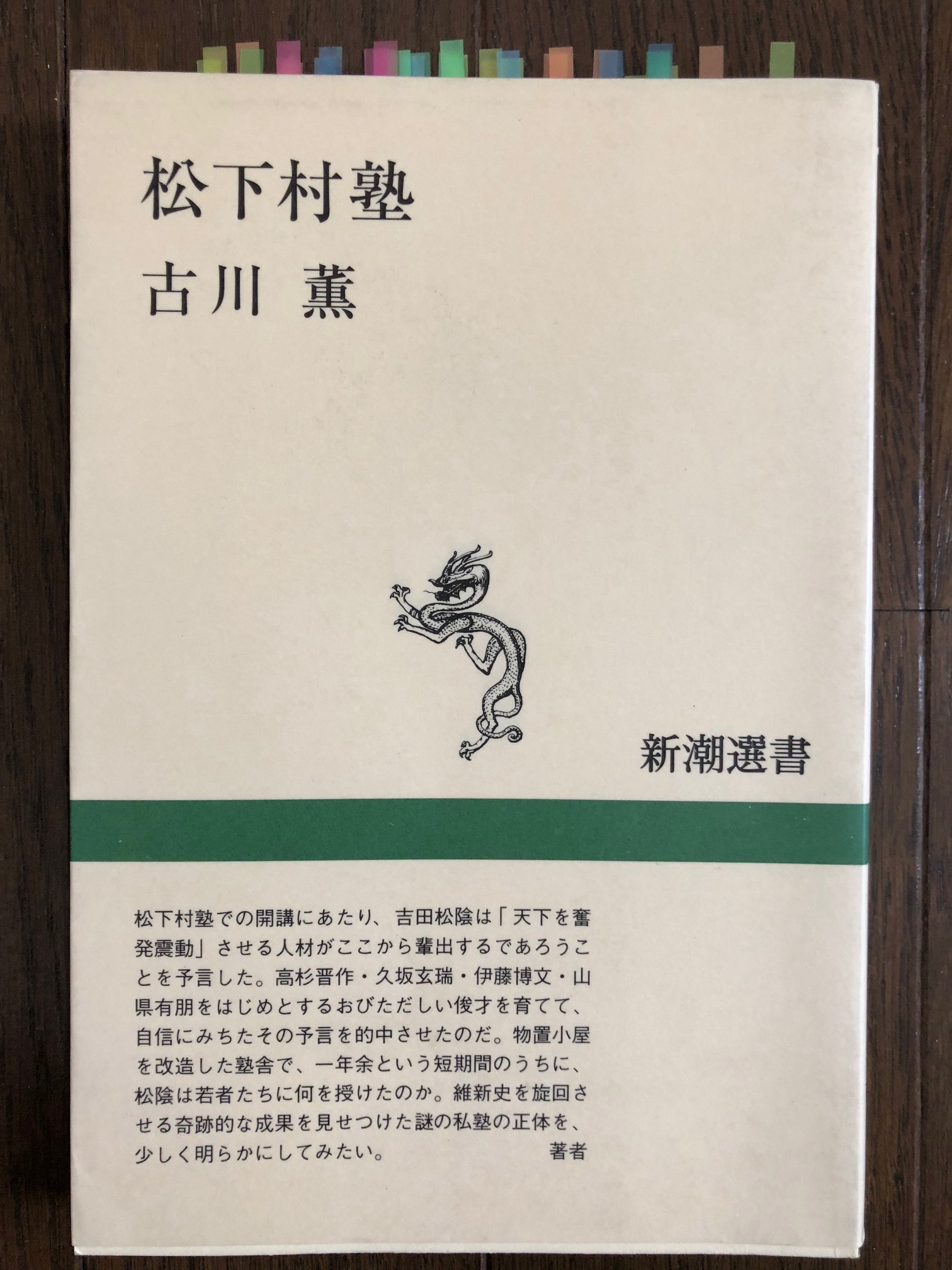 |
古川 薫 |
新潮選書 |
◎ |
Ⅱ 割拠の思想 月謝 ・塾生たちの学費はどうなっていたか。 入塾するとき手土産程度の束脩は受け取った。束脩は入門のしるしとして師に贈る礼物だが、もともと入門の儀式を言ったもので、月謝は不要だった。 ・幕末の私塾の月謝は、普通で年間一両二分、それと盆と暮れのつけとどけをふくめ倍近くになる。今でいえば二十万円前後というところか。 ・適塾は比較的安く、それでも年間一両弱、咸宜園が〇・五両だった。 ・萩城下では、そうした有名塾ほどでないにしても、教師が塾の経営で生活している以上相当な謝礼を出さなければならない。 ・松下村塾の塾生の多くは下層の家に生まれた人々だから、余分の学費を調達して私塾に通うなどは贅沢といってよく、学問のある父親が家庭で授ける家も多かった。月謝のいらない松下村塾は、それだけでもありがたい存在だったにちがいない。 ・寄宿生は米を持ってきて、調理は自分でした。 ・松下村塾は、完全に松陰の奉仕によって経営された。杉家からかなりの経費が注ぎこまれたはずで、いずれにしても「学商」ではなかったのである。 友情 ・松陰は身分差を一切無視した。学問をする上に、身分意識など余計なものだとし、人間は平等であるという松陰の信念は、その言動の隋所にあらわれている。 ・封建社会の人間関係は、すべて縦につながっている。松下村塾では、塾生の身分、年齢の別にこだわらず横に並べ替えた。 ・松陰は塾生を「諸生」と言い、「諸友」と呼んだ。 Ⅲ 指導と感化力 引き出し喚起すること ・松陰は塾生教室の中二階で著述・読書し、終日ほとんど塾舎ですごしたので、寄宿生にかぎらず文字通り塾生と起居を共にしたことになる。 ・松陰はいわば舎監も兼ねたわけだが、塾生を「諸友」と呼び、友人として彼らの輪の中に入り、若い人たちの行動を一々規制するようなことはしなかった。 ・その間、塾生の一人ひとりを観察し、その者の資質を見抜き、それに沿って指導したが、相手の境遇、性向などによって助言・方法はそれぞれに違っていた。 ・本人の気づかない長所を発見し、それを褒め上げることによって自信を持たせ、さらに向上させるように導いた。まさに松陰は educate (教育する)というよりも educe (引き出す、喚起)したのである。 ・松陰の強烈な感化力の秘密は、生得身につけていた人間的な魅力であったにちがいないが、あらゆる機会をとらえて親しく塾生に接近していく指導者としての努力と、するどい監察の視線、相手を選ばない誠実な姿勢にあるといえるだろう。 相労役 ・松下村塾には五ヵ条の規則が定められていた。 一、両親の命必ず背くべからず。 一、両親へ必ず出入を告ぐべし。 一、 一、兄はもとより年長又は位高き人には必ず順ひ敬ひ、無礼なる事なく、弟は言ふもさらなり。品卑き年少なき人を愛すべし。 一、塾中に於てよろづ応対と進退とを切に礼儀を正しくすべし。 右は第一条より第五条に至り、違背あるべからず。若し背く者は第一条の科は必ず座禅なるべし。その他四条は軽重によりて罰あり。 ・杉家の庭内には広い畠があり、春や夏になると松陰はよく草むしりをした。一緒に作業すると除草しながら読書の方法や歴史の話をしてもらえるので、塾生にとってはそれも楽しみだった。 ・塾生たちと共にそうした作業にあたることを松陰は「相労役」といった。 ・共に労働の汗を流すとき、人の心が最もよく通いあうのだと松陰は信じていた。 Ⅳ 何を教えたか 学科 ・松陰の『丙辰日記』(安政三年)は、学習の記録である。 ・その表紙には、「身体髪膚之れを父母に受く。敢えて毀傷せざるは孝の始めなり。身を立て道を行き、後世に名を揚げ、以て父母を顕わすは孝の終りなり」とう『孝経』の一節が書かれている。 ・松陰の高弟高杉晋作は、のちに外国連合艦隊来襲に備えて奇兵隊を組織して、いるが、その基本構想は松陰の『西洋歩兵論』に酷似している。 ・文久三年、高杉は杉家から松陰の遺著を借り出して読みふけっている。彼が奇兵隊を結成したのは、その直後である。 ・また安政四年に入塾し、翌年の松陰投獄まで松下村塾にいた山田市之充は、後年の陸軍中将山田顕義である。 ・やがて市之充が “用兵の奇才” といわれる軍事専門家になる基礎は、松下村塾でつちかわれたものかもしれない。しかも山田が最も得意とする作戦は、しきりに松陰が説いた「衝背戦」なのであった。 ・『孟子』は松陰の生涯をつらぬく思想の中心を流れており、塾生にも強い影響を与えた。 評価 ・松下村塾も一応の評価基準がもうけられてはいた。 ・学習態度の評定を三段階、さらに六つに分けて、これを三等六科とし、上等とは「進徳・専心」、中等は「励精・修業」、下等が「怠惰・放縦」とした。 ・評価の基準を知識の量におかず、学問に向かう姿勢にしぼっていることをあらわしている。 ・効果判定としては漠然としたもので、しかも塾生をこれに当てはめて評価し発表した事実はない。 ・松下村塾には、テストの成績を争って人の上に立とうとする競争原理はなかったのである。 ・試験の成績を争う激烈な競争は、互いの足を引っ張り合う心理がはたらき、冷えた人間関係を生じさせたりもする。 Ⅵ 塾生架空座談会 「村塾のころ」 天野御民(冷泉雅二郎) ・先生は「書を読んで自分が感じたことは、抄録しておけ。それを読み返していると以前の愚に気づく。それは知識が上達したしるしである」と。 あとがき ・松下村塾は、自由を失った一人の人間が複数の若者に思想と行動をバトンタッチする後継者育成の教場として、わずかな期間存立した。松下村塾で松陰がさずけたのは人間の学だった。 ・「学は、人たる所以を学ぶなり」とし、あくまでも学問を通じて真実とは何かを問い続けながら、共に考え共に生活して若者の心を揺り動かしたのは、並みはずれた感化力であり、それこそが松陰における学徳というものだった。 ・短期間に松陰がなしとげた驚異的な成果の秘密は、感化力の一語に尽きる。 ―― 完 ―― |