
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年01月11日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |
34 |
20.09 |
決定版 がん休眠療法 個人差重視の抗がん剤治療革命 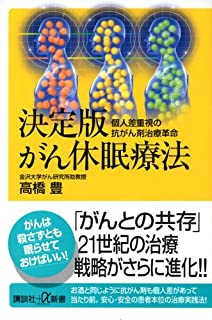 |
高橋 豊 |
講談社+α新書 |
◎ |
はじめに ・従来の抗がん剤治療では、どうしたらがんが消滅するか、小さくできるかに、医師たちは必死でした。 ・がん休眠療法は、発想が逆です。がん治療の地動説とも言えます。がんを殺すのではない。小さくならなくてもいい。がんを眠らせればいいのです。これが治療の目的です。 ・がん細胞とは、もともと眠っていた正常な細胞が、目を覚まして暴れているようなものです。ですから、本質的ながんの治療とは、暴れん坊を再び眠らせ、おとなしくさせることです。これが、がん休眠療法の目指すところです。 第一章 延命はどうしたら可能になるか 人体の形成とがんの発生 ・遺伝子の中で、主に細胞の増殖に関与する遺伝子に異常が起こると、増殖が止まっていたはずの正常細胞が再び増殖を始めます。これが、がんの正体です。 ・全細胞六〇兆個の約一〇パーセントにあたる六兆個あたりまでがん細胞が増加すると、ヒトは死にます。 治療目的は進行度で変わる ・転移がほとんどない早期がんは、局所的な病気です。通常の ・がんという病気は、進行度によって治療目的(治癒か、延命か)、治療方法(手術などの局所療法か、抗がん剤による全身療法か)が異なってきます。 ・手術と抗がん剤治療では、治療の目的がそもそも違うのです。前者の目的は治癒ですが、後者は延命です。 第二章 二一世紀の抗がん剤・分子標的剤 血管新生抑制剤アバスチン ・がん細胞は増殖する時、増殖しやすいように、新しい血管を自分でどんどん作ってゆくのです。これを、病的な「血管新生」と呼びます。 ・そして、がん細胞や周囲の細胞から「血管新生因子」と呼ばれる分子が産生されることによって、血管新生は促進されます。 ・この血管新生をブロックすれば、血管を新しく作ることが難しくなり、その結果、がん細胞の増殖が阻害されるというのが、「血管新生抑制剤」です。 分子標的治療の特徴とは 1.標的とする分子が発現している人に特異的に効く。 2.毒性(副作用)のグレードは低いが存在する。 3.主な効果は縮小よりもむしろ増殖抑制。 4.抗がん剤との併用は、現在のところ、ほとんどのがんで不可欠。 ・分子標的剤の特徴こそが、がん治療の本当の姿である可能性が高いということです。 ・それは、分子標的剤が、がんの本質的な原因である増殖を果てしなくつづける分子の働きを抑え、増殖を抑制する薬剤だからです。 第三章 抗がん剤治療革命の必要性 抗がん剤とはすべての細胞の分裂、増殖を阻止する薬です。それは、がん細胞だけでなく、分裂・増殖している正常細胞(白血球、消化管粘膜、毛髪など)も殺します。抗がん剤とは、がんに効く薬というより、がん こうして抗がん剤は誕生した ・DNA合成などを阻止するように開発されたのが、「抗がん剤」と呼ばれる薬剤です。 脱・縮小至上主義 ・抗がん剤評価システムの欠点は何か。まず第一点――最大の問題は、その「縮小至上主義」にあります。 ・延命期間は縮小のみでは決定されない。 抗がん剤の適量には個人差がある ・抗がん剤評価システムの第二の問題点は、個人差をまったく無視していることです。 ・抗がん剤の適量には個人差があります。 ・薬剤によって異なりますが、五倍から五〇倍異なると報告されています。 ・分解酵素量の個人差によるものです。 飲む抗がん剤TS-1登場 ・TS-1は経口の抗がん剤で、5-FU(フルオロウラシル)という抗がん剤をもとにして作られたものです。 ・TS-1の特徴は、何といっても、5-FUの分解酵素(DPD)をブロックすることです。そのため、5-FUが分解されにくくなり、血中濃度が高まり、効果が高くなります。 第四章 個人差・継続重視の抗がん剤治療 休眠療法が「患者に優しい」理由 ・一定量の抗がん剤が投与されると、体内の分解酵素によって抗がん剤が分解されます。この酵素の量に個人差があるため、血中濃度にも個人差が出てきます。血中濃度に比例して、毒性(副作用)のグレードも上がります。 ・このことは、アルコールと同じです。アルコール分解酵素が少ない人の体内ではアルコール血中濃度が上昇し、分解酵素が多い人では血中濃度が低くなります。この血中濃度と酔いの程度とが相関し、濃度が高くなるほど、深く酔うことになります。 ・お酒に強い人、弱い人があるように、抗がん剤に対する「個人差」があるということです。 投与は多ければ多いほど良いのか ・毒性とは正常細胞の障害です。これは、薬剤の血中濃度と深い関係があると考えられます。 休眠療法の臨床試験スタート ・現在の抗がん剤治療は、ヒトの限界の投与量による治療しかありません。 なぜ治療関連死は起きるのか ・毒性と効果は表裏一体です。 第五章 がんの種類別にみる休眠療法 [胃がん] ・がんは大きくならなければ何の影響もない。 ・糖尿病では血糖を下げる薬剤やインシュリンで、高血圧ならば降圧剤でかなり長期間コントロールすることができますが、がんではなかなかそうはゆきません。がん細胞に薬剤耐性が起こるためで、薬が効かなくなってくるのです。 [膵がん] ・本当は余命は人によって異なるのです。平均値は個々の患者さんにとって大きな意味はない。 [肺がん] ・肺がんは、極めて進行の速い小細胞がんと、それ以外の非小細胞がんの二つに分類されます。 ・小細胞がんは手術の適応はなく、非小細胞がんは、進行度によって手術か抗がん剤のどちらかを選択します。 ・TS-1は、肺がん治療薬として二〇〇四年に認可されました。(シスプラチンと併用という形ですが)。 どんな治療を選択すべきか ・どんながんでも手術で治療が可能であれば、手術を選択すべきです。そして、手術が適応されない場合には、抗がん剤治療が中心となるわけです。 ・ここで、がん細胞がほぼ完全に消失するなどの著名な効果が得られないがんに対して、休眠療法の適応があります。つまりは、一時的な効果で延命を得るのか、それとも継続治療で延命を得るのかの二者択一です。 附章 休眠・延命が得られる他の治療法 がんになっても予防はできる ・がんの予防とは、がんの発生を阻止するというより、がんが大きくなるのを邪魔することなのです。 ・予防は今からでも間に合います。がんの増殖は指数関数だからこそ、少しでも早く始め、長く継続することこそが重要なのです。 おわりに――がん休眠療法の功罪 がんと共存して天寿をまっとうする ・がんと共存しながら天寿をまっとうできれば、がんとの闘いに勝ったことになるということです。 ・さらに言えば、がんとの共存こそが、多くの手術不能がんや再発がんに対する、抗がん剤治療の目的とすべきというのが、休眠療法の発想です。 ・拡大解釈すれば、がんを糖尿病や高血圧のような慢性疾患としてとらえ、病状を悪くしない、あるいはコントロールすることが治療の目的ということになります。 ・治療の目的を完治から共存へ変えれば、末期ガンでも希望は充分ある。 ・つまり、がんの原因である、増殖を絶え間なく継続させている遺伝子、分子をすべて抑制できれば、増殖を止めることが可能であり、そうすればずっと共存できるのではないか。 ―― 完 ―― |