
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2020年10月15日 木曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |
36 |
20.10 |
彷徨の王権 聖武天皇 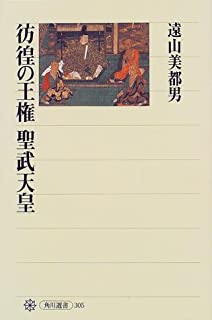 |
遠山美都男 |
角川選書 |
◎ |
第一章 待たされた即位 一 岡宮御宇天皇――祖父、草壁皇子 天皇が誕生する ・天皇という地位は、壬申の乱を通じて、乱後の天武朝に誕生した。 ・天皇号ができる以前は、治天下大王という称号が使用されていた。 ・大王(オオキミ)とは王族に対する尊称にすぎない。王族の数だけ大王とよばれる者がいたことになる。したがって、大王だけでは国家を代表する地位をあらわす称号にはならない。そこで、日本列島やその周辺に対する統治行為を意味する治天下の語を冠したのである。五世紀末には治天下大王号は成立している。 ・治天下大王の支配がおよぶ天下とは日本列島に限定されるものではなく、朝鮮半島の南部もふくむものであった。 ・倭国とよばれていた日本は、対朝鮮という関係においてのみ、超大国=中国と対等であるという国家意識を抱いていた。 ・大王や王族に対する貢納・奉仕を恒常的に吸い上げるシステムが ・天皇とは皇帝(天子)を指名する天帝の別名であり、あるいは道教において最高の神格である天皇大帝のことであった。 ・東アジアにおいては唐の第三代皇帝、高宗が一時期ではあるが、皇帝号に代わり君主号として採用したことがあった。 ・中国の皇帝が使用した君主号を治天下大王に代わって採用したということは、百済・高句麗の滅亡という天下瓦解の後もなお、倭国が朝鮮半島に対して一定の支配権をもっているという点では中国と対等の立場にあるという国家意識を再生させたことを意味している。 二 御狩立たしし時は来向かふ――父、文武天皇 持統即位―珂瑠皇子の立場 ・持統の場合に限らず、古代において「中継ぎ」の大王・天皇の存在が指摘されるが、大王や天皇に集中した権力(王権)を担い、それを行使するのに、はたして「中継ぎ」などという役割が成り立つものであろうか。 ・「中継ぎ」とは、本来それを担う資格も能力もない者がその任にあたるという語感がつきまとうので、これを大王権力や天皇権力の継承問題において用いるのは、やはり妥当ではないように思われる。 ・また、ある大王・天皇が「中継ぎ」であったかどうかというのは、あくまでも歴史の結果をふまえた一定の評価であって、いわゆる「歴史の後知恵」にすぎないともいえるであろう。 ・持統天皇は、それ以前の女性大王たち(推古・皇極=斉明)と同様に、大王に集中した権力の一部を担うことがあった前大后という資格のもとに即位したとみられる。 ・世代・年齢を重視した王位継承を行なっていた段階では、即位資格をもった皇子が集中してあらわれ、王位継承をめぐる紛争が激化する危険が生ずることがあった。前大后はそのような時に、紛争の発生と激化を未然に抑える役割が期待されて大王権力を継承したと考えられる。 ・持統の場合、草壁・大津といった最有力の皇位継承候補を失った段階で即位しているのであるが、高市皇子を筆頭に即位資格をもつ天智・天武の諸皇子が多数存在したので、かれら相互の王位継承をめぐる争いを紛糾させないために、天武と共治の実績にもとづき即位したということになる。 「衆議紛紜」 ― なぜ紛糾したか ・皇太子の地位は飛鳥浄御原令に規定されていたと考えられる。 ・それは持統天皇の即位に合わせ、あたかもそれを記念するかのように六八九年六月に施行された。これにより、天皇位を継承する唯一の予定者の地位が制度化されたのである。 草壁皇子の血統と狩猟 ・六九七年八月一日、持統天皇は珂瑠皇太子に譲位し、珂瑠は皇太子としての約半年間を経て即位した。 ・皇太子というプロセスを経て天皇になったのは、この文武天皇が最初であった。 ・初代天皇である天武も、つぎに天皇となった持統も、皇太子という階梯を経ることなく、いきなり即位した。 審査される首皇子 ・七世紀後半になって、天智天皇が世代・年齢に代わる新しい王位継承の基準として血統という価値を創出しようとしたのは、世代・年齢にもとづく大王の選出と擁立が代替わりごとの紛争の火種になったことを憂慮し、それを乗り越えようと考えたからであった。 ・その結果、治天下大王から日本天皇に変わって以後は、人格・資質に加えて新たに血統が、天皇の条件として厳しくもとめられるようになったのである。 三 年歯幼稚にして――元明から元正へ 元明天皇の即位資格 ・元明以前において、大后(皇后)たちは一体どのような理由で即位することになったのであろうか。それは、王位継承候補が複数存在し、かれらの資格や実力が伯仲しており、これを放置すれば 即位できない皇太子 ・首皇子は皇位継承資格者のひとりであり、皇太子の地位にもついていたが、早い段階からその即位が確約されていたわけではなかったことを重視すべきであろう。 ・皇太子制ができて間もなく、皇太子の実例も文武ひとりしかいなかったこともあって、皇太子という階梯を経ることが、その人物の皇位継承をかならずしも保証することにはならなかったのである。 ―― 完 ―― |