
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年01月31日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |
36 |
20.10 |
福沢諭吉 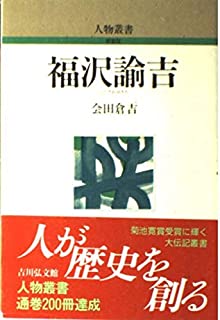 |
会田倉吉 |
吉川弘文館 |
◎ |
はしがき ・福沢諭吉はまれにみるスケールを持った人物である。 ・人並みすぐれた体格にめぐまれて、身体が頑健であると同時に、その精神がまたはなはだ強じんであった。 ・そして、つねに闊達明郎、いささかもよどみを見せない言動のなかに、きっぱりとした筋をいつもとおしていた。 ・きわめて透徹した理性をもってあらゆるものの本質を鋭くとらえながら、そのうえで決して現象を無視するような行動に走ることはしていない。 ・一面いかにも細心でよく些事に通じながら、そのために大局を見失うことなく、本質と現象とをはっきり見さだめる識見を万事に欠かさなかったのである。原理と現実の微妙な調整に卓越していたものといえよう。 ・真理は真理、人事は人事で、絶対的なものと相対的なものとを峻別し、それを巧みに調和させるすべを心得ていた。 ・のみならず、いついかなるときでもきっと現実をみすえながら、それでいてその現実には巻き込まれないで、それよりもはるかにひろい視野に立ち、大所高所からこれを冷静に客観視する余裕を持っていた。 ・福沢諭吉は単なる妥協はもとより認めず、おのれの損得をはかりにかけて態度をきめるようなことは断じていさぎよしとしていない。絶対にまげることのない確固とした信条をあくまで堅持していたのである。 ・すなわち、「人生を万物中の至尊至霊のものなりと認め、自尊自重苟も卑劣な事は出来ない」と自伝で述べていっている点がそれである。 ・福沢諭吉は最も人間を愛し、人事に身をくだいた。 ・いつでもその時代における先端にいて、目標と針路をたがえることはなかったし、さらに注目されるのはそれへの達成の方策であろう。 ・福沢諭吉はそこに独断を許さず、急変をも期待もしない。一個独立の市民が各自で真剣に思案した結果、衆人の意向が定まって、事はすすむのでなければならないのであった。 ・福沢諭吉はやはり大きな包容力を持った真の教育者で、独立市民の育成をひたすら願ってやまなかったのである。 第一 誕生 誕生日 ・福沢諭吉が生まれたのは天保五年十二月十二日、太陽暦に換算すると、一八三五年一月十日にあたる。 第五 少年のころ 天性の大酒飲み ・諭吉は生来の大酒飲みで、物心のついたときから大好きであったという。 第八 緒方洪庵の知遇 諭吉の文章と洪庵の教訓 ・諭吉の文章はいわゆる福沢流とも称すべき独特の文体で、きわめて平易通俗のうちに、伝えんとするところをいいつくし、読むものをしてうなずかしめずにおかない強い説得力を持っている。 ・諭吉はそのためには、つねに一字一句をゆるがせにしない最新の努力をはらい、とりわけ万人にわかるようにと心がける。 第二一 文明の諸活動 断髪の時期 ・諭吉が断髪したのは明治三年(一八七〇)九月ごろのことであった。 無用な刺激を避く ・実際に散髪・廃刀の自由が認められるにいたったのは翌四年八月であり、なかでも断髪のすこしく増加しはじめたのは同六年三月に天皇がそれを実施してからとされる。 つとに刀剣を売り払う ・諭吉は、慶応二年(一八六六)の秋ごろにはもう、当時まだ武士の魂とまで称されていた刀剣を、スポーツ用の居合刀一本を除きことごとく売り払ってしまっていた。 ・世にいう廃刀令の布告が明治九年三月であることを思えば、ずいぶんな英断といわなければなるまい。 「京都学校の記」 ・明治四年十月から東京府では新たに邏卒三、〇〇〇人を置いて治安の取り締まりにあたることになったが、その制度のもとが諭吉の調査になる。 七曜制の採用 ・ついで、翌五年から諭吉は慶應義塾に七曜制を採用している。 ・これは、明治元年すでに世に先んじていったん実施したのであるが、一時中止していたのを再び施行したもので、文部省が官立の諸学校にそれを及ぼしたのが同七年三月、官庁の休日が日曜日に一定したのが九年三月であったのに比べれば、ずいぶん早い時期のことといえよう。 『改暦弁』と『帳合之法』 ・同六年一月刊行の諭吉の著『改暦弁』はこの年から採用されることになった太陽暦につき、懇切にその利便を説いて一般に示したもの。 ・同年二月に出版した『帳合之法』は近代的な簿記法をわが国でまっ先に紹介したものである。 「文明開化」の造語 ・「文明開化」なるこのことば自体が、おそらくシビリゼーションの訳語として諭吉あたりの創案になるのではないか。 ・『西洋事情』外編にその造語がはやくも見られる。 「演説」 ・わが国で演説がはじめて試みられたのは明治六年(一八七三)のことで、諭吉を中心に慶應義塾社中のもの数名が西洋のスピーチ・デベートの法を研究して行なったものである。 ・「演説」なることばそのものがほかならぬ諭吉の発案によるものなのであった。 諸会社の設立斡旋 ・現在の丸善の前身である丸屋商社は、諭吉の門に学んだ早矢仕有的により、諭吉の支持を得て明治二年一月にわが国最初の近代的な会社組織をもって創設されたものであった。 ・あるいは森村市左衛門に外国貿易をすすめたのも諭吉ならば、同十三年七月にやはり右の早矢仕を社長として貿易商会がつくられたときにも、諭吉はかげながらこれを応援している。 ・また、いまの東京銀行の前身である横浜正金銀行の創立は同十三年二月のことである。諭吉が時の大蔵卿大隈重信そのほかに連絡斡旋して設けたもの。 ・翌十四年七月からわが国最古の生命保険会社として開業した明治生命保険会社もまた、諭吉の周辺のものたちによってつくられたのであった。 民間事業の育成 ・明治十四年に民間企業として始められた ・上からの政策よりも、どちらかといえば諭吉はつねに民間における事業の育成に多く力をいたしたのであった。 第二二 官民の調和策 ・諭吉は終始、官に仕えることをがえんじなかったし、実際の政治に直接たずさわることを生来、好みもしなかったのである。 「民権論の首魁」 ・真の官民の協調は官と民があくまで対等でなければならず、官は十分に民意を尊重しなければならない。その意味では、政府がすみやかに国会を開くべきことを諭吉ははやくから主張した。 ・諭吉は急進的ではないけれども期を見てはそれを推進していたのである。 『国会論』 ・ことに、明治十年代にはいってその運動のにわかに盛んになったのは、諭吉も自伝にいっているとおり、まさしく諭吉の『国会論』が火つけ役をつとめたといっていい。 第二三 新聞の発行と世論の指導 『時事新報』の発行 ・福沢諭吉は、民間独立のものとして新聞の発行を決意し、それによって新たに世論の指導にあたることになった。『時事新報』である。 ・明治十五年(一八八二)三月一日の創刊号にかかげられた同紙発兌の趣旨によると、諭吉がここにかたく中道主義を守って漸進に徹し、つとめて極端を排しながらも、なにものにも顧慮することなく、着実に文明の進歩を目ざそうとした点は注目すべきであろう。 第二六 独立自尊の鼓吹 ・福沢諭吉が生涯をかけて力説したものはあえて学問の独立のみに限らず、人生のすべてにおいて「独立」の一事であったといってよかろう。 独立自尊 ・また諭吉と言えば「独立自尊」の語も切り離せまい。この四文字は実に諭吉の法号にまでつけられているほどなのだ。 個人の独立 ・諭吉が幕末以来ひたすら洋学に励み、かつそれをすすめた根本はそもそもそれ自体がすでに一身一国の独立を念じてのことなのである。 ・しかも、そのような諭吉の本領といえば、それこそあくまで各個人ひとりひとりの真の独立をまず期した点にあった。 ・明治九年三月に諭吉のしたためた「慶応義塾改革の議案」は、慶応義塾の教育の本旨は人の上に立って人を始める道を学ぶのではなく、また人の下に立って人に治められる道を学ぶものでもないというのである。 健全な市民育成 ・つまり、一個独立の健全な市民の誕生を諭吉はつねに強く期待していたわけで、そのような市民の確立があってこそ真の文明国が形成されるものと、諭吉は信じていたのである。 ・つとに身分制度を否定し、維新とともにいちはやく自ら武士の身分を捨て去った諭吉のことであるから、諭吉の心にはそういう意味での社会の中心となるべき、毅然たる市民の存在が望まれたに違いない。 ・附和雷同は諭吉の断じてがえんじないところであった。必ず自分自身の思考のうえに立って是は是、非は非とし、それもいつでも目前の事象にのみとらわれることなく、ものの本質をよく見きわめて着実に歩を進めるという態度を諭吉は堅持したのである。 「独立自尊」の人 ・諭吉の念願にはそういう市民の育成がつねにあったわけで、そこに「独立自尊」の人が期待されたのであった。 独立の手本 ・諭吉が明治新政府の樹立とともにしばしば召命を受けながらついに出仕しなかった理由につき諭吉は自伝に四つをあげて、そのころの役人たちに鋭い批判の目を向け、 一つにはからいばりの群に入るべからず、 二つには身の不品行は人種を異にするがごとしとし、 三つには忠心義士の浮薄をいとうといい、 第四として結局は独立の手本を示そうとしたのだ、 といっている。 ―― 完 ―― |