
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年10月03日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |
40 |
20.10 |
明治天皇 苦悩する「理想的君主」 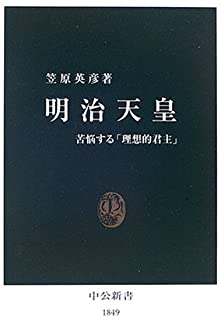 |
笠原英彦 |
中公新書 |
◎ |
はじめに ・明治天皇は究極の平和主義者で戦争を嫌ったが、臣下の立場を思いやり、政府の方針に真っ向から反対することはなかった。 ・自らの確固たる意思と統帥権の総攬者の立場をともに尊重していた。 ・明治天皇はいわば、つくられた君主である。むろん天皇個人の意思は存在したが、自ら統帥権の総攬者として時の政府が求める上奏案を裁可した。避けて通れぬ戦争を大元帥として遂行しつつも、戦場の兵士を思って一人悩んだといわれている。 ・天皇は常に自己の意志と政府の意向との乖離に耐え忍ばねばならなかった。明治天皇はそうした立場を積極的に受け入れるだけの強い精神力を身につけていたのである。 第一章 幕末の政局と睦仁の降誕 ペリー来航の衝撃と孝明天皇の治世 ・欧米列強の進出は東アジア諸国にとって大きな脅威であった。アヘン戦争はそのことをまざまざとみせつけた。 ・外圧に伴う国難に直面しても、江戸幕府には妥当な対応策がない。幕府の権威の失墜は、相対的に朝廷の政治的地位を押し上げた。それまで政治の局外にあった朝廷がにわかに政治の表舞台に登場することになる。 第二章 激動の中の即位と明治維新 幕末の動乱と朝廷 ・対外関係でもこの時期は緊張感が高まっている。ロシアが接触を求め、対馬の地政学的重みを指摘し、イギリスを仮想敵国として現地の権益を保全するよう迫ってきた。 ・しかしこの頃幕府はイギリスと親密な関係にあり、言葉巧みに接近してくるロシアをむしろ排除しようとした。 ・なんとこの問題に朝廷が関与し、長州藩から情報を収集した朝廷は対馬藩に対して海防策を強化するよう政治指導を加えた。 第三章 天皇権威確立の努力と挫折 親裁体制の樹立 ・維新政府は、天皇に政治的宗教的権威を求めたにちがいない。いったん獲得した権力を保持するためには精神的権威が求められる。 ・西欧と異なり、わが国にはキリスト教のような宗教権威がない。だから政権に正統性を付与してくれる天皇の存在は大きいのである。 ・明治国家は現人神たる天皇を精神的権威の拠り所とした。 ・古代以来、公家政権も武家政権もこの統治システムを踏襲してきたが、維新政権はそれがさらに直接的である。 ・つまり古代政権と同様に、明治政権期に入り国家体制と天皇制が結合したのである。 ・諸外国は懸案の通商問題を早期に解決したいだけである。維新政権が天皇の権威を借りて正当化され、一日も早く安定することのみを望んでいた。 ・列強諸国はミカドの政権に期待を寄せた。天皇親裁体制の樹立にとって、外圧は追い風だったのである。 留守政府と地方巡幸 ・明治年間には九十七回の行幸が挙行されている。これは即日還幸を入れての話であるから、いわゆる地方巡幸は六十回ということになる。 ・行列が簡素であっただけでなく、奉迎する側の負担軽減措置がとられている。 ・明治五年五月に陸軍省から全国要地巡幸の建議が提出されている。 ・注目されるのは、行幸の目的を「聖明の四海に君臨するや、 明治六年の政変と天皇権威の失墜 ・明治六年(一八七三)、朝鮮の態度を無礼とみた西郷らはにわかに征韓論を主張した。 ・とはいえ、西郷は最初から征韓を主張したわけではない。まずは全権使節を派遣してわが国の真意を伝え、朝鮮を説得する姿勢をとる。 ・しかし朝鮮があくまで日本を侮蔑する態度に出るなら、そのときは朝鮮征討もやむなしとの意見である。 第四章 維新の宰相、大久保の政治指導 天皇の厄年、明治六年 ・政府は天皇の権威を駆使して、時間的空間的支配に乗り出した。 ・まず一世一元制(天皇一代につき一元号)の実施により時間的支配が具体化された。 ・明治と改元されたのは慶応四年(一八六八)九月のことであり、これ以降一世一元の原則が踏襲されることになる。 ・江戸時代には事実上、改元には幕府の同意が必要であった。実際には幕府側の政治的配慮が優先され、天変地異により動揺する民心の収攬のため頻繁に改元が行われたのである。 ・一世一元制への切り替えによって、天皇と元号の結びつきは断然深まりをみせた。 士族反乱と天皇の政治的成長 ・絶対君主を戴く天皇親政を志向する岩倉と、あくまで公議政治を追求する木戸が折り合えないのは、ある意味で当然かもしれない。 ・維新政府は天皇親政と公議政治を二枚看板にしていたが、両者は本来相矛盾する。つまり、維新の二つの政治理念は二律背反的であった。独裁政治と民主政治の共存に等しい。 ・この頃政府を悩ませていたのは各地で湧き上がる士族の反乱である。政府の開明政策は士族らを追い詰め、暴発させた。 ・熊本神風連の乱しかり、福岡秋月の乱しかり、山口萩の乱(いずれも明治九年十月)しかりである。 ・しかし、宰相大久保は少しもたじろがない。士族の反乱はことごとく制圧された。大久保はそれにおかまいなく殖産興業政策を推進する。 第六章 立憲制の確立と皇室制度の形成 教育論争の意味 ・明治天皇は、教育には殊の外、心血を注いだのである。 内閣制度の成立と皇室典範の起草 ・皇室典範の起草は明治憲法と別立てで作業が進められた。 ・明治十八年(一八八五)、宮内省の制度取調局では「皇室制規」が起草された。内容は驚くほど柔軟であり、「女帝」のみならず、母方のみに天皇の血を引く「女系天皇」までもが容認されている。 ・「皇室制規」は「女系」の皇位継承を容認し、嫡系皇族を優先したところに特徴がある。 ・これに対し、井上毅は直ちに「謹具意見」を提出して真っ向から反対した。 ・井上は女帝制の問題を重視し、島田三郎、 ・島田らは女帝容認への反論を二つ挙げ、ものの見事に論駁してみせた。 ・まず、わが国には古来、女帝を立てる慣習があるとする反論に対して、即位事情の今日の状態との違いを挙げ反論する。 ・ついで男女平等という時代の要請に対しては、女帝に一生独身を貫かせることが条理に反することや皇婿(女帝の配偶者)がわが国の夫婦観念になじみにくいことを挙げて反論するといった具合である。 ・井上は、わが国にかつて在位した過去の女帝は欧州の女王と異なり「摂位(仮に位につき政治を行うこと)」であり、また皇婿が政治に干渉する恐れがあると意見書で主張した。 ・次に提出される「帝室典則」からはすっかり女帝即位の可能性は消えた。これは当時の実力者伊藤が井上の意見を採用し、修正を加えたからである。 ・皇室典範については憲法とは異なり、臣民に対して公式には公布せず、制定のことを賢所、皇霊殿、神殿に親告することになった。 ・皇室典範は英訳されたが、そもそも皇室典範の制定自体が、西欧に向けた文明化のアピールであった。 第七章 憲法の制定と立憲政治の開始 憲法の起草と発布 ・近代日本の立憲制の立役者は井上毅であろう。その地道な功績は大いに讃えられねばならない。 ・わが国近代は井上毅という、またとない逸材に恵まれたのである。 教育勅語の起草 ・わが国は憲法の制定や帝国議会の開設によって、確かに外面的には政治的近代化を果たしたが、国民的統一に必要な道徳的基準をいまだ持ち合わせていなかった。 ・それは江戸時代までと異なり、儒教道徳や他の宗教ですむものではない。 ・国民の心を皇室に帰向させることが求められていた。 ・井上毅は、世情の変化や上流社会の習弊により道徳の衰退が引き起こされていることを憂慮し、政治家が率先して矯正にあたることを希望しつつ、道徳的な最終手段として天皇の勅語を位置づけようとしたのである。 外交上の暗雲と司法権の独立 ・明治二十四年(一八九一)、外交上不幸な事件が引き起こされた。いわゆる大津事件がそれである。 ・ロシア皇太子ニコライ(のち即位してニコライ二世)が滋賀から京都への帰還途中、沿道で警備にあたっていた津田三蔵巡査がやおら剣を抜き人力車に乗るニコライに斬りつけたのである。 ・時代的背景として、当時のわが国に「恐露思想」が充満していたことを看過するわけにはいかない。 ・ロシアは対韓侵略を視野に入れており、いずれその脅威はわが国にも及んでくるとみられていた。 ・ニコライの訪日は、将来を見越した軍事的偵察が目的であるとの風評がもっぱらであった。こうした空気のうちに事件は発生したのである。 条約改正への道のり ・ロシアとフランスの親密な関係(一八九四年一月、露仏同盟成立)の進展はイギリスをいたく刺激した。おかげでイギリスは一段と親日に傾いた。 ・内地雑居は実にデリケートな問題である。諸外国の側にも言い分がある。どこの国でも日本人は居住が許され、自由に旅行しているではないかと。 ・日本は正直のところ、内地雑居に怯えていた。日本人の側が外国人を極度に恐れ、加害者となる危険があった。 ・諸外国の立場に立てば、治外法権はいわばそうした暴力に対する有力な抑止力である。 ・日本国内でも条約改正の賛否は明確に分かれていた。政府内部も分裂している。 日清戦争の勝利 ・明治十年代を通じて、女帝容認論も盛んに議論されたが、男系主義の伝統が守られたのである。たとえ庶子の皇位継承権が認められたと言っても、皇子の成長ぶりをみると、絶えず皇統断絶の危機を想定せずにはいられなかった。 ・だが側室制度という安全装置があったためか、皇位継承資格は男子に限定された。 ・この時代、何よりも天皇が大元帥であったことが大きい。女性が大元帥を務める事態は想定しづらかったのである。 ・一八九四年(明治二十七年)五月上旬、甲午農民戦争(東学党の乱)が起こり、朝鮮政府は清国に対し軍隊の出兵を要請した。日本公使館からの打電を受けた日本政府は朝鮮派兵を決定する。 ・ところが、農民反乱は日本軍が到着する以前に収拾された。 ・日本にとってこうした事態は不都合であった。何より陸奥外相や参謀本部が出兵にこだわったからである。日本側は出兵の口実を執拗に求め、そこで朝鮮の内政改革が争点になった。 ・閣議決定は駐在日本公使館からの来電に基づき、内乱が漢城(現在のソウル)および日本人居留地に侵入する脅威とそれに対応した居留民保護のための出兵要請を受けて行われた。 ・閣議では「即時先行出兵方針」が決定されるが、それは間もなく「対抗出兵方針」へと修正された。 ・清国への朝鮮内政改革の提議に、清国はこれを拒絶した。日本の軍事方針からいって、予想された通りの展開である。 ・そこで日本は、清国が日本の提案を吞まない限り撤退しない意向を表明した。 ・ところが厄介なことに、列強が介入してきたのである。 ・開戦の阻止をめざすロシアが、それにつづいてイギリスが干渉の姿勢を示した。日本はいやでも開戦を急がねばならなくなった。 ・七月に入ると、恐れていたイギリスの介入が本格化し、北京で日清会談が開かれた。この会議は清国側が同時撤退を主張したため決裂した。 ・日本は開戦に向けて一段と外交攻勢を強める。 ・開戦の口実を見つけるよう、日本は清国に対し、朝鮮の内政改革をめぐり無理な要求を突きつけた。 ・そしてイギリスの調停工作を撥ねつける。ときあたかも、日英間の条約改正交渉は最終段階を迎えようとしていた。それでも日本がイギリスの疑念をかいくぐることができたのは、イギリスが極東におけるロシアの進出を日本と同盟して防ぐ意図が働いていたからである。 ・七月二十三日、日本軍は首都漢城に進軍する。日本兵は王城内に突入し、朝鮮兵を駆逐した。 ・このため、朝鮮国王の高宗は実父である大院君に政治の主導権を渡すことになった。 ・大院君は、自らが国政改革を進める意向を告げた。いわば全権を掌握した大院君があらゆる措置について事前に大鳥と協議することを約したのである。 ・七月二十五日、日清間で最初の衝突が起こった。 ・朝鮮のみならず清国も、日本が開戦に及ぶとは予期していなかった。 ・海上でも日本の艦隊は清国艦隊を撃退して優勢を誇った。 ・陸戦の方は七月二十九日に開始された。陸戦でも日本は輝かしい戦果をあげた。 ・日本軍は快進撃を繰り返し、九月半ばには釜山、元山、仁川など朝鮮半島の心臓部を占拠した。 ・政府首脳は遼東割譲をめざし旅順攻略を開始する。そしてこの年十一月には旅順が陥落した。 ・伊藤は、意見書を提出して速戦即決、軍事・外交の一致を説いた。実にバランスがとれ、状況判断が的確である。 ・二十八年(一八九五)、講和交渉が下関で開始された。伊藤首相は列強の介入を考慮して交渉を急ぎ、遼東半島、台湾、澎湖列島の割譲、賠償金二億両(現在の価値で約三億円)といった条件で四月十七日には調印した。 ・明治天皇は大元帥として見事に戦争指揮した。日清戦争は近代日本にとって政治的、経済的に重大な意味をもつ戦争である。 第八章 議会政治の進展と日露戦争 日露戦争への道のり ・日本は、明治三十五年(一九〇二)までに極東問題については政策判断を下していた。日本には本来、二つの選択肢があったはずである。 ・第一には、ロシアと結び、満洲(中国東北部)をロシアに委ねる代わりに韓国に対する日本の優越を認めさせることである。 ・第二は、欧米列強と提携してロシアに対することである。 ・結果的に、日本は極東におけるロシアの進出を警戒していたイギリスと提携する政策を選択した。 ・三十五年初頭にはロンドンにおいて日英同盟を締結している。 ・日英同盟の効果は大きかった。明治三十五年四月、ロシアが満州から撤兵することを内容とした露清条約を締結したのである。 ・ロシアは同年十月以降、三段階で撤退を完了する旨を鮮明にしていた。しかしロシアは条約を真摯に履行しようとしなかった。ロシア内部で強硬派が台頭し、満洲北部の占領継続の方針が確定したからである。 ・翌三十六年(一九〇三)四月、対露方針を決定した。陸軍、海軍もロシアの横暴を抑止することで一致した。 ・七月下旬には、満韓問題をめぐりロシア政府との交渉に入ることが確認された。 ・八月三日、協商案をロシア政府に手渡す。まもなくロシア皇帝の指示の下、ロシア外交当局も交渉に応じる体制を整えた。 ・日本国内では、ロシアが第二次撤兵を履行しないことから、主戦論を含む強硬意見が表明されていた。 ・日本は協商案の中で、ロシアの満州における権益を明確にせず、日本の韓国における権益のみを重視した感がある。 ・対露不信感は予想以上に大きく、ロシアが朝鮮半島への進出を企図しており、日本への脅威はただならぬものであるとの認識もあったようである。 ・ロシア側でも皇帝ニコライ二世の猜疑心から、ロシアの極東政策は一貫性に乏しかった。 ・日本側の第一次協商案は、政府の弱腰が裏目に出て協調性に欠けていた。 ・日本の強硬な態度が結果的にロシアの強気の交渉姿勢を誘発し、さらに日本側の対露不信感を強めるという悪循環が生じていたとみられる。 ・桂・小村の交渉を見詰めていた山県はしだいに対露開戦をもやむなしとの考えに傾いていった。 ・桂内閣の真意は満韓交換論にあった。戦争はできれば回避する方針である。 ・交渉は事実上、明治三十六年(一九〇三)十月に開始されたが、予想以上に難航し、翌三十七年二月に至り決裂した。まもなく政府はロシアに対して宣戦を布告した。 日露戦争と明治天皇 ・宥和論者である伊藤もすでに明治三十六年(一九〇三)末の段階で、戦争回避は困難であるとの認識を山県に伝えている。 ・満州問題も結局外交努力では解決不可能であり、朝鮮問題でもロシアが修正要求を吞まない以上、開戦は不可避であった。 ・天皇は必ずしも開戦には賛成ではなかった。政府は言を左右にしてやまないロシアに痺れをきらしている。 ・伊藤の意見を聞き決意した天皇は、明治三十七年(一九〇四)二月四日、「事万一蹉跌を生ぜば、朕何を以てか祖宗に謝し、臣民に対するを得んと、忽ち涙潜々として下る」有様である。 ・開戦の決断がなされると、政府は英米両国の理解を求めるべく動き出した。 ・日本の戦略は、戦争を一年以内に終結させ、英米に対してはロシアを駆逐して満州を開放する方針であった。 ・戦争勃発の原因を、日本の名誉が傷つけられたためとするのは必ずしも妥当ではない。 ・日本は主体的かつ計画的に開戦を求めたのである。 ・日本はおよそ三倍の戦力のロシア軍を向こうに回して戦うことになり、戦線は膠着した。 ・日露戦争はたんに二国間の紛争ではない。日本の背後には英米があり、ロシアの背後には独仏があった。 ・独仏がロシアに加担したのは、極東の権益のみならず日本が異民族、異教徒の国であるという意識が作用していたからであろう。 ・フランスは日本の優位を想定し、バルチック艦隊の派遣に関してイギリスに対し注意を喚起した。おかげで、ロシアの大艦隊はアフリカ西岸から喜望峰を回る航路を選ぶことになった。 第九章 天皇の晩年と明治の終焉 韓国併合と伊藤の死 ・伊藤は統監退任後、ロシア蔵相との協議のため大連を経由してハルビンに向かった。 ・明治四十二年十月二十六日、ロシア一行の待ち受けるハルビン駅頭で伊藤は遭難する。ロシア兵の背後から躍り出た案重根という名の韓国人青年に撃たれ、三十分後に伊藤は絶命した。 ・暗殺者はその場でロシア守備兵に拘束された。 ・安重根は大変な愛国主義者で、韓国が植民地となることを恐れるあまり外国語学習を放擲している。彼の自伝等を読む限り、西欧諸国によるアジア支配を嫌悪していたようである。 ・安重根が学びかけた外国語はフランス語であったが、祖国を支配しようとしたのは「白禍」ではなく日本であった。期待は伊藤によって無残に打ち砕かれた。 ・安重根は清国、韓国、日本が協力して西洋列強に対抗し、東アジアの平和を守ることを念願していたのである。 ・安重根は東洋の平和をひたすら希求し、日韓関係の改善を強く望んでいた。獄中記などを読む限り、大変な理想主義者である。 ・伊藤の韓国における悪政を、日本の天皇がよく理解し正してくれることを希望していたようである。 ・彼は愛国者であると同時に、大変な知日家であった。しかし日本についての理解には正確さを欠く部分がかなりあることも確かてある。 ・安重根が伊藤を標的とした理由は、第二次伊藤内閣下の明治二十八年(一八九五)十月における閔妃(韓国皇妃)殺害に始まり、韓国にとって不平等な条約に締結へと続く。 大逆事件の衝撃 ・明治四十三年(一九一〇)五月下旬、陸軍大臣の寺内政毅が曾禰荒助後任の韓国統監に任命された。 ・すでに日本は韓国を併合する方針を固めていたが、かの伊藤暗殺により事態はいっそう加速化していった。韓国側にも韓国併合を求める動きが出てくる。 ・寺内統監は韓国情勢を見極めようとしていた。強引に併合に持ち込むのではなく、韓国側に併合やむなしとの空気が醸成されるのを辛抱強く待つ構えである。 ・韓国では、日本により韓国の皇室や内閣が支配されることが懸念された。寺内は韓国側に日本の天皇や政府が寛大であることを伝えた。とはいえ、韓国の治安には目を光らせ、多数の憲兵を派遣している。 ・韓国政府は親日的というより日本に対して迎合的であった。朴斉純内閣も李完用内閣も伊藤らが進める改革に協力的だったのである。 ・李に至っては、日本との条約締結を渋る韓国皇帝の廃位すら日本側に提案しているほどである。 ・たとえ反日運動が燃え盛ろうと、政府間では併合の道が選択されている。ついに韓国皇帝は自ら統治権を日本の天皇に譲ろうと覚悟した。これにより政府間交渉が進み、韓国併合がなる。 ―― 完 ―― |