
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年01月10日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |
42 |
20.10 |
官僚を国民のために働かせる方法 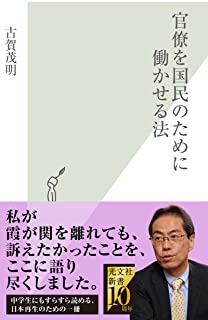 |
古賀茂明 |
光文社新書 |
◎ |
はじめに ・官僚たちの多くは「国民のために働く」という本分を忘れて、悲しいことに、自らの生活保障のために、省益の拡大ばかりに心を奪われるようになってしまっています。 1章 なぜ「国家公務員制度改革」が進まないのか こんな国に誰がした? 霞が関の改革なくして危機を乗り切ることはできない ・日本を凋落へと導いたのは政府、もっと言えば官僚です。もちろん、政治家にも責任はありますが、国が反映し、国民が幸せになるための政策を考えて政治家に進言し、実行するのは官僚たちなのです。 ・逆に言えば、日本のいまの危機的状況は、いかに官僚たちがちゃんと働いてこなかったか、国民や民間企業のために汗を流してこなかったかの証明でもあるわけです。 ・国家公務員制度改革と聞くと、誰もが「やれ やれ!」と応援します。ただ、その理由は大方、「官僚の連中がみんな、いい暮らしをしているのはけしからん! 税金のムダだ!」 というもの。 ・時の政権ですら、その辺の国民感情を利用して、人気取りのためだけに官僚バッシングに走っているきらいがあります。 ・大事なのは、「改革がどうして日本の危機を救うのか」、そこをよく理解すること。 ・日本には長いこと、「お上にまかせておけば大丈夫」というような風潮があって、官僚たちはその "根拠なき信頼" のうえに胡坐をかいてきました。 ・現状、無策の霞が関を、「日本を危機から脱出させて、再生に向けて大転換させていくための政策を出せる」集団に変革しなければなりません。その根っことなるものが「国家公務員制度改革」なのです。 改革派官僚は干される、飛ばされる 霞が関の異端児と呼ばれて ・多くの場合、経産省の省益にとって極めて重要な政策に、強く反対意見を述べた若手官僚たちが、退職・左遷の憂き目に遭ったように、省益に反する改革を行おうとする者は、霞が関的には「許しがたい異端」と見なされるのです。 人事に改革のメスを 人事権者はいったい何をしているのか ・典型的なのは、「消えた年金問題」でしょう。なぜ、こういうことが起こるのか。 ・勇気をもって現状の不備を指摘し、「ちゃんと現状を把握しなくては」「間違いが起こらないようなシステムにしなくては」と動き出す人がいなかった。いや、いたかもしれないけれど、上から暗に「見て見ぬふりをしろよ」というサインが出た、とも考えられます。 ・官僚にはミスを認める。潔さも、人任せにしない責任感も、問題を解決する能力も、すべてが欠けていた。何より、年金を頼みにしている国民のことを考える優しさがなかった。 経産省三幹部 "更迭人事" の茶番 ・官僚はみんな、大臣ではなく次官のほうを向いて仕事をしている。 ・「どうせすぐにいなくなる大臣の言うことを聞いたってしょうがない。次官に嫌われたら出世の道が閉ざされるから、次官にこそついていかなくちゃ」と考える。それが官僚の習性なのです。 第3章 "内向き志向" が日本を滅ぼす どうにかならないのか、天下り 問題は役所のシステムと一体化していること ・天下りポストを確保・維持するために、霞が関は国民の税金を使って、ムダな仕事を増やし、予算を歪ませ膨らませ、癒着を生み出しているのです。 4章 政治家はこうして官僚にからめとられていく 官僚は政治家より偉いのか 行政は本来、「政治主導」が当たり前 ・民主党は「政治主導」「脱官僚」を掲げ、多くの国民が「そうだ、そうだ」と支持。歴史的な政権交代が起きました。 ・でも、日本だけなんですよ。いちいち「政治家が行政を主導します」なんてことを主張しなくていけないのは。 ・政治主導自体は政策でも何でもありません。やって当然のことです。重要なのは、政治主導によって、何をするか、ということなのです。 ・結果的に民主党は政治主導に失敗しました。 ・民主党の体たらくぶりを目の当たりにした国民の間に、何となく「官僚主導のほうがいいんじゃないの?」という空気が蔓延していくことです。 ・そのことがまた、「結局、自民党時代のほうがよかったよね」という揺り戻しを起こす可能性があります。 ・そうなっても、自民党がある程度変わって、政権を取り戻すのならいいのですが、あまり期待はできません。 ・そもそも、官僚をのさばらせてしまったのは、自民党の議員たちなのですから、その体質を改善するのは容易なことではないのです。 ・それでも「やっぱり自民党かなぁ。官僚とうまくやっていけるもんね」となっていくと、また「官僚のほうがいいんじゃないの?」というのがテーマになってくるわけです。 ・行政は、「主」たる政治家が「従」たる官僚を使って、国の利益と国民の幸せのために政策を策定・実行していくプロセスなのです。 ・政治主導の本来あるべき姿とは、 「政治家は日ごろから、国民生活をより向上させるための重要課題や、国をより発展させるための中長期的課題をしっかり認識しながら、広い視野から政策の方向性を決定する。 一方で官僚は、その政策を具体化するよう、資料や情報を厚め、研究や議論を重ねる。そうして集積した専門知識をベースに、状況に適した具体的な政策の選択肢を複数政治家に提案する。 政治家はそれらの情報・知識と提案をもとに、官僚とは異なる考えを持つほかの専門家や国民の声を聞きながら、総合的に判断して結論を出す」 ・この論理にのっとれば、仮にその結論が官僚の提案とは異なるものであっても、政治家はしっかりと方向性を示して、官僚に実行させなければいけません。 ・そして、その政策に対して、政治家が全責任を持つ。それが、政治主導であり、政治家のリーダーシップなのです。 官僚は政治家をバカにしている? ・残念ながら、現在の行政は政治主導とはほど遠いものです。すでに多くの人たちが、「官僚のほうが政治家より力を持っている」ことに気づいています。 ・官僚というのは、「自分たちのほうが政治家より上だ」という意識を非常に強く持っているものなのです。 ・官僚たちのこの考えかたは、根本のところで間違っています。 ・たしかに、知識は官僚のほうが豊富なことも多いでしょう。「資料や情報を集めて、研究を重ねて専門知識を集積していく」ことこそが、官僚の仕事だからです。 ・一方、政治家の仕事は知識を蓄積することではなく、官僚や専門家、有識者からの情報・知識・考え方を踏まえて、大局的に政策を決めることです。 ・極言すれば、知識などなくとも、状況判断力とリーダーシップが発揮されればいい。そこに政治家の優劣を決する要素があるのです。 ・政治主導を実現するためには、政治家たちが官僚たちの誤った価値観を正し、思い上がりを制することも、ポイントの一つと言えそうです。 事業仕分けは政治家がやることではない ・そもそも、事業仕分けなんて細かい作業は、政治家のやるべき仕事ではない。 ・よほどのことがない限り、何の意味もない事業というのはありません。 ・たとえば、同じような事業を二つ、三つ並べて、「国民から見れば、どれも同じですよね。どれに予算をつけましょうか」とやるのならまだしも、事業を一つずつ、ムダかムダではないかをチェックするなど、非常に不毛なことなのです。 ・政治家としてやるべきは、ムダを探すことではなく、優先順位をはっきりさせることです。 官僚主導へ逆戻りした民主党政権 「脱官僚」は絵に描いた餅 ・民主党は「政治主導」の本当の意味を理解していなかったのかもしれません。 ・菅氏などは野党時代から「官僚は大バカだ」などと発言し、官僚を政治家の敵もしくはライバルと位置づけるきらいがありました。 ・つまり、政治家が自ら官僚の土俵に降りて、そこで戦おうとしてしまったわけです。 ・官僚にしてみれば、自分の土俵で戦えるのですから、こんなに有利なことはないでしょう。 ・で、土俵に上がったのはいいけれど、行き当たりばったりの政策しか持たない民主党は、立ち合う相手の官僚がどこにいるのか、どんなファイティングポーズをとっているのかもわからない。勝手知らない他人の土俵、ですからね。 ・結局、見当違いのところにパンチを繰り出しては空振りすることの繰り返し。官僚はひょいひょい身をかわしながら、ほどなく民主党が勝負をあきらめて、自分たちに頼ってくるのを待てばよかった、という感じでしょうか。 ・堺屋太一氏が、菅政権時代の政官家関係について、こんなふうにたとえていました。 「本来、官僚はタクシーの運転手で、行き先を決めるのは政治家のはずです。ところが、菅さんはいきなり『オレが運転する』と言いだした。で、技量がないから、大事故を起こした。こりゃいかんと官僚にハンドルを握らせたら、これが定期バスの運転手で、乗客が何を言おうと決められた路線、つまり『官僚権限の強化』という路線を走っている。これが政官の実際の関係です」 ・早々にハンドルを官僚に渡したのは、菅氏だけではありません。大臣以下、民主党の議員たちはことごとくそうて゜した。 ・民主党の誤り 「日本を変えよう」という意思が、実は「自民党を否定する」ことでしかなかったのです。 だから、「政治主導」「脱官僚」そのものが目的化し、そのために「どんな哲学・理論に基づいて、何をどう変えていくか」という最も大事なことが抜け落ちてしまったのではないでしょうか。 ・民主党はウソつきだったのではなく、単に勉強不足だったと結論づけていいと思います。 ・政策を実行するには、たしかな哲学や理論に基づく仮説が必要です。民主党議員にはこれがなく、その場その場で感覚的に決めているように見えました。 ―― 完 ―― |