
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年03月14日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |
45 |
20.11 |
難治がんと闘う 大阪府立成人病センターの五十年 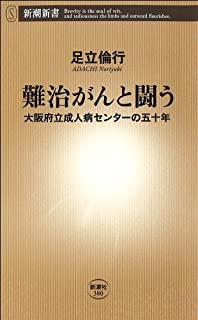 |
足立倫行 |
新潮新書 |
◎ |
第一章 がんと闘うために 津熊秀明医師に聞く がん登録とは何か? ・がんがどのステージ(進行度)で発見されたか、日本を含む世界の地域がん登録の分類。 ①限局(がんが原発臓器に限局している)、 ②領域(所属リンパ節に転移がある、または隣接する組織臓器に浸潤が及んでいる)、 ③遠隔(遠隔転移がある)、 の三つです。 医療の格差 ・住基ネットは、個人情報の保護や国民総背番号制への懸念から、その利用について非常に強い縛りがあるわけですが、地域がん登録といったきわめて公益性の高い事業にこそ使ってしかるべきだ。 ・現在の社会は、自治会名簿も作らない、という方向に進んでいます。 ・行き過ぎです。大体、機密性ということで言えば、厳格な規制の下で担当者のみが住基ネットのファイルと突き合わせを行う方が、現状の、府職員が市町村で住民基本台帳を参照するよりも、よっぽど機密性は高いのです。今の形式の方が逆に人目に触れやすいんです。 第二章 胃がんに挑む 飯石浩康医師に聞く 「外科いらずのがん治療」を目指して ・今、内視鏡治療の対象は粘膜内がんで、粘膜下層がんはガイドラインでは適応外なんです。 ・でも、胃の例で言えば、粘膜下層がんと診断されてそのうち転移が実際にあるのは15%から20%。大腸であれば、10%から15%です。 ・つまり、残り8割以上の粘膜下層がんの人は病変部のみ切除すればそれでいいんです。手術などする必要はない。 ・ "しなくていい手術" なんて言うと、外科の先生に叱られてしまいますが、現にその8割の人は、胃を切り取られているわけです。 ・内視鏡による局所的な切除でははなくてね。灰色が全部黒と見なされてしまう。この現状を、ぜひとも変えたい。 ・そのためには、一つは、転移しない胃がんの特徴が組織検査でわかればいいわけです。 ・その時、 "このタイプのがんは転移することはない" と判明すれば、手術ではなく、そのまま経過観察に移行したらいい。 ・そういう検査技術が確立できたら、現状は変更できます。 ・もう一つは、腹腔鏡とのハイブリッドですね。 第四章 肺がんとの闘い 兒玉憲医師に聞く ・2008年のがん統計によると、年間34万2963人の日本のがん志望者のうち6万6849人、約19.5%が肺がんによる死亡である。 年6万人が死亡する肺がん ・どうして肺がんは難治がんなのでしょうか? ・「それは肺の、内臓としての解剖学的、生理学的特殊性によります。肺にできたがん細胞は、肺静脈に入って心臓に流れ、そこからパーッと全身にバラまかれてしまう。他の臓器のがんと違って局所にとどまりにくい。局所に抑えても、簡単に遠隔転移してしまうわけです。頭にも、肝臓にも、骨にも転移する。だから予後が悪いんです」 ・「肺がんは生物学的なな特性によって、小細胞がんと非小細胞がんに分かれます。大部分の患者さんは非小細胞がんでして、全体のほぼ85%を占めます。残りの15%の人が小細胞がん」 ・「小細胞がんは喫煙との関連が大きく、肺の太い気管支にがん細胞ができるんですが、増殖のスピードがとても速く、周辺のリンパ節はもとより、肺から離れた臓器や骨に転移しやすい。そのため発見時にはすでに転移していることの多い厄介ながんなんです」 第六章 女性とがん 上浦祥司医師に聞く ・子宮頸がん自体は減少傾向にあるにもかかわらず、20歳代、30歳代で発症する人が増え、この20年間で倍増する勢いにある。 ・子宮頸がんの主な原因が性的接触によるHPV(ヒトパピローマウィルス)感染とされるところから、女性の性体験の低年齢化や性的パートナーの複雑化など、時代による社会変化が指摘されている。 若い女性が罹るがん ・HPVは人間の皮膚などにイボや腫瘍をつくるウィルスで、それ自体ありふれたウィルスです。 ・通常、HPVは性交渉によって感染します。 ・普通は感染しても、免疫の力でウィルスが体外に排除されます。無症状のまま自然に消滅してしまう。しかし10人に1人ぐらいは感染状態が続き、そのうちごく一部の人で、10年以上たってから遺伝子の異常によりがんが引き起こされます。 第七章 乳がんを撲滅する 稲治英生医師に聞く どんな女性が乳がんに罹るか? ・なぜ乳がんに罹る人が増えたのでしょうか? 「一言で言うと、日本人女性のライフスタイルが欧米化した、ということでしょう。 一つは閉経後の肥満です。欧米の乳がんは60歳代がピークなんですが、日本の同年輩の女性も、昔はやせ細ったイメージがあったのに最近はふくよか。食生活が豊かになって、高蛋白・高脂肪の食事に変わってきました。ふくよかな初老の人は、見栄えはいいのですが、乳がんに関しては不利なんですよ。 それと、女性ホルモンの分泌期間が長くなったこと。戦前の女性は14歳頃が初潮で、数人の子どもを産み、40歳代でもう閉経でした。ところが戦後は栄養状態が改善し11歳頃に初潮が始まり、閉経も50歳代まで伸びてます。しかも女性の社会進出がさかんになり、非婚、晩婚、高齢出産が増えました。生理のある期間が何十年も続き、生涯に産む子どもの数はせいぜい1人か2人です。 乳がんの約7割はエストロゲンなどの女性ホルモンの影響を受けますから、非婚・少子化の現代は、乳がんが増える条件が揃っている時代なんです」 ・――子どもを産まないと乳がんになる率が高くなる? 「そうです。妊娠中は女性ホルモンがストップした状態です。昔のように生理期間が30年とした場合、その間、仮に10人子どもを産めば、乳腺がエストロゲンの影響を受けるのは20年。しかし、現代女性のように生理が40年間続き、子どもを産まなければエストロゲンの影響を受けるのは40年。女性ホルモンを2倍多く浴びることになります」 ・――肥満と非婚・少子化が主な原因とすれば、現代病、文明病の趣がありますね? 有効なホルモン療法 ・乳がんは女性ホルモンが悪さをするがんなんです。 治療の値段 ・乳がん検診について言えば、ただやみくもに "受けなさい" と連呼するよりも、 "将来乳がんに罹る確率の高い人は受けて下さい" と勧める方が合理的かも知れない。確率が0.1%の人は別に受けなくてもいいけど、10%であれば毎年でもマンモグラフィ検査を受けた方がいい。むしろ受けるべきです。 第八章 がんを切らずに治す 西山謹司医師に聞く がんに有効な放射線の原理 ・放射線ががん細胞をやっつける原理は 照射された放射線が細胞のDNAを損傷する。そのため細胞分裂ができなくなって細胞死に至ります。 ・人体の細胞には2種類があります。放射線の感受性が高い、つまり影響を受けやすい細胞と、感受性の低い、影響を受けにくい細胞です。 ・分裂をさかんにくり返しているがん細胞は、生殖細胞や造血系の幹細胞などとおなじく放射線によって影響を受けやすく、増殖能力を失って細胞死しやすい細胞です。 ・神経や筋肉の細胞は放射線の感受性が低く、許容度以上の放射線を受けると、増殖うんぬんよりも核や細胞膜など細胞そのものが破壊されます。 ・放射線によって細胞内のDNAが損傷された場合、正常な細胞なら直ちに細胞自体が傷を修復します。ところが、がん細胞は修復能力が著しく劣っており、DNAの傷を修復し切れずに死んでしまいます。放射線治療はこの現象を利用したものです。 ・どういうことかと言うと、低い線量の放射線を病巣部に照射します。線量はグレイという単位で表わし、通常は1回2グレイです。 ・すると、病巣部のがん細胞はDNAを損傷されてダメージを受けますが、周囲の組織の正常細胞は、たとえダメージを受けてもすぐ修復作業を開始する。翌日また照射すると、がん細胞の方はダメージが積み重なり、正常細胞の方は多くが回復していて、新たなダメージにすぎない。 ・こうして、週5回の照射を6週間なり7週間なり続けると、がん細胞は60グレイ、70グレイという大線量の放射線をうけて死滅し、正常細胞はタイムラグがあるので、ダメージが最小限に抑えられて生き残る。このような考え方なのです。 ・――放射線の照射は、感受性の高い低いにかかわらず、がん細胞でも正常細胞でも、どちらにも深刻なダメージを与えるわけですね? 程度の差はあっても。 ・全身に5グレイの放射線をかけると、2ヵ月後に50%の人が死亡します。10グレイであれば3日半で100%人が死にます。100グレイなら即死です。 ・もっとも、全身の場合は、5グレイなら血液を作り出す骨髄を破壊するから死に至るわけですし、10グレイなら、食物の栄耀を吸収する小腸の細胞が死滅することによって死に至ります。 ・生体の維持に不可欠な、非常に放射線の感受性の高い細胞がまず破壊されるから人体が死に至るのであって、その線量で全体の細胞が死んでしまうわけではありません。 ・放射線治療では、いかに正常組織への影響を小さくして病巣部への照射を効果的なものにするか、というのがポイントになります。その前提の一つが、腫瘍が小さいこと。 ・病巣のがんそのものが小さければ、巻き込んで影響を受ける周辺の正常組織も少なくてすむ。 ・照射される正常組織の体積が小さければ、ものすごい線量の放射線があたっても障害は出ない。放射線治療は、がんの体積と放射線の量のパラメーター(媒介変数)なんです。 第九章 がん細胞を究める 加藤菊也医師に聞く マンマプリントを駆使する ・抗がん剤は本来が細胞毒性です。がん細胞を破壊すると同時に、正常細胞にも傷害を与えてしまう。貧血、脱毛、下痢、嘔吐などの強い副作用を伴います。抗がん剤の効果には非常に個人差がありますから、有効でない人はできることなら使わない方がいい。転移する可能性が少ない、おとなしいがんの人も、きつい抗がん剤は極力省いた方がいい。 ゲノムと遺伝子情報の解析 ・個人の全ゲノム解析が一般化すれば、確実に起こるのは、遺伝病の遺伝子の保有が明らかになってしまう問題です。 ・染色体は対になっていて、優性遺伝の病気ならそのうちの1個の異常で発現しますが、劣性遺伝なら2個とも異常でないと病気にならない。で、世の中の遺伝病の多くは劣性遺伝なんですよね。発現してない遺伝病の遺伝子を持っていることが、全ゲノム解析でわかってしまう。これをどうするか、です。 ・――両親の全ゲノムがわかってしまうと、子どもに遺伝病が出る確率が事前にわかってしまうわけですね。 ・そうです。当然、産むかどうか迷うことになります。両親も、社会も、非常に大きな倫理的問題になるでしょうね。 ・――個人の全ゲノムの情報というのは、究極の個人情報なんですね。 ―― 完 ―― |