
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年02月28日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |
47 |
20.11 |
医療政策を問いなおす ―国民皆保険の将来 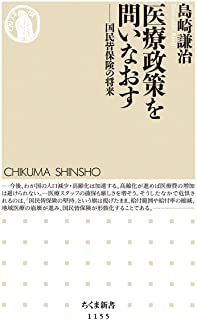 |
島崎謙治 |
ちくま新書 |
◎ |
第2章 歴史から得られる教訓と示唆 1 社会保険方式の採用と二本建てによる国民皆保険 † 日本が社会保険方式を採った理由 ・1つは、自ら保険料を納めることにより将来のリスクに備えるという自立・自助の重要性である。日本は自由経済を標榜する国である。自由経済の基本は自立・自助であり、医療制度の制度設計は、その基底を成す社会経済の基本原則とできる限り調和させておくことが望ましい。 ・2つ目は、社会保険方式では給付と負担が結びついているため財政の規律性が保たれることである。 ・3つ目は、社会保険方式では保険料の拠出の見返りとして給付が行われるため、税方式に比べ権利性が相対的に強いことである。 † 被用者保険と国民皆保険の2本建ての理由 ・民間医療保険と異なり公的医療保険では、健康な人から病気がちの人へ所得移転が行われる。 ・また、保険料賦課に当たって応能負担を導入すれば、高所得者から低所得者にも所得移転が行われる。 ・このため、健康な者や高所得者の不満を顕在化させないようにするためには、保険者は共同体意識をもてる集団を単位に組成することが合理的である。 ・わが国は被用者保険と国民健康保険の二本建てにより国民皆保険を達成したが、被用者保険は「カイシャ」という共同体、国民健康保険は「ムラ」という強固な共同体を基盤に成立したものである。 2 老人医療費の無料化と高齢者医療制度 † 老人医療費の無料化とその評価 ・老人医療費無料化は日本の医療政策史上最大の失敗策であったと考えている。コスト意識を失わせ過剰受診や社会的入院の増大をはじめ数々の弊害を招いたからである。 第4章 人口構造の変容が医療制度に及ぼす影響 4 人口構造の変容と政治 ・医療・介護との関係でいえば、世代間の利害対立が先鋭化することが懸念されるが、これを民主的なプロセスを通じ解決することは難しくなる。 ・なぜなら、高齢者の有権者比率が上昇するため、高齢者にとってマイナスとなる政策決定が行いにくくなるからである。 ・ちなみに、2010年の高齢者の有権者比率は28.0%であるが、2035年には38.8%、2060年には45.8%まで増大すると見込まれている。 ・「シルバー民主主義」が危惧されるゆえんであるが、逆にいえば、まだ比較的冷静に議論ができるのは今しかない。 第5章 医療政策の理念・課題・手法 1 医療政策の理念 † 自己決定権の尊重および個人の尊厳の確保 ・医療政策の理念は人間や社会のありかたに関わる。 ・近代市民社会ないしは自由主義社会の基本は自立・自助および自由である。 ・つまり、自分の生活はできるだけ他人の世話にならず自らを支えるという社会、個人の意思や選択が尊重される社会である。 † 医療観・医療モデルの転換 ・高齢者の疾患の多くは生活習慣病であるうえ老化が関わっているため、1人の高齢者が複数の疾患・症候を抱えるとともに完治しない場合が多い。 ・したがって、「病気を治す」という単一的な医療観や医療モデルの転換が必要になる。 ・高齢者は複数の病気を抱えるだけでなく、身体機能の低下や認知症の発現に伴い介護需要も高まる。臓器別ではない全人的・包括的な医療、尊厳ある看取りまで含めた「生活を支える」医療が大切になる。 ・そして、これは医療政策の守備範囲の拡大を迫ることになる。 ・比喩的にいえば、「生活を支える」といった途端、医療政策の「視界」は、医療の隣接領域である保健、介護、福祉はもとより、住まい、就労、さらには "まちづくり" まで一挙に拡大する。 ・それはなぜか。医療は病をもつ人にとって重要であるが、医療は生活の一部として存在し、生活は介護・福祉等の関連サービスや生活の基礎となる住まいや地域と切り離して存立しえないからである。 終章 結論と課題 † 結論 ・第1は、医療政策の制約条件である。 近未来の日本の人口構造は大きく変容し、未曽有の「超高齢・人口減少社会」が出現する。後期高齢者の急増は医療費を増加させるとともに、医療保険制度における世代間扶養の性格を一層強める。 医療制度の財政制約が厳しくなるだけでなく、生産年齢人口の激減に伴い医療の人的資源の制約も厳しさを増す。 ・第2は、医療提供体制の改革である。 高齢化に伴い医療費が増加することは避けられないが、医療の生産性の向上・効率化が求められる。 「医師不足」が指摘されるが、医師の総数は増加している。新規養成数を増やすのではなく、診療科別の配分や地域偏在の是正に努めるべきである。 ・第3は、医療保険制度の改革である。 社会保険方式は給付と負担を自律的に決定するなどの利点があり、今後とも社会保険方式を維持すべきである。 医療費の財源については、社会保険料は今後ともその中心となる。 公費については現状でもファイナンスできておらず、消費税率の引上げは避けて通れない。 世代間の医療給付と負担の不均衡を是正するため高齢者の負担の見直しを行う必要がある。 混合診療の解禁は適当ではなく保険外併用療養費制度の改善で対応すべきである。 医療保険制度の改革については、国民が必要とする医療は公的医療保険できちんとカバーした方が、医療の質や安全性を確保できるだけでなく医療費の総額も抑制できる。 ―― 完 ―― |