
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2020年04月08日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |
6 |
20.03 |
病気と自己実現 ―― 真の治療関係を求めて ―― 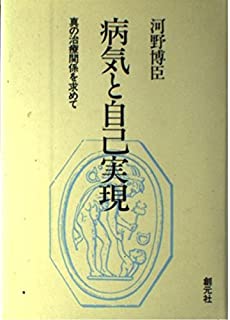 |
河野博臣 |
創元社 |
◎ |
第一部 患者の心・治療者の心 第一章 治療者とは何か 患者は最後まで希望を捨てない ・患者はどんなに手遅れであっても希望を捨てるものではない。 ・人間はその生命の火が消えるまで決して希望を捨てないのである。 ・患者が希望を捨てない以上、医師が希望を捨て、失っていいのであろうか。本当に治療者は臨床家としてもう一度考え、反省する必要があるのではなかろうか。 ・現代の医学があまりにも化学的になり、理論的になったため、ともすれば人間の生命が身体面だけと思いがちになり、身体的に駄目だと診断がつけば、その患者の心まで、駄目と診断してしまうようなことを当然とする傾向があるのではなかろうか。 ・手術・化学療法・放射線療法・免疫療法と、医師の持ち駒がすべてなくなってしまっても、医師には、心をもった治療者として病者を癒すという、最後の持ち駒がある。 ・それは治療者としての最も基本的な資質であり、最大の技術でありアートでもある。 ・治療者自身の心の問題は、決して忘れてはいけないものだと思う。 ・治療者は患者が生への希望を捨てない以上、たとえ必ず死ぬとわかっていても、患者自身の生命を左右できる唯一の人間なのであるから、決して、希望を捨てるべきではないと思うのである。 ・考えてみれば恐ろしいことである。この世で唯一頼れる人から、希望を捨てられ、見捨てられるということの孤独。治療者にはその罪深さをもっと感じてもらう必要があるのではないだろうか。 ・患者は本能的に死と闘うものであり、その一瞬一瞬が、たとえ苦しく痛みに満ちたものであっても、患者にとってその時間は大変に大切な充実した時間であるからである。 ・科学はコンピューターなどを駆使して、人間の個人の未来さえも判断してしまう。しかし、それはあくまで一つの合理的な判断であって、感情をもった人間全体、即ち個人として、内的環境と外的環境という両者の統合された人間を簡単に判断し、診察できるものではないと思えるのである。 「手当て」の治療的意味 ・「手当て」という、治療を意味する言葉がある。「手を当てる」という本来の意味のことを考えると、わたしはずいぶんと長い間、患者を「手当て」しながら、治療はしていなかったように思う。 ・手を当てるということは、治療者が患者に生きるエネルギーを与えるとともに、患者の自然治癒力を阻害している障害を取り去ることであろう。 ・その力が大であればあるほど、治療的効果が期待できるものである。 道案内者はあきらめてはいけない ・医師の本命は治療にあり、治療は科学的な技術を必要とする。 ・これはあくまで職業である。治療における無駄と思えることをも、決してそうは思わないものにしていくためには、職業を超えた人間的な愛を必要とする。愛は耐えることができ、悔いることはない。 ・回復困難な患者をみながら、なお回復することを期待して治療することこそ、治療関係を失わない方法であろう。患者が希望を失わないかぎりにおいては。 第二章 治療関係とファンタジー 「共通感覚」の活用を ・現代ではM・E(Medical Engineering)が医学の中にさかんに入り込んで、すべてを対象化し数字化し、細胞から分子レベルまで分割分析してしまい、その分析された部分から全体としての人間を構成しようとする傾向にある。 ・生まれ、そして死んでいく人間の出来事や現象、即ち生きた人間自身をも静止させ固定化した状態で分割するので、生命をもった人間を全体像としてとらえる方法を見失ってしまうのである。 ・しかし、人間の精神現象や身体の痛み、不快、掻痒など未分化な知覚は簡単に対象化できない。 ・それは抽象化できない現象で、実に深く主観が入ってくる知覚であるからである。 第三章 心の癒しと治療者の任務 グリム童話の意味するもの ・日本では人間が神になれる風土がある。 名医の条件 ・今日の医療では、癌などでもう生命が助からないとわかっていても、やたらと患者を苦しめる点滴や高度の医療機器を使用して、みせかけの生命を保とうとしている。 ・ローソクの火が消えかけているのに、あたかもまだまだ燃えているように見せかけるのは、一体治療といえるのであろうか。 ・もはや薬が救命の用をなさなくなったとき、医師はそれを認め、身体の治療から心の癒しへとエネルギーを向けるべきであろう。 「癒し」を忘れた現代医学 ・今日、医療の世界では、「癒し」という言葉は忘れ去られてしまっている。 ・「癒し(healing)」はインチキ療法やいかさま治療と同一視されてしまっているので、医者自身は自分を「癒し人(healer)」とは考えていない。 ・「癒し」は「呪術」と同じように思われているし、非科学的な取るに足らないものと多くの医者は考えている。 ・現代では「病気」を直す人を医師といい、科学的医学では医師のその行為を「治療」と言っている。 ・今日、医師は患者が苦しんでいる原因に眼を向け、それを科学的に究明することだけに努力を傾ける。 ・言いかえれば、医師は「病気」は診ても「病人」は診ないということである。 「医者よ、自分自身を癒せ」 ・患者が苦痛を感じて診察を請うとき、医者は習慣的に原因を究明する。病気の原因は病気自体の現象と混同されてしまうのである。 ・どうも「病気」と「疾患」は別のものであるらしい。言いかえれば、「病気」と「病気をもった人間」とは現代では実際には全く別ものもになってしまったのである。 癒し(healing)と治療(curing) ・病気と病人を混同する医師にとって、癒しと治療は区別されてはいない。 ・患者の精神的苦悩を援助するようなアプローチをすることもまた、医師の仕事の一部なのである。実際にはどんな病気でも、心と身体が相関し合っているのであるから。 第四章 術後癌患者の生き方を探る ――グループ・イメージ療法の提唱―― 内向的な癌患者の性格傾向 ・癌患者の性格傾向 まじめで内向的であり、働き者で、職場では人並み以上の過剰適応型人間であるが、遊ぶのがへたである。 東洋的グループイメージ療法の技法 ・免疫細胞は外敵が自己であるか非自己であるかを見極めることによって免疫機能を発現する。 ・癌細胞は自己の細胞から突然無制限に増殖して、遂には宿主である自分自身を殺してしまう結果になる。 ・不思議なことに、この癌細胞を免疫細胞は非自己とは認めたくない。従って免疫機構が働かないので癌はどんどん増大していく。 ・この免疫細胞の主役がリンパ球のT細胞・B細胞である。 第五章 ヒト癌の自然史と患者の深層心理 発癌因子の探求 ・多くの癌患者を診ていると、癌が全身にまわってしまって、末期の状態になっていないときから、彼らはすでに癌のイメージにやられてしまっている。 ・これは驚くべきことで、肉体が癌にやられるころには、心もすでに癌にやられてしまっているのである。心が癌になってしまっているのである。 ・癌との闘いは結局、自分との闘いなのである。 癌患者の性格傾向を探る ・一つの病気になるためには、親から受けついだ体質というものがある。それに気質、性格が加わり、さらに環境が影響してくる。 ・最小限度この三つの要因が同時に作用して初めて病気になるわけであって、またその他の要因によるものもあると思える。 ・癌になる人には、やはり共通の性格傾向があるようである。 ・癌患者には、次のような性格傾向がある。 (1)幼児期に父母など愛する人との離別があったことが、調査した一部の人にみられた。愛の対象喪失は、人間をうつ状態にし、自閉的になり、更には自分に対し怒りを向けることになる。 (2)内向的で内に怒りをもっているが、その感情の発散がへたである。 (3)仕事には大変まじめで、過剰適応といえる状態である。 (4)しかし遊びがへたで、人間関係の中で適切な “間” をもつことができにくい。 (5)人との交流は必ずしも悪くはない。他の人だったら起こりそうなことでも、それを抑圧して人間関係を良くしているからである。 ・単純に考えれば、癌にならないためには、このような性格傾向と反対だったらよいのである。 第六章 臨死患者にとって「食べる」とは 生への意志としての食欲 ・戦後、母親たちの多くは自身の容貌のおとろえることをおそれて乳児に母乳を与えずに、人口乳にしてしまった。これはどうであろうか。 ・母乳を与えることによって、母と子のスキンシップを通しての非言語的なコミュニケーションが成立し、この経験を通して食と性(セックス)と人格的性(ジェンダー)の基礎が固まるのではなろうか。 ・時として、神経性食欲不振症の患者の中に、そのような乳児期のコミュニケーションの不在を見ることがある。 末期癌患者の食事に配慮を ・患者にとって、点滴とは何と無味乾燥なものであろう。静脈を通って栄養が身体に入っていっても、おいしくとも何ともないのである。 ・確かに栄養が良くなっていっているのはわかっていても、本当に生きているという実感からはほど遠いものであろう。 ・少々痛くても、下痢をし、嘔吐しても、食物が口から食道、そして胃腸と通っていってこそ、生きているという生命の充実感を感ずるにちがいないのである。 ・患者が実感として生きているという想いの抱ける援助をするために、人間の最後の願いである食事への配慮をもっと大切にしたい。 ・生への願いを託すような食べものを与え得るような看護を期待したいものである。 第八章 個性化と自己実現 問題をもつ人こそ成長する ・心に悩みをもっている人が、どのように苦しみ、葛藤し、そして、心の世界がそれ相応に統合されていくかを長年見ていると、かえって問題をもたない人の方が、いかに退屈でつまらないものであるかということがしばしば実感をもって感じられる。 ・心が揺れるということは、その人がさらに高い自我を望んでいるということであり、問題や症状の出現はそのための試金石に他ならないのである。まさに神経症は力であるという感じがする。 ・心に不安をもち問題をもつことこそ、人間の成長のための基本のように思えるのである。 病気の背景にある家庭・社会の問題 ・家庭内で俺だけは立派で問題はないと思っている父親がいるとすれば、その影の部分を家庭内の誰かが引き受けなければならないことになる。 ・実際、多くの登校拒否児、家庭内暴力児などの家庭に、このような例をみるのである。 ・個人の病気が個人のものだけでなく家庭、さらに社会の問題とも複雑に絡み合っているのであるから、そんな中で、病気をした本人が、真の自己実現への道を歩もうとすることは、大変なことである。 ・心身の変革については意識と無意識、更には身体との関係、即ち人間全体としての大きな視野よりみてゆく必要があると思うのである。 死への準備としての自己実現 ・誕生から死への過程において、自己実現の道を歩むということは、死への準備、つまり全き死を受容するための準備を意味するのである。 ・真に自己実現に達した人には、死に対する恐怖はもはやないといわれる。この究極において、生と死は初めて一つになるのである。 第二部 自己実現への歩み ――治療者としての自己探求―― 第一章 教育分析との出会い 教育分析を受けるまで ・手術頻回症の患者を通して初めて、メスでは切れない、心が原因で起こる身体病のあることを知らされた。 日本人にとっての母親のイメージ ・日本人にとって、母親の忍耐や苦しみを思うとき、自分の苦しい抑圧された感情さえも目をつむらなくてはならない気にさせられる。 ・しかし、そのような無意識の抑圧が心身症の発祥の原因の一つになっているように思える。これは日本人と西欧人との大きな違いではなかろうか。 第七章 終末期の自己実現 ――死の臨床から―― 人間は "生きてきたように死ぬ" ということ ・癌患者の性格傾向(西ドイツの癌学者、バルトラッッシュ) ①内向的でまじめで、感情の発散がへたで、しかも遊ぶのがへたである。 ②勤勉で、職場においても人以上によく働く。会社が中心で、家庭はその次ということである。 ③人間関係は非常によい。普通の人間だったら怒るようなことでも怒ったりしない。自分の感情に気づいていない。 ④怒りをつねに抑圧している。 ・癌患者で怒りを持っていても、これに気づかずに、他者に対しての怒りの感情を自分に向ける。このために二次的にうつ状態になる人が多いのである。 ・援助する看護婦・医師・病院・家族など、周囲の対象に向けて怒りを発散できる人は予後はむしろ良好である。 ・うつ傾向をもつ患者程、ケアが困難である。なぜなら感情の抑圧が強くて適切なコミュニケーションがとれないからである。看護婦も医師も――そして家族が最も苦しむのだが、援助できないためである。 ―― 完 ―― |