
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2020年05月06日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |
8 |
20.04 |
苛立つ中国 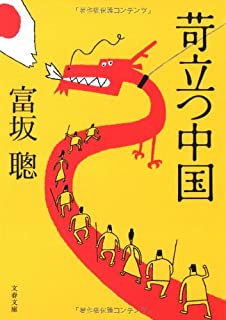 |
富坂 聰 |
文春文庫 |
◎ |
第一章 膨張する反日エネルギー 反日問題の複雑化 ・中国で行われるデモには、市井の人々が政治参加を望む要求と、それをさせまいとする権力の拮抗がかならず重層的に絡んでいる。 ・民間人の政治参加、発言の要求を「民主化」と呼ぶならば、反日デモが認められるか否かは、民主化が認められるか否かとも重なる問題なのだ。 ・反日デモが認められないとしたら、民主化を阻んだ者は日本であると混同されかねない。その場合、現在の中国人は日本を抑圧勢力と見做すだろう。 第二章 西安の日本人狩り 恐怖体験の始まり ・事件(西北大学の日本人留学生が起こした寸劇事件)を通して浮かび上がるのは、中国社会に存在する恐ろしい一つの特徴である。 ・たとえ誤解であっても一旦走りだしてしまえばなかなか修正はきかない。日本人の悪を追及する話であればなおさらその傾向は強まる。 ・また、たとえ修正されることがあっても、それは原状回復が難しいほど大きな被害を出してしまった後なのである。 中国人が感じる「侮辱」 ・中国政府が警官を使って日本を守ることで、市民の中の「反日」が増幅される。 ・また、日本を守ることで警官のなかにある「反日」も覚醒し、増幅される。 ・この負の連鎖は、「反日」への対処を現地の権力だけに委ねている限り、今後さらに中国各地で繰り返されていくのである。 自殺する日本人ビジネスマン ・官製メディアしかない中国では、情報は上から与えられるものであり、その例外は口コミであり、また最近では「民主化」の窓でもあるインターネットなのである。 ・そもそも中国人にとっては、どんな言論もある程度は政府の管理を経たものだと考えてしまう傾向があるのだ。 第三章 反日運動の「七勇士」 尖閣海域に眠るエネルギー資源 ・中国が尖閣諸島を自国領土だと主張する根拠 中国人はもともと、列強や日本に国土を蹂躙された暗黒の近代史のどさくさのなかで支配権を奪われたという気持ちが強い。 中国人が島の第一発見者であることや命名者であること、そして大陸棚の一部であるという地理的な観点から、自国領であるとする説明もある。 また、アメリカの反対によって参加できなかったために、中国が「サンフランシスコ講和条約を認めていない」という立場から、日本の実効支配を「無効」だと主張する者もいる。 ・日本と中国の議論のベースが噛み合わないのは、近代国際法を基準とした話し合いにならないためだ。 ・日本は、明治十八年から内務省が沖縄県に命じて始めた調査によって、尖閣諸島にはいかなる外国の支配も及んでいないことを確認し、島の領有を宣言。明治二十八年、どこからも異議の申し立てがなかったことを確認した上で日本領土に編入したのである。 ・もちろん、戦争によって奪ったのではなく国際法上必要な手続きを経て領土に組み入れたものなのだ。 ・事実、大正八年に中国福建省の漁民三十一人が遭難し魚釣島に流れ着いたのを、同島で活動中の古賀善次が救助したことに対して、長崎駐在の中国領事が石垣村長と古賀へ宛てて感謝状を送り、その中には「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島内和洋島」と記されていたのである。 ・戦後、サンフランシスコ講和条約で沖縄や奄美と共に一時期アメリカの施政下に置かれたが、沖縄返還にともなって再び施政権を返され、その後ずっと実効支配してきたのである。 ・その間中国共産党は対アメリカをふくめ日本に対して一度も抗議をしたことはなかったのである。 ・中国が自国の領土だと言い出したのは一九七〇年代に入ってからのことに過ぎない(七一年に魚釣島などの島嶼に対する領土主権を国連海洋法委員会で公式に表明した)。 ・それも、同海域に豊富なエネルギー資源が眠っていることが、ECAFE(国連アジア極東経済委員会)の調査や日本政府の調査(六九~七〇年)によって明らかになった直後からの主張だ。 ・どこの国の地図に最初に書かれたとか、命名者がどこの国の人間かといったことで領有権が決まるのであれば、世界の現実は例外だらけと言わざるを得ないし、またそれを言い出したらキリがない上に混乱は必至だろう。それを避ける意味でも国際的なルールが定められているはずなのだ。 政府に認められていない組織 ・尖閣諸島に上陸した彼らの行動は、「絶対多数の中国人が支持した」という童増氏(反日組織のリーダー)の言葉は恐らく誇張ではない。にもかかわらず、彼らの露出が国内で異様なほど限られていたのはなぜなのかということだ。 ・その答えは単純明快である。中国政府が、国内の主要メディアに対して彼らを取材することを禁じていたからだった。 ・上陸直後、国内主要メディアに向けて出された政府・中央宣伝部の通達 <過激な民族主義的感情を煽ったり、事態を拡大させて、不必要な社会不安の要素がつけ入る隙をつくらないよう。各報道機関は、厳格に節度を保ち、いわゆる「連合会」のメンバーに対する取材を行ったり、紀事を載せること、またはテレビで追跡報道をしたり特集を組むことをしてはならない> ・政府は彼らの “英雄的” な行動を喜ぶどころか、むしろ警戒している様子がうかがえる。 ・実は、尖閣諸島上陸で高まった中国の反日運動は、運動の前面に名乗り出た連合会とそれに熱烈に支持する世論、そして二つを複雑に見守る政府という張り詰めたバランスのなかで鼎立していたのである。 同情されない広島・長崎 ・日本人も中国人も、相手を知る以前の段階で互いを「近い存在」と認識しがちだ。 ・だが、現実には日本人と中国人の間には埋めがたいほどの深い溝がある。 ・政治体制の違いにはじまり、ほどこされた教育、生きてきた環境、触れてきた情報、立場、歴史観や国家観、さらに生きるということへの姿勢も根本的に違う。 ・日本人と中国人の違いを認識しないまま互いに接したとき、当たり前だと思っていったりしたことが、相手の目には思わぬ “悪意” として映りかねないのである。 ・例えば、八〇年代に日本に留学していた中国人たちは、アルバイト先の電話を借りて長話をして顰蹙をかっていたが、そのころの中国では基本的に職場の電話はタダで使えたという環境の違いがあった。 ・しかも、働いても働かなくても賃金に差が生じなかった当時の中国人にとっては、西側社会では当たり前な概念である「勤勉さ」も理解できなかったのである。 ・「中国人は列に並ばない」とか「横から割り込む」といった認識が日本にも広まったが、並んでいさえすれば目的とするものが手に入る日本とは環境が違うのだ。 ・問題は、こうした厳しい環境になれた中国人が日本で人々が並ぶ列を無視したとき、日本人が中国人を「同じ価値観を共有している」との前提で判断するのならば、彼らのイノセントな行動は間違いなく悪意と受けとめられるだろう。これこそ無用な摩擦を生むメカニズムなのだ。 ・つまり、双方が何も努力しないままに「分かり合える」という先入観を持つことは、本来なくてもよいトラブルを作り出す装置となってしまうのだ。 ・忘れてならないのは、過去の歴史から現在の時事問題にいたるまで、中国人も日本人と同じ情報を共有し物事を判断しているという思いこみだ。これも「誤解」である。 ・現実には、施された教育にはじまり政治体制の違いなど、歴史へのアプローチにはほとんど共通の接点はない。 ・例えば、東京大空襲は日本人が被害者として語ることのできる数少ない歴史的事件だが、中国では、「重慶爆撃をやった日本がアメリカにやられるのは当たり前だ」と切り捨てられてしまう。広島・長崎の原爆も同じように中国人の同情を得ることはまずない。 ・南京大虐殺では、客観的に見ても三十万人という数字はあまりに大袈裟ではないかと日本人が考えるのに対して、中国人は日本人がこの問題で異論を述べたり反論したりする行為そのものが許せないのである。 ・その結果、「日本人は歴史認識がまるで足りない」という感情的な爆発に遭遇することになる。 ・中国が重視する近代史にしても、日本人は長い歴史の連続性のなかでとらえようとするのに対して、中国人は「侵略戦争」だけを切り取って日本を断罪する傾向をもつのである。 ・問題は、本来、非常に政治的な色を帯びているはずの歴史に対して、日本人も中国人も互いに自分が理解している歴史だけを "客観性" のあるものとして相手と向き合おうとしていることにある。 ・日本には、現政権の正統性に歴史解釈を引き寄せなければならない中国とは違って、自分たちこそより「客観的事実性」をもって歴史をみているのだという自負がどこかにあるように感じられる。 ・つまり、中国の側はいまだに生々しい「政治」を背負った歴史なのに対して、日本の主張は純粋の学問としての歴史であり言論の自由という世界のなかでの歴史なのだ、と。 ・そんな両者が、互いに自分の側にこそ「客観性」があるとぶつかりあっても、接点はうまれないだろう。 ・古来、戦いに勝った国が歴史を作ると言われてきたように、戦争を挟んだ二国間に、一つのHistory(=歴史、物語)が共有されることなどあり得ないのではないか。 ・かつてナポレオン・ボナパルトが言った言葉――「歴史とは、合意の上に成り立つ作り話以外の何物でもない」は、じつに示唆に富んでいると言えるだろう。 第四章 迷走する香港 「日本の沖縄領有は非合法である」 ・中国は清朝の崩壊から中華民国を経て中華人民共和国へと政権が移っていく過程で、自分たちに都合のよい約束だけを引き継ぎ、都合の悪いものは放棄するということを対外関係のなかで繰り返し行っている。 第五章 靖国参拝の是非 中国にかけられた呪縛 ・民主主義の社会では民意は正義だが、民意には複雑な判断はできない。 ・住民投票などを見れば明らかなように「イエスかノーか」の単純な判断を超えた複雑な処理はできなくなるのである。 ・外交を見るにあたっては、もしも「勝ったか負けたか」が成否の基準となれば、外交の現場はたちまち柔軟性を失い、行き着く先は衝突しかなくなってしまう。民意が二国間の利害の調整に適しているかどうかはこの点を考慮しても明らかだろう。 ・中国は民主を標榜しているものの、実質的には共産党による一党独裁国家である。その独裁政権をもってしても、中国は日中国交正常化の時点からずっと、「民意」という呪縛にはとらわれ続けてきたのである。 A級戦犯の矛盾 ・「日本からわざわざ問題を中国に持ち込み、向うの中・中問題に火をつけて帰ってきた人々」とは誰か。言うまでもなく、社会党の議員や朝日新聞の記者たちのことだ。彼らが靖国問題に火をつけるため、中国という外圧を利用したことはすでによく知られた話だ。 日本の軍拡に寛大だった鄧小平 ・中国をして七二年の日中国交正常化へと大胆に向かわせた最大の要因は、ソ連の脅威があったからにほかならない。 ・六〇年代末から深刻化する中ソ関係は、七〇年代に入っても深刻な局面を抜け出すことができないままであったのだ。 第六章 中国人を味方にできない日本企業 「民主化」の波を受け入れよ ・日本は中国と競って軍拡はしない。そうした分野で競うことはしないが、一旦「自由」や「人権」に絡む問題が持ち上がれば、中国がいかなる圧力をかけようとも支持し、亡命者を受け入れる。そうすることで日本の新しい「価値観」を「中国」にではな「中国人」に向かって発信するのである。 ・こうした発信を辛抱強く続けていくことによって、中国人の頭のなかで「民主化」と「日本」のイメージが重なれば、中国に起こる新たな動きは日本を受け入れるかもしれない。いやむしろ、日中問題の解決の糸口はそこにしかないかもしれないのである。 あとがき ・日中間に平和を保つための要は、反戦を叫ぶことでも自衛隊を目の敵にすることでも、ましてや中国に遠慮することでもない。国民のなかにある中国への「恐れ」を取り除くことである。 ・もしも国民が本気で中国を恐れるようになれば、勇ましい対中強硬論がたちまち日本を覆うことだろう。そのとき、憲法第九条など何の役に立とう。 ・落選したくない政治家は国民の声に迎合する可能性が高く、ジャーナリズムが売れないことを覚悟で世論の逆風に立ち向かうことも期待できない。「マス」に支持されなければ敗北となるのだから当然だ。 ・中国は、近い国だが外国である。外国との付き合いでは疑心がつきものだ。日本のリベラル層はこの疑心に冷淡で、人びとの「苛立ち」や「恐れ」を ・日本は中国を警戒すべきかもしれないが、恐れる必要などないのである。 ・外交は、世論の熱狂から距離を置くことが急務だ。 ・外交は国民の「感情」を満足させる道具ではない。もしもそんな方向に進めば衝突は必然だろう。 ・日本の外交に必要なのは国民の信頼を得ること。そして「世論」から解放されることだ。そのためにも国益重視の姿勢を貫かなければならない。 ・最悪なのは従来型の "パイプ" を強調する外交であり、「中国通を自称する政治家が中国で中途半端な歩み寄りを見せて帰国する」ことだ。 ・そうなれば国民は「政治家個人が中国から利益を受けて国益を蔑ろにした」と疑い、ますます外交問題にコミットしようとする意志を強めるからだ。 ―― 完 ―― |