
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年10月01日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |
11 |
21.02 |
新版 魏志倭人伝 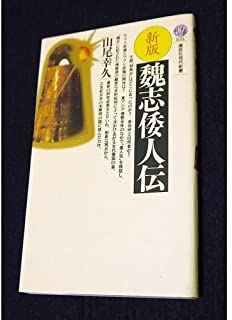 |
山尾幸久 |
講談社現代新書 |
◎ |
Ⅰ―『魏志』倭人伝の成立 2―『魏志』東夷伝の成立 3―『三国志』の版本と後代の書物 「壹」「臺」のどちらが原形か ・三世紀の倭王が都していた「邪馬臺」は、ヤマトである。 Ⅱ―王都「 1―道程記事解釈の前提問題 3―水陸の行程の算出 ふつうは日数計算 ・里程は ・記里鼓車とは、一定円周の車輪の回転を、何枚もの歯車による減速装置に伝え、一〇〇回転ごとに人形が ・皇帝の行幸や親征では、この車を引く者が鼓の音を記録しておく。このばあいには道路上の実距離が正確につかめる。ただ海上ではつかえない。 ・ふつうは所要の日数(または刻数)によって行程を概算する。 ・歩行の日数は、当の使人その人が里数に換算して復命することがありうる。しかし船行は日数のまま報告するのがふつうであろう。風向・風速・波浪その他の条件によって速度はまったく違い、換算は困難である。 ・ところが、『魏志』倭人伝の、帯方郡から ・大きな問題は、郡使はどのような方法で里数を算出したのかである。 ・方位については、魏の時代にはすでに指南車が使われている。これも歯車仕掛けの車である。 ・最初に人形(腕を上げて正面を指さす形)を正南に向けておく。そうしておくと、引いている車の方向いかんにかかわらず、人形は常に正南を指さしている。ただ海上ではこれは使えない。 一日の行程は四〇里前後か ・所要日数から里程を概算するとすれば、通常の旅程のばあいは一日四〇里(約一七キロ)前後であろう。 水行日程は徒歩と同じか ・海上交通の日程についてであるが、中国には豊富な史料がある。 ・ただ、これらは、『魏志』倭人伝の解釈にそのまま適用することができない。 ・なぜなら、『魏志』倭人伝の水行日程(「二十日」「十日」)は、三世紀の倭人の通常の所要日数なのである。 ・三世紀頃の倭人の船は、オールで漕ぐ "準構造船" であって(古来の丸木舟ももちろん使われている)、帆走することはまずなかったと考えられている。 ・それに対して中国のばあいは、オールで漕ぐほかに帆が推進力として使われている。 ・積荷がないばあいでも、せいぜい徒歩と同じ程度であろう。ここでは一日四〇里(約一七キロ)前後と見ておきたい。 4―放射式・並列式の読解法 放射式読法の注意点 ・『魏志』倭人伝の行程の記事を解釈するうえで大きな問題が二つある。その第一は "放射式読法" の問題である。 ・伊都国から先の国の方位・道程は次のように書かれている。 ・これは伊都国を起点にした書きかたで、順次経過する書きかた( "連続式" )ではないという。 ・ "方位・距離・地名" のばあいは "連続式" である。 "方位・地名・距離" のばあいは "放射式" である。それが中国の古書の伝統的な書きかたであるという。 ・『魏志』倭人伝には、伊都国について、「都使の往来に常に駐まる所なり」と説明している。その先は伊都国を起点とした方位と道程とが記されているのである。 「水行十日・陸行一月」の意味 ・もう一つの問題は、伊都国から ・『魏志』倭人伝の本文によるかぎり、「水行十日・陸行一月」の邪馬台国は、同じく「南」に位置する「水行二十日」の投馬国よりも、なお遠い南方にあった。この認識は争う余地がない。 ・「女王の境界の尽くる所」(「其の余の旁国」の分布の南限)のさらに「南」にあるのは狗奴国である。併記式読法は史料に忠実ではない。 ・伊都国から邪馬台国まで「水行十日・陸行一月」という記載は、倭人からの伝聞と推考される。 ・三世紀の倭人の航海術は、速度については徒歩と似たようなものであったと考えられる。 ・伊都の南にあって、そこへといたるのに陸道が水道の三倍もかかるというのは、東または西に大きく湾入した地形を考えねばならない。しかしそれは地形の実際に整合しない。 2 中国人が見た王都の所在地 2――誤った情報の探求 七世紀中国の倭国地理像の修正 ・中国人は、三世紀の「親魏倭王卑弥呼」も、五世紀の "倭の五王" も、七世紀の「倭王、姓は ・『隋書』倭国伝はいう。 「倭国は百済・新羅の東南、水陸三千里に在り。大海の中において三嶋に依りて居る。魏の時に訳を中国に通ずるもの三十余国なり。みな自ら王と称す。夷人は里数を知らず。ただ計るに日を以てす。其の国境は東西は五月行、南北は三月行にして、 ・『旧唐書』倭国伝はいう。 「倭国は ・『後漢書』の注 六七六年から六八〇年にかけて、 七世紀中国人の邪馬台国観 ・三世紀の王都 yamato と七世紀の王都 yamato とが連続的に理解されているのは、まったく疑問の余地がない。『隋書』や『後漢書』注は、七世紀の中国人がいわば邪馬台国畿内説であったことを示している。 ・また『梁書』倭伝は、「 ・七世紀の中国人には「邪馬台国が畿内大和であることを疑わせるようなことは何もなかった。 「一万四千里」の新知識 ・ところが、そうした認識とともに、『隋書』には、「其の国境は東西は五月行、南北は三月行にして、各海に至る」の記述が現れる。直前の文(「夷人は里数を知らず、ただ計るに日を以てす」)から推測して、これは遣隋使など倭人からの聞きとりをもとにしていると思うが、東西に長いかなり大きな島国のように認識されている。 ・六〇八年に 「又 ・これも筑紫から東に向かい、瀬戸内海沿岸の、倭王に従属する十余の国を、東へ東へと経由している。 ・『旧唐書』ではさらに「京師(長安)を去ること一万四千里」となる。これは新しい知識なのである。 ・三世紀の『魏志』倭人伝は帯方郡から「万二千余里」であった。 ・三世紀の中国人の倭地に関する認識、すなわち朝鮮半島の南端から福建省地方の東方まで約二一〇〇キロにわたって点在する群島である、という認識は、実際の地理からかけ離れた不正確なものであったらしい。七世紀にはそれがいくらか修正されたらしい。 橋本増吉説に学ぶ ・七世紀の中国史料は、新知識によって、邪馬台の所在地を、北部九州の「南」から「東」へと訂正しているのである。これほど確かな根拠はない。 倭地南方観を支えたもの ・第一に、三世紀の中国人の先入観をうかがうことができる。 ・五七年、倭の奴国王の使者が洛陽に入った。これは中国の王都の人びとが、倭人を見た最初である。 ・五七年に倭の奴国王に授けられた金印の ・『魏志』の記述の背後には、後漢時代以来の中国人の固定観念があると考えられる。 ・第二は、『魏志』倭人伝の "自然・人文地誌" の部における南方色の優越の問題がある。 「男子は大小と無く皆鯨面文身(入墨)す」。 ・『魏志』倭人伝の "自然・人文地誌" の部は、やはり主として二四〇年頃に北部九州までやってきた梯儁の記録をもとにしているのであろう。二四七年頃から何年間か王都に滞在した張政の見聞もある。 方位誤解説には客観性がある ・第三に、魏朝が邪馬台の卑弥呼を「親魏倭王」に封じた破格の厚遇が、魏人の倭国所在地観を端的に示している。 ・何にもまして大事なことは、中国から見た政治的利用価値である。 ・「親魏倭王」への冊封の最大の理由は、倭国の所在が呉にいちじるしく近いこと、それにもかかわらず魏に入朝したことであろう。 ・呉は、魏の背後をなす公孫氏の燕や高句麗とのあいだに、軍事的提携関係を樹立すべく強い政治的関心を払っていた。それに抗して、魏もさまざまの働きかけをしていた。「親魏倭王」 ・第四に、ずっとのちの時代になっても、日本列島を南北に長く描く地図があることである。 ・以上の四点を根拠として、私は、邪馬台の所在についての『魏志』倭人伝の記述のうち、実際の塵と一致しないのは、誤解されていた方位であると考える。 ・七世紀の中国人が新しい知識によって東と訂正したのに従って、三世紀の中国人の古い知識における「南」は、実際には東のことだと理解する。 三世紀の政治地図 ・『魏志』倭人伝の「 ・北部九州に「 Ⅲ―三世紀の倭人の社会 1―弥生時代の社会とその混乱 2―倭国の乱とヤマト政権の出現 倭国の乱の前提条件 ・一八〇年代前後に、ヤマト政権は、おそらくキビ政権との連携のもと、対外関係においてツクシ政権を統御する立場に立った。 ・ヤマト政権は、ツクシ政権から、対外的通交と鉄の供給機構との掌握態勢を継承したのである。 古墳時代への新しい文化要素 ・同じ弥生時代でも、二世紀代と三世紀代とでは、北部九州と近畿との関係は逆転したと考えた。その核心的事実を、ヤマト政権のツクシ政権制圧とした。 ・二世紀後半に鉄工技術や太陽信仰を担う朝鮮系有力集団が畿内中枢地に定着したのではないか。 2―初期ヤマト政権の政治と宗教 1―宗教的統合と女性最高司祭者 ヤマト政権の祭政二元構造 ・三世紀半ばのヤマト政権を見るうえで大事な点が二つある。 ・一つは、中国の皇帝を根拠として形づくられている東アジアの政治的構造のなかで、倭人種族を正当に代表するものと公認された「倭王」を擁していることである。 ・諸「国」を統治するうえで政治上・経済上共通する要求をもつ首長が、この倭王へ対外的交通を集約する必要上、倭王を代表者として求心的に結集している。 ・中国ではそれを宗主国-附庸国の関係で把握している。また倭王はそのような地位を維持するため、ツクシ政権を統制して、中国・朝鮮との交通を独占している。 ・もう一つは、ヤマト政権は、それ自体、二世紀末の近畿とその周辺の乱、遠州灘の勢力との戦争、それに続く第二次の乱を乗り越え、いちじるしく権力的性質を濃くした部族連合体である。 ・大事なことは、それが伊勢湾沿岸から周防灘沿岸に分布していた二一もの部族、または部族連合の祭政的結集の核となっていることである。「男弟有りて国を治むを ・前者は諸国首長の国内統治とヤマト政権の機能との相互関係を見る視覚、後者は倭王への対外交通の集約と祭祀儀礼の共有との相互関係を見る視覚、の必要性を示しているであろう。 女性最高司祭者と宮廷巫女団 ・ヒコ・ヒメは、元来は神秘的な霊力をもつ男・女の意味である。したがって、ヒメコは固有の実名ではなく、地位に就いての尊称である。 ・「 ヤマトの宗教の広域信仰圏 ・「邪馬台」とは畿内のヤマトのことであった。ヤマトの語が指すところは、「日本」すなわち天皇の統治権がおよぶ領域を最大の空間範囲とする。 ・もっとさかのぼれば、ヤマトといえば三輪山の麓のことであったと思う。 ・「能く衆を惑わす」とあるように、ヒメコの宗教は絶大な信者群を獲得していた。西日本各地の首長層のあいだに、みずからが主宰する地域的・完結的な信仰や祭祀とは重層的な関係で、ヤマトの宗教が共有されていったのである。 ・その一証は鏡である。景初三年の詔には、「銅鏡百枚」をヒメコに下賜するとある。これはヒメコの要請にこたえたものであろう。詔には「汝国中の人に示せ」とあるので、彼女の祭祀に参加する女性を通じて、各地の首長に分与されていったのであろう。 ・三世紀半ばに、ヤマトを中枢とする広域信仰圏が成立していること、点々とではあれ、祭祀儀礼共有関係が倭人種族の次元で拡大していること、この点を過小評価してはなるまい。 ・一つは「倭王」の資格認定の必要条件の問題としてである。他の一つは、地域性を断絶し画一性を特色として出現する古墳文化の史的前提としてである。 ・この時代に広域信仰圏が成立した理由は、この宗教が、戦争と動乱とのさなかにこれを統合と安定とに転化したこと、ヒメコの「共立」とは、実は、この新宗教の女性最高司祭者の地位を置いたのであったことから考えるべきである。 ・一、二世紀の西日本はけっして牧歌的な時代ではなかった。むしろ闘争を基調とする時代であった。 ・共同体としての地域集団の結成から、政治的社会としての「国」の結成、さらには諸「国」首長の権力の統合機構(地域政権)の結成にいたるまで、常に緊張と対立のモメントをはらんでいた。 ・「国」と「国」との戦争、地域政権の盟主の地位をめぐっての大小の戦争や動乱が、各地で絶え間なく起こったと思われる。 ・慢性化した不安から解放され、新しい秩序原則による平和を志向する時代思潮は、社会に普遍的に潜在していたであろう。 ・三世紀後半頃から、ヤマトの男王への求心的結集による列島規模での安定期、いわば " ―― 完 ―― |