
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年11月01日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
13 |
21.02 |
池上彰の宗教が わかれば世界が見える 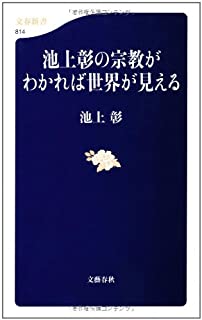 |
池上 彰 |
文春新書 |
◎ |
第1章 宗教で読み解く「日本と世界のこれから」 ~東日本大震災・ビンラディン殺害・中東革命 いまこそ伝統宗教の出番だ ・本当にいい人なのに不遇であるという方は大勢います。いい人であるが故に不遇になるのかもしれませんが、苦労して、結局、報われずに亡くなっていく人たちがいる。その一方で、本当に悪いやつが羽振りをきかせている。 ・そんな残酷な現実に対して、「こんなことがあっていいわけがない。いい人たちは、来世では幸せになるだろう。悪いやつは来世では地獄に落ちるだろう」と思う。少なくとも、そう信じることによって、心が落ち着く。 ・このような心の働きから、宗教心が育っていくのだと思います。 ・人々は、なぜ宗教を求めるのか。結局は、心の安寧を求めているのです。 ・それに応えることが宗教の役割だった。理不尽な世界に生きる人間の心に安寧や平穏を与え、納得させる。それが宗教の始まりであり、変わらぬ役割であろうと思います。 日本人は無宗教なのか? ・日本人はけっして、たんなる無宗教ではなかったのです。 ・日本人は、日本人なりの宗教観、あるいは超自然的なものに対する畏れのような宗教意識を、実はしっかりと持っているのです。 増加するイスラム人口 ・カトリックでは、避妊は禁じられています。ユダヤ教も同じです。 ・「産めよ、増やせよ、地に満てよ」と神様が命ぜられたのですから、避妊してはいけないのです。せっせと子どもをつくることが、神様の教えに叶うことです。 ・イスラム教では、「避妊をしてはいけない」とはされていません。けれども、セックスは神様が私たちに与えてくれたものだから、十分楽しめと、『コーラン』に書いてあります。 ・ただし姦通は、極刑です。楽しめ、しかし家族社会が崩壊しないように、家族の中にとどめなさい、とされているのです。 ・結果的に子どもが増えます。いま、イスラム教徒の人口は大変な勢いで増加しています。ヨーロッパからみると、イスラム教の脅威とは、人口の脅威でもあるのです。 インドの経済発展とカースト制 ・カーストは、非常に厳密です。たとえば日系の企業が現地でオフィスを掃除する人を雇おうとしたなら、テーブルの上を拭く人と、床を拭く人とは、カーストが違います。 ・ところが、そうやって仕事を分けることによって、結果的に、ワークシェアリングが成り立っています。十二億の人たちがうまく仕事を分け合ってきたという面もあるのです。 インド人はみなターバンを巻くのか ・実はターバンを巻くのは、シク教徒だけなのです。 ・シク教徒とは、西から入ってきたイスラム教の影響を受けて、ヒンドゥー教徒の一部が一神教徒に変わったものです。ヒンドゥー教とイスラム教との接点で生まれた新しい宗教です。 ・シク教徒は、インドの人口のたった二%しかいません。 宗教はよく死ぬための予習 ・宗教を考えることは、よく死ぬことだと思っています。宗教は「死のレッスン」と言った人もいます。つまり、どう死ぬかという予習なのです。 ・よりよく死ぬとは、よりよく生きることでもあります。 ・よく生きることができれば、従容として心穏やかに死を迎えられるのではないか、と思うのです。むろん思い残すことはないというのが理想です。 ・しかし、たとえ思い残すことがあっても、自分は生きてきた中でそれなりのことはやったという思いがあれば、死ぬことを、しょうがないことだとどこかで納得できるのではないか。 ・死の予習をすることが、よりよく生きることにつながる。それが宗教を考える意味だ。 宗教がわかる! 第2章 ほんとうに「葬式はいらない」のですか? 宗教学者 島田祐巳 日本人はほんとうに無宗教か 島田 ・日本人にとっては神道と仏教はそう簡単に分けられないものですよね。仏教が伝来した飛鳥時代からずっと神仏習合の文化でしたから。 ・日本人の多くが「無宗教」と言うようになったのは、明治政府が神道と仏教を別々の宗教として分けて、廃仏毀釈運動などが起こった時期からです。 ・それでも、やっぱり分けられないんですよ。どっちか選択しろと言われても、片方を選択できる人はほとんどいない。 ・やむをえず「無宗教だ」と答える。それだけ、どちらも深く根付いているんです。 ・これだけ宗教が自然に根付いている国は、かえって珍しいんじゃないですかねぇ。 仏教寺院の経済モデルが成り立たない 島田 ・そもそもお寺とは、古くは寺院の建立を発願した人間が、建立後も田畑を寄進して、そこから上がる収入によって寺院を維持運営するという構図になっていたわけです。それが、明治時代に「上知令」が出て、それら寺の領地は召し上げられ、さらに戦後、GHQの指令に基づく「農地改革」で農地を奪われた。この二度の改革で、仏教寺院は決定的に経済基盤を失ったのです。 仏教がわかる!➊ 第3章 「南無阿弥陀仏」とはどんな意味ですか? 浄土真宗本願寺派如来寺住職 釈 徹宗 「南無阿弥陀仏」とは 釈 ・南無阿弥陀仏は「この世界に満ち満ちる、限りない光と限りない生命の仏さまにおまかせして生き抜きます」という、自分の生きる姿勢を表わす言葉になります。 ・自分の生きる姿勢を常に口にして人生を歩む「信仰告白」は、世界の多くの宗教で見られます。私は、人類学的に見ても、とても重要な行為だと思っています。 戒名は自分でつけられる 釈 ・浄土真宗は受戒しないので法名という。 仏教がわかる!❷ 第4章 仏は「生・老・病・死」を救ってくれますか? 臨済宗神宮寺住職 高橋卓志 お寺を地域の拠点に 高橋 ・団塊世代の六百数十万人が老の域に入ってきたら、国家の社会保障もうまくいくかどうかわからない。そのときに、寺がもっている潜在能力をしっかり発揮できたら、間違いなく社会は変わります。 ・土地はある、建物ももっている、人脈もあるのだから、それらを最大限に使い、その地域に高齢者の支援施設をつくっていくというアイデアは見過ごせません。 ・たとえ檀家数が少ない寺の場合でもデイサービスやグループホームなど、介護保険の対象になる運営が可能です。しかも、地域のお年寄りとの深い交流も可能になります。寺の運営と同時に、社会にも貢献できるのです。 ・これから大変な状況になる団塊世代をケアし、サポートができます。 神道がわかる! 第6章 日本の神さまとはなんですか? 國學院大學前学長 安蘇谷正彦 安蘇谷 ・神社の本殿には鏡などのご神体がまつられていることが多いのですが、そこに神様が住んでいるわけではなく、あくまで神の実在のシンボル(象徴)と考えるべきです。そのシンボルを通して神様を拝む、としか言いようがない。 ・伊勢神宮に天照大神が住んでいると表現するのはよくないでしょう。しかし、天照大神は神霊として生きているわけですから、生きている天照大神を拝むには、伊勢神宮へ行って、あの御正殿の前で拝むのがいちばん良い。 ・しかし、ほかに拝みようがないのかといったら、大体いま、一千万体くらい、「大麻」といわれる神宮の御札が全国の各家庭で祀られていますけれども、それを拝んでいるわけですね。御札を通して、天照大神を拝んでいるわけです。 ・神さまのあり方というのは時間・空間を超えている。 神道における「神様」とは 安蘇谷 ・まず祖先の霊です。それから自然ですね。太陽神とか風の神とか。あるいは海山川などのご神霊を祭っています。 池上 ・それで八百万の神といわれるくらい、たくさんの神さまがいらっしゃるということになるわけですね。 神仏習合は不自然ではない 阿蘇谷 ・神道は稲作と結びついた日本人にとっての生活様式で、そこに後から仏教が入ってきた。神道に属しながら、仏教徒でもある、という神仏習合は日本人の重層性を示していて、少しもおかしなことではないと思います。 ・実際、奈良時代の頃には神様がかかわるお寺が「神宮寺」と称して各地に建てられます。 池上 ・神道は、もともと共同体を維持するための生活スタイルのようなものだから、融通が利く。後から入ってきた宗教を排するどころか、仏教とは混じり合ってきた。だから日本人が神社とお寺の両方にお参りするのはあたりまえというか、おかしなことではないということですね。 イスラム教がわかる! 第7章 「コーラン」で中東情勢がみえますか? 東京外語大学教授 飯塚正人 飯塚 ・飲酒についても、最初は飲んでいいとなっていたのが、だんだん変わっていって、最後は飲んではいけない、ということになりました。 ・もしお前たちが節度を守って酒を飲めるのだったら飲んでいい。ところが節度が持てないのでだめにした。そういうふうに変化した。 池上 ・『コーラン』には酒を飲むと、互いに憎しみ合うようになり、神を忘れて怠るようになるからだ、と書かれています。 なぜ女性をベールで覆うのか 池上 ・女性はベールをかぶらなくてはならない、といったイスラム世界のルールは、すべて『コーラン』に書いてあることなのでしょうか。 飯塚 ・『コーラン』には女性の服装についての記述が主に二カ所あります。 ・一つは「女性たちにジルバーブを纏うように告げなさい」というもの。ただし、ジルバーブというアラビア語には、ベストという意味も、マントという意味も、ベール(ヒジャーブ)という意味もあり、幅があります。 ・もう一つは、「女性の体のうち外に出ている部分は仕方がないが、それ以外の美しいところは隠せ」というものです。これもずいぶん幅のある表現ですね。 ・その解釈によって、アフガニスタンのブルカのようにすべてを隠す服装をする国もあれば、トルコのように欧米や日本と同じ服装でいい、という国も出てくる。 ・中東の男性は、女性の髪の毛に猛烈に興奮するようです。だから髪の毛を隠すようになった、という説が有力です。 池上 ・「豚肉を食べてはいけない」というタブーは、どういうところから来ているんでしょうか。 飯塚 ・これもまた『コーラン』に、「豚肉や死んだ動物の肉を食べてはいけない」と書かれているのです。ただ、その理由までははっきりしません。 ラマダン月の断食はユダヤ教の習慣? 池上 ・一年のうち一カ月間、夜明けから日没まで食事をとらないラマダンの断食は、どのように始まったのですか。 飯塚 ・実は、断食はもともとユダヤ教の習慣なんです。それをムハンマドが見て取り入れた、と言われます。 池上 ・『コーラン』は「一夫多妻」を認めている。 飯塚 ・一夫多妻の根拠は、『コーラン』に、「おまえたちがみなしごに公正にしてやれそうもなかったら二人目、三人目、四人目の妻をもらえ」と書いてあることです。 ・実はイスラム教は、キリスト教と違って性欲に否定的ではありません。むしろ人間の根源的な歓びで、十分楽しむべきだと考えている。 自爆テロの論理は 飯塚 ・一九七三年の第四次中東戦争で、エジプトのサダト大統領がユダヤ教国であるイスラエルとの戦いを「ジハード」と言いだしたのが発端です。要するにイスラム教徒の領土を守るための自衛の戦い、ということです。 ・自爆テロを一般化させたのはレバノンのシーア派組織「ヒズボラ」です。 ・ヒズボラは、圧倒的なイスラエルの軍事力と戦うのに、ただ行っても撃たれて殺されてしまうので、自分の体を武器にするということを考え出した。 ・ただ、イスラムは自殺を禁じていますから、「これは自殺ではない」という理屈にするわけです。あくまでもこれはジハードだ、と。ここで自爆とジハードが結びつきました。 ・よく言われるのは、『コーラン』のなかに「神の道のジハードで倒れたものは死んだと思ってはならない。彼らは神のみもとで生きている」とあって、つまりジハードで死ぬと、この世が終わるのを待たずに天国へ直行できる。それで自ら進んで喜んで自爆テロをやるんだという説明が、以前から特にアメリカでされてきました。 ・ただ、やはり9・11の影響は、イスラム教徒の中でも大きいんですね。あれは、よく言われる劇場型犯罪の最たるもので、あの死に方がかっこいいと思う若者が出てきたのは、イスラム教徒の側でも否定できない事実だと思います。 ・イスラム教徒にとって理想の生き方をしたはずのムハンマドは殉教などしていませんから、本来はおかしな話なんです。 宗教と脳がわかる! 第8章 「いい死に方」ってなんですか? 解剖学者 養老孟司 「人間の致死率は一〇〇%」 養老 ・自然は人間の意識ではコントロールできません。死も自然現象の一つですから、コントロールできるはずがない。 ・日常生活に死は、 “あってはならないもの” になっている。でも、それは異常です。なにしろ人間の致死率は一〇〇%なんですから。 メディアが作りだす「原理主義」 養老 ・一神教同士はぶつかるようにできている。 ・NHKが自称する「客観報道」なんて、完全な宗教ですよ。唯一客観的な現実というのは、神様がいないかぎり成り立ちませんから。 ・「環境を守ることが絶対の正義だ」とか言うのも、一種の原理主義ですよ。 ・自分の目や耳で確認したことを信じる、というなら健全でしょう。 池上 ・生まれたときからすでにネットがあった若い人たちのなかには、検索して出てこないものはもう存在しないみたいに思う人もいますね。 養老 ・まさしく言語にない者は存在しないという世界ですね。聖書の「初めに ・だから、一次産業従事者がどんどんいなくなるんです。 ・でも日本には神道という非常に貴重な文化があって、天皇陛下が田植えや稲刈りで五穀豊穣を祈られています。 池上 ・神道では、自然というのは何が起こるかわからないから、神に祈りますね。 ・しかし、これだけ農業がなくなって都市化してしまうと、やっぱり八百万の神が成り立たなくなって、一神教のほうに行ってしまうということになるのでしょう。 養老 ・ところが、日本の国土は68%が森林ですからね。国土自体が語っている。 ・これが絶対に正しい、ということを置いておく方が、いちいち自分で判断するより面倒が少ない。それで、いつでも人間は原理主義を主張するんでしょう。 死に方と生き方は同じ 池上 ・死は生理現象に過ぎず、死体は物質に過ぎない……。 養老 ・死を考える、ということは、結局どう生きるか、ということにつながります。死に方と生き方は同じなんですよ。 ・人生に日々起きる出来事はすべて二度とはおきない。われわれ人間は日々変化している。 ・その先に、誰にも死が来る。それが自然の ■インタビューを終えて ・欧米で「無宗教」といえば、それは「アンチ・キリスト」のことであり、イスラム圏で「無宗教」といったら「反宗教」になる。 ・ところが、日本人の「無宗教)の「無」は、仏教の「無」であり、「空」でもある。日本人の体に宗教は沁み込んでいて、意識しないだけだと。 ・日本人はけっして宗教心がないわけではない。 ・養老氏曰く、「幸いなことに死んでしまえば、もうあれこれ悩む必要はありません」 『宗教は「よく死ぬ」ための予習』 ―― 完 ―― |