
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年07月18日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |
2 |
21.01 |
王権の海 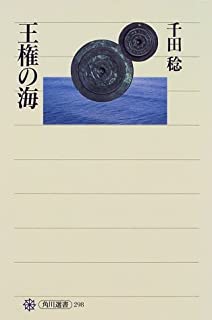 |
千田 稔 |
角川選書 |
◎ |
第一章 母なる島 海人族と大王家 大王家の出自 ・古代王権についての議論は、「はじめに大王ありき」という前提からはじまるのが常だ。 ・それは大胆な仮説によってしか越えられない文献史学の宿命のようなものだ。 ・大王家は海人族の文化とかなり深いかかわりがあるのではないか。 八十嶋祭と国生み神話 ・海人族を統括した阿曇氏の奉祭する神と住吉の神とが近しいものとして記紀に語られているので、もともと海浜の祭儀である八十嶋祭には海の神を祭る住吉社がかかわっていたとしても不自然ではないと思う。 ・大八十嶋祭は住吉の難波の浜でなされ、住吉大神とその系列の神々の守護のもとに八十嶋祭はなされたという。 南の原郷と母系原理 母への憧憬 ・国生み神話は、『日本書記』の国生み神話の「一書」に淡路島を胞とするとあることに、直接つながる。 ・つまり淡路島は王権の「母体」そのものであった。 ・それだけではない。記紀神話を貫いて大王家あるいは天皇家が語ろうとしたのは、母系の川筋を遡ることであった。 ・王権の母なる島、淡路島で天皇が狩をする記事がいくつかある。 ・魚や鳥、野獣の体内に、人間の魂が仮に宿っている期間があり、それを迎えるべき時期に狩猟を行なうというのが、古代人の考えで、そうして迎えた魂を体内に鎮めるための、歌舞をともなった動作を「あそぶ(鎮魂呪術を意味する)」ということ、そのためにこそ狩場は祭場であるとする(折口信夫氏の説)。 ・淡路島で大王が狩をしたことは、母なる島の魂にふれることであった。 ・南九州という神武誕生に関しては架空の空間が現実の舞台にひきよせられて、始祖王朝の「母体」の「胞」の伝承がつくられたのではないか。始祖王朝の誕生伝承が国生みにほかならない。 ・淡路島の津名郡一宮町に伊弉諾神宮があるが、イザナギ・イザナミに「ナギ=凪」と「ナミ=波」との意味をも含ませたものとするならば、記紀神話は日本の誕生を「海」に求めているといってよい。 ・イザナギ・イザナミは海神であることは確かなことなのだ。 第二章 日向の高千穂 南九州と記紀神話の風景 母系へのベクトル ・記紀の天孫降臨神話は霧島山とその周辺の地理的空間を具体的に認識して伝承されてきたものであり、記紀神話が現実空間から遊離したような理解からぬけでなければならない。 ・神話の地名はボロなんかをまとってはいないのだ。 ・なぜ、日向という南九州が記紀神話の風景にならなければならなかったのか。 ・それは、天孫降臨神話の祭儀性のなかから解きほぐすのがよいように思われる。 ・この神話にマトコオウフスマ(真床追衾・真床覆衾)にくるまってホノニニギが降臨することから、大嘗祭の際に造られる仮殿である ・折口信夫氏の大嘗祭論 「 ・大嘗祭の本質について折口氏は大嘗祭の原型を、天皇としての資格を得るための重要な鎮魂の行事とみなし、その過程で聖婚がなされたことを想定しているのだ。 ・新嘗祭と一体化した即位儀礼に重きをおき、農耕祭祀とのつながりとして解するとしても、松前健氏は聖婚の意味を指摘している。 ・つまり、神の聖婚は本来農耕呪術であり、大地に豊穣をもたらす聖劇であり、後世の神社の春田打ち、御田祭、田遊びなどの神事で、 ・いずれの見解をとっても、大嘗祭には聖婚のイメージがつきまとう。ここにも、天皇家の母なる系譜への憧憬が見え隠れする。 ・ホノニニギが阿多の女神をめとること、そして、『日本書記』第三の「一書」には、カムアタカシツヒメが ・このことは、阿多という地が特別の意味をもっているにちがいないのだ。阿多の地名を導くために、ホノニニギは高千穂の峯に天降らねばならなかったのだ。 第三章 海神の宮 天孫降臨以降の系譜 転換する皇祖 ・なぜ、天皇家の系譜をたどるために天孫が南九州に降りるストーリーを語らねばならなかったか。神話的世界において、天皇家の原郷は ・しかし、いうまでもなく、それは架空の空間である。伝承であろうと、みずからの遠祖の土地を地表面に即して語るには、母なる人の故郷を訪ねることによってしかなしえないのだ。神話における母系憧憬の物語はそのような次元によってこそ読みとられるべきなのだ。 海幸・山幸神話の基層 ・海幸・山幸神話のモチーフについては、ミクロネシアのパラオ島、インドネシアのケイ島、あるいはセレベス島のミナハッサなどの類話などから、隼人をインドネシア系の種族とする説があった。 ・近年においては、神話の内容においては、中国の江南地方の伝承との関係が注目されている。 ・「文身断髪、以って蛟竜の害を避く」などといった越文化に特徴的にみられる文身の風習は、百越とよばれた地域ならびに雲南省南部まで及んでいるという。 ・ ・隼人は竹細工に長じていた。 ・ベトナムには細い竹を編んだ底にヤシ油を塗った椀型の船が、また、台湾南部には竹筏があり、同様のものはビルマ・南洋群島、中国奥地の河川でもみられる。 ・この点に注目すれば隼人の原郷は東南アジアから南中国にかけての地域に求めることが可能である。 ・いま、われわれは、なつかしい浦島太郎やかぐや姫の物語のはるかな故郷をさかのぼっているのだ。 ・さらに隼人文化について、その源流を求めるとすれば、鵜飼についても見過ごすわけにはいかない。 ・鵜飼については可児弘明氏は楚の文化と関係をもった地域に広がったとし、戦国時代あるいはそれ以前に四川・雲南・広東・広西地方の文化とかかわったとしていることに注目すれば、隼人は江南地方から中国西南部にその文化的出自を見いだすことができるであろう。 ・また相撲も隼人と関係がある。この相撲も西南中国のイ族などの少数民族の農耕の予祝儀礼である ・安曇氏の神話と隼人文化の系譜をたどると、いずれも中国江南地方から西南中国に結びつく可能性が高いことが認められる。 ・つまり、安曇氏も隼人も本質的には中国南方からの渡来人とみてよく、彼らの当時の日本列島における生活様式や体制などとの社会的関係が両者の異質性をあらわしているものと考えられる。 ・安曇氏同様海人たちを率いた宗像氏について、かつて水野祐氏は、隼人と同じ種族であるという見解を示した。 ・和珥(邇)氏が海人族に出自すること、ワニが江南文化と関連することなどを考慮すれば、和珥(邇)氏に関係が深い和仁古氏も隼人の根拠地である阿多とかかわりがあったことは想定できないことではない。 ・したがって阿多という土地は、江南文化と直接かあるいはそれに近い形で結びついた土地であると考えねばならないことになり、われわれは中国(あるいは朝鮮半島経由で)―北九州とは別の伝来ルートを認める準備をしなければならないであろう。 ・安曇、隼人、宗像は(そして和邇も)その種族的な出自においてほとんど異なるところがなく、やはりこれらの集団の社会的な構成が相異したにすぎないといえよう。 第六章 ハツクニシラススメラミコト 青銅器の王朝から鏡の王朝へ オオクニヌシとオオモノヌシ ・オオクニヌシ系からアメノヒボコ集団への宗教的転換を、私は、象徴的に「青銅器の王朝」から「鏡の王朝」への変革とみようと思う。 ・崇神天皇をもって初代の大王とする立場では、神武から開化天皇までをまったくの架空としてしりぞける。 ・記紀の記事の内容についてはフィクションとしても、崇神より前に歴代の天皇をおいたことは、神武より開化までの王朝から崇神以後の王朝の交替を仮定することによって、右の矛盾を解き明かすことはできないだろうか。 ・すなわち、オオクニヌシ系の王朝からアメノヒボコ系の王朝への転換として私ととらえてはどうかと考える。 ・アメノヒボコ集団によって奈良県桜井市の巻向山一帯に王権への一歩を踏み出していくことを、『日本書記』は崇神天皇の物語として構成した。 ・記紀では神武から開化までは「オオクニヌシ王朝」を物語っているのだ。 ・当然のことながら大和に進攻したアメノヒボコ集団と、オオクニヌシ系の神々とのしこりは、すぐにはぬぐいきれたとは思われない。そのような観点から記紀の崇神伝承を読むことができる。 ・神武から開化までをオオクニヌシ系の「青銅器の王朝」とし、崇神から景行あたり(成務、仲哀までも含めてもよいが)に「鏡の王朝」の始祖伝承がこめられているのではないか。 第七章 アマテラスの誕生 皇祖神の転換過程 日神誕生 ・基層文化としてあった海人族の文化は、北から渡来したアメノヒボコ集団の海洋民的な呪具と日鏡などの信仰と結びついて、日神を皇祖神へと高めていったのであった。 伊勢神宮の創祀 ・アマテラスが、いつ伊勢の地にまつられたか。 ・伊勢神宮はアマテラスをまつる内宮とトヨウケ(豊受)大神をまつる外宮からなる。このような構造をもつにいたった年代も定かでない。 ・ただ、遷宮の儀式が持統朝に始まったことはほぼ確実なので、そのころから今日われわれがみるような神宮として整ったものと思われる。 ・『日本書記』垂仁紀二十五年三月条の記事は、アマテラスを伊勢にまつるにいたった理由をいうものである。 ・伊勢の国は常世の浪が押し寄せてくるところだから、そこは常世に近いところであるという。 ・常世は、神仙の住む世界のことであるから、遥か彼方の神仙の世界から浪が押し寄せてくるところが伊勢である。だからここに居ろうとアマテラスがいったという。 ・したがって、神宮が伊勢にまつられたのは道教的な観点から説明すべきだといわれてきたことを私は積極的に認めたい。 ・常世を意識して、伊勢神宮が国家レベルの神となってくるのは、天武天皇が律令国家の体制を整え、かつみずから道教に傾倒していく七世紀の後半ころとしてよいだろう。 東方の太陽神と王権の母系 青の香具山 ・香具山が王権にとって意味をもった時代こそ、アマテラスは王権の皇祖神としての地位を得たのだ。それは、七世紀ごろ、天武の時代がもっとも可能性が高い。 ・そのころ王権は八角形墳をつくり、道教思想を内部に取り組んでいく。伊勢の地に今日のような神宮が成立するのも、この時期あたりと考えておくのがよいと私は思う。 ・アマテラスという女神を皇祖神として伊勢にまつったのも、天武の乳母 ・(王権の海」は、母なる海であった。 ―― 完 ―― |