
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年10月04日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
23 |
21.04 |
古代天皇の誕生 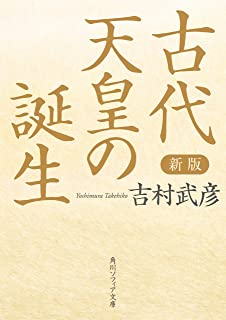 |
吉村武彦 |
角川 ソフィア文庫 |
◎ |
はじめに――天皇はどこからきたか 天皇と蕃国人の血 ・帰化人という言葉は、古代では確固とした国家なり王権なりが確立し、王化を求めて渡来してくる人びとが現われないと使えない、とされている。したがって、律令制国家の成立とほぼ同じ時期に成立したと思われる天皇号を冠した天皇家に使うことが是か非か、これも大きな問題である。 ・ただし、外国人と言うような漠然とした使い方で「帰化人」の言葉が使用されることもある。 ・律令制国家では、唐を隣国、新羅を蕃国として扱い、日本列島の夷狄である隼人と蝦夷とは明らかに区別していた。 ・平安朝以降の天皇家には蕃国人の血が流れており、この事実は疑いようがない。 第一章 倭国王の誕生とヤマト王権 二 ヤマト王権の成立 倭国とヤマト王権 王と王宮の実存性 ・宮は「みや」と読む。建物を表わす「や(屋)」に、尊称の「み(御)」を付けた言葉が宮(みや)である。「みや」は特殊な施設を意味するが、具体的には王やその一族の居住施設を「宮」という。そして、場所を表わす「こ(処)」を付した「みやこ(宮処、都)」が、宮の所在地となる。 第二章 自立する国王 二 大陸と列島の天子 冊封関係の離脱 隋の国書の文面 ・隋は、けっして倭国を対等のパートナーとは認めていなかった。 ・倭国は、隋の外交政策にもめげずに、対等の関係で外交交渉を重ねたのであった。 ・倭国の主観的な対隋対等外交は貫かれたが、東夷の倭国に対する隋の政策は変わることがなかった。 第三章 天皇の誕生 一 蕃国と夷狄の支配 海西の蕃国 半島への政治的支配と「質」 ・広開土王碑文によれば、三九一年に倭国は高句麗が臣民として扱っていた百済・新羅と外交関係を結んでいたことになる。 ・また、百済関係の史料(『三国史記』百済本紀)によれば、倭国は百済から太子を「質」として入国させていたことがわかる。 ・「質」とは、」「身代わり」の人質のことである。 ・このように倭国の軍事的勢力が朝鮮半島に渡海し、一定の地域を政治的支配下においたり、軍事的支配権を振りかざしていたのである。とりわけこの時期は百済に対して、太子を「質」とするような外交関係を保持していた。 ・『三国史記』は一二世紀半ばに成立した朝鮮の史書であるが、そこに「質」とみえる。『書紀』による、日本側の意図的な記述ではない。 ・しかも、倭国と百済の関係では『書紀』に「質」と記されたものを含め、相方向ではなく、百済から倭国への一方的な派遣である。 ・こうした状況をみれば、百済からの人質とひきかえに、倭国は百済に対して軍事的救援を行っていた可能性がある。 ・『書紀』は、第一章第二節の「初期ヤマト王権の展開」のなかに「応神天皇の物語」の項を立てた。 ・応神が神功皇后の胎中で、「三韓」を征討する物語である。 ・この虚構の物語の前提として、朝鮮半島に対する軍事的支配が存在したことはまちがいなかろう。 ・この事実は、倭の五王が中国の宋に要請した称号に、たとえば珍の場合「 加耶と「任那問題」 ・古代朝鮮の三韓のうち、馬韓(百済が統一)・辰韓(新羅が統一)諸国と異なり、諸国が分立して統一国家が形成されなかった半島南部の旧弁韓諸国の総称が加耶である。 ・『書紀』では任那と呼び、「日本府」が設置されたことになっている。戦前の皇国史観のもとで、誤って「植民地経営」の元祖のように扱われた。 ・「任那」の名称は『宋書』倭国伝などの中国史料にもでており、蔑称のような語ではない。 ・「任那日本府」を、倭国が加耶に対して直接経営を行なったとする見解は誤っている。 ・第一に「日本」の国号は、七〇一年の大宝令で法的に定まるので、『書紀』に書かれた時期には「日本」はまだ存在しない。したがって、「日本府」の語は「日本」の国号ができた後の時期の潤色をうけている。当時、何らかの名称があったとしても、「倭府」のようにしか表記できないだろう。 二 内外の戦争と蕃国への干渉 壬申の乱 王位継承と不改常典の法 ・王位継承には二つの面がある。一つは、即位している王とどのような血縁関係にある人物が後継者に選ばれるかという候補者の問題、もう一つはどのような手続きを経て選出されるかという手続き問題である。 「大君は神にしいませば」 ・『古事記』も『日本書紀』も巻首は神代である。神代から「天皇の代」に移ることは、「人の代」になったことを意味した。その「人の時代」の天皇を神とよぶには、何らかの理由がなければならない。 ・壬申の乱後に天皇神格化が強まったとする見解が、有力である。 ・この歴史的事実を承認することが歴史認識の第一歩となる。 ・ここでは、壬申の乱を戦い抜いて勝利した天武天皇から神格化がはじまったことを確認したい。 三 天皇号の誕生 律令法の成立と君主号 「近江令」の存否 ・六七〇年(天智九年)に、全国的な戸籍である庚午年籍が作成された。 ・全国的に戸籍が造られたということは、各地域で国・評(後の郡)という行政機構が整い、これらの行政組織が戸籍を作成する政治的能力を保有していたことを意味する。 ・天皇号と同じように、皇后の称号が定まったのも浄御原令である。 律令制支配 ・七〇〇年(文武四年)三月には大宝令の選定が終わり、大宝律の準備に入った。翌七〇一年(大宝元年)には大宝律の選定も終了し、次の七〇二年には律令とも全国的に実施された。 ・ここに、日本の国は律と令がともに備わった法治国家に成長したのである。 天皇号の成立 中国における「天皇」の語 ・天皇の称号と道教思想との関連は強いものがある。 ・道教のなかでもっとも重視された天皇大帝は、六世紀後半まで宇宙の最高神としての位置をしめた、という。 ・この天皇の語が日本に入ったのである。 ・法制語としての天皇は、「スメラミコト」と読んだようである。 ・その意味は、「スメラ」は「最高の主権者」、「ミコト」は「行為者の敬語」だという。 ・「天皇」という漢語に、倭国で遣われていた最高主権者の名称をあてはめた用字であろう。 おわりに 「日本の国号」 ・天武朝ないし天智朝に出現した「天皇」の称号は、六八九年(持統三年)に施行された浄御原令で法制化された。 ・日本の国号は、天皇の称号よりさらに一〇年あまり遅く、七〇一年(大宝元年)に完成した大宝律令で規定された。 ・日本の国と国王の称号の成立を、歴史の流れに位置づけてみると、浄御原令の成立とともに天皇号が定まり、大宝律令の制定時に日本の国号が決まったことになる。 ・多少の時間的な差はあるものの、天皇号・律令・日本の国号は、ほぼ一体として成立したことになる。 ・総括的にいえば、日本の古代国家は天皇制に基づく律令制国家として確立した。 ―― 完 ―― |