
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年09月19日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
25 |
21.05 |
日の丸・君が代の戦後史 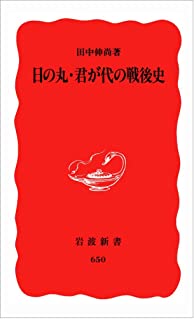 |
田中伸尚 |
岩波新書 |
〇 |
第1章 占領下の「日の丸」「君が代」 ―― 一九四五~一九四九 ―― 1 「日の丸」への曖昧さ 掲揚解禁と冷戦の進行 ・占領時代の「日の丸」掲揚が完全に自由になるのは、一九四九年一月一日からだった。それは元日付でマッカーサーの「年頭メッセージ」の形で公表された。 「余はここに諸君にたいし諸君の国旗をふたたび国内において無制限に使用し、掲揚することを許可する。余が今回この挙に出た理由は一にこの国旗が人類のひとしく探し求めてきた正義と、自由の不易の観念に立脚した平和の象徴として、とこしえに世界の前にひるがえらんことを。・・・さらにまた、〔この国旗が〕日本の政治的自由を確保し、保全するに足る日本経済建設の義務に向って、日本国民の一人一人をふるいたたせる輝く導きの光としてひるがえらんことを心から念願するからにほかならない」 ・マッカーサーは憲法施行の際の書簡と同じように「平和に本」のシンボルとしての「日の丸」を強調し、さらにナショナリズムのシンボルにも位置づけている。 【私見 : 著者はこのフレーズをちゃんと読んでいるのだろうか。蓋し、正論だと思うのだが】 第三章 押し出された「日の丸」「君が代」 ―― 一九五八~一九六八 ―― 1 学習指導要領への登場 義務教育の現場へ ・(学習指導要領で)近代日本の歴史認識と天皇観が刻み込まれた「日の丸」「君が代」を、参加者が従うことを拒みにくい儀式という「支配の空間」に持ちこむことそれ自体が強制であった。 【私見 : 著者の先入観と偏見に基づく表現。】 世論はどう見たか ・「日の丸」「君が代」の果たした戦争責任・・・。 【私見 : 無機的なものに責任を負わせて、評している人間は善意の第三者に見える】 第四章 強制と抵抗の狭間で ―― 一九六九~一九八一 ―― 2 法制化と処分のはじまり 田中首相の法制化発言 ・奥野文部大臣の発言 「自国の国旗などを尊重しない人間が他国の国旗などを尊重することができるだろうか」 「他国の国旗を尊重できない人間が、他国から尊重されるだろうか」 【私見 : ごく当然の発言】 初めての処分 ・現在まで三〇年にもわたって教職員への処分がつづき、被処分者数は一〇〇〇名をはるかに超えている。 ・それは、何とか「日の丸」「君が代」を学校現場に定着させて、かつてのような上からの命には服従する「国民」づくりを目ざす国家の側の執念と、少数とはいえ繰り返してはならないという思いを持った人びとの必死の異議申し立ての狭間でおきている戦後史の実相でもある。 【私見 : 他の多数の教師が肯定していることにはどう答えるのか。少数意見と認識しているのならば、多数に従うしかないのではないか。反対運動は教育現場以外でやって欲しい。】 校長自殺の悲劇 ・「日の丸」「君が代」が学校現場に持ちこまれなかったら、起きなかった悲劇であるのは間違いない。 【私見 : 犯人は反対運動をした人たちであることを全く認識していない。本末転倒である。最近の子どもの自殺の対応に似ている。】 第五章 裏切られた沖縄 ―― 一九八二~一九八八 ―― 2 抵抗と復帰のシンボル 自由と抵抗のシンボル ・教育は日本の植民地支配・侵略戦争を支える子どもたちを「臣民」としてつくっていった巨大な装置として機能し、教師たちはそれを支えた。その総括をほとんどなされないまま、戦後民主主義を謳い出していた。 【私見 : 日教組はどう総括しているのか知りたい。】 教職員会の「日の丸」購入運動 ・祖国から分離されたことがかえって教職員の復帰悲願となり、祖国復帰運動に国旗掲揚運動を取り入れることにつながった。 ・沖縄をアメリカの支配から解放し、「祖国日本」へという復帰運動がきわめて強い民族主義的色合いを持っていた以上、「日の丸」を積極的に選んだのは必然だった。 【私見 : 日の丸には、その時々、人々によって解釈がいろいろあることを著者も分かっているではないか。ならば、日の丸を一つの定義に押し込んで悪者扱いにするのはおかしい。】 第六章 義務化と抵抗 ―― 一九八九~一九九八 ―― 1 新指導要領での義務化 教育課程審議会の最終答申 ・臨教審の最終答申(第四次、八七年八月) 「日本人として、国を愛する心をもつとともに、狭い自国の利害のみで物事を判断するのではなく、広い国際的、人類的視野の中で人格形成を目指すという基本に立つ必要がある。なお、これに関連して、国旗・国歌のもつ意味を理解し尊重する心を養うことが重要であり、学校教育上適正な取扱いがなされるべきである」 ・国旗や国歌という人為的な装置によって無理やりつくられる愛国心は、「強ばった」偏狭な、排他的な精神を生みだし、「国際人」とは反対の方向へ向かう。 【私見 : 理解不能、意味不明】 ・第三次答申 「人間関係の基礎としての社交能力が体得されなければならない。例えば、海外にあっては、その国の国旗、国家等に対して敬意を払うなど国際的に常識とされている基本的マナーを身に付け、現地の文化や習慣を尊重する謙虚さを失わないようにするなど、子どものしつけに対する家庭、学校における配慮が必要である」 「君」は象徴天皇 ・「日の丸」「君が代」の強引な押しつけは、何より人びとの思想・良心の自由、さらに表現の自由に深く侵襲する。 【私見 : 反対派の意見としては理解できるが、国民の大勢が認めるなかでは、押しつけということにはならないのではないかと思う】 ・しかし戦後社会は、戦前・戦中とはちがって容易には公権力などに包摂されない「 ・それが「日の丸」「君が代」強制化の中で、地域や規制の組織を越えたところで、試行錯誤を重ねかつ悲しみさえ抱えながらも鮮やかなオブジェクション(異議申し立て)のたたかいを創造してきた。 3 「日の丸」「君が代」のない街――国立市民のとりくみ 市民の歴史意識 ・市内の各学校長に出した「日の丸」「君が代」の強制に反対する要望書類やアピール 『かつて「日の丸」「君が代」が、どんな「日本人としての自覚」を促してきたか、……他国を、他民族を侵略し、占領し、土足で踏みつけて恥じない、いや、それどころか、そうすることが「お国のため」「天皇陛下のため」と信じて疑わない大日本帝国の臣民が、「日の丸」「君が代」によって作り出されてきたのではなかったのでしょうか』 【私見 : 部分を切り取って、それがあたかも日本人の全体のような言い回しには不賛同。純粋に国のために戦った人は沢山いる。】 『教育の場に、「日の丸」「君が代」が問答無用とばかりに強調することは、教育の理念に著しく反するものと言わなければなりません。……自由と人権をないがしろにして、日本人としての自覚を植えつける教育とは、戦前の「少国民」教育とどこが違うのでしょうか』 (「一九九〇年三月三日、子どもたちのための卒業式・入学式を!集会アピール」より) 【私見 : 自由と人権を偏重しすぎ、年端のいかない自我も未確立、判断力も出来上がっていない教育途中の子どもたちに、自由と人権をそれこそ押しつけたために教育は荒廃し、子どもたちは突然与えられた自由に判断責任を負わされ、精神的に不安と孤独を抱えてしまうことになってしまった。子どもには、成長に応じた応分の自由を与えればよく、他の責任(自由に伴って生じる責任)は大人が持ってあげるべき。】 第七章 法制化へ ―― 一九九九年 ―― 3 論議の中で明らかになったこと 精神的自由と強制 ・国家には、憲法上、宗教的中立性が求められているが、実は、信条的中立性も同様に要請されている。したがって「日の丸」「君が代」を学校現場に持ちこむこと自体が、この中立性を侵していることになるのである。 【私見 : 「日の丸」「君が代」を学校現場に持ちこむことと中立性に何の関係があるのか】 ―― 完 ―― |