
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年11月21日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
31 |
21.06 |
官僚のレトリック 霞が関改革はなぜ迷走するのか 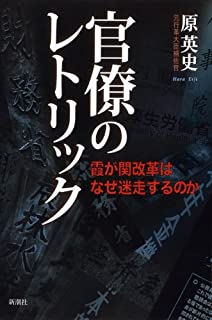 |
原 英史 |
新潮社 |
◎ |
第一章 「脱官僚」とは何か 政治家と官僚の "倒錯関係" ・「官僚主導」システムを基底で支えてきたものは何か。 ・正体は、日本社会に長く息づく、「官僚こそが国益のために働く存在」という社会通念だ。 ・最近になって揺らいでいるものの、依然として根強く残る、明治以来の伝統的教義と言ってもよい。 「官僚主導」はなぜ正すべきか ・「かつての官僚は国益のために働く立派な人が多かった。最近の官僚はダメになってきた。だから、今度は政治家に任せてみよう」ということではない。 ・そんな見方では、本質を見誤る。将来、政治家の側が失点を重ねたとき、再び「官僚主導」への揺り戻しが起こることにもなろう。 ・本質的な答えは、政治家は国民の選挙で選べるが、官僚は選べない、ということだ。 ・政治家が誤った方向に進みそうなときは、国民が正せる。しかし、官僚が主導権を握って暴走したとき、国民に正す手立てはない。 ・そして最大の問題は、「官僚主導」が、単なる「現象」の域を超えて、「制度」に昇華していることだ。 ・単に「現象」として、本来は「上司」である大臣より「部下」の官僚が主導権を握るという程度なら、民間企業でもどこの組織でも、よくある類の話だろう。 ・たまたま「上司」が頼りないとき、「部下」が奮起しないようでは、むしろ組織が危うい。逆に、「部下」がおかしな方向に暴走を始めた時は、自ずと天秤の重りが動き、「上司」が主導権を取り戻すはずだ。 ・ところが、「部下主導」が「制度」化されてしまったのが、「官僚主導」システムだ。 ・例えば、国家公務員法には「公務員の身分保障」という規定がある。公務員は、特段の自由がない限り、免職や降格はできないという制度だ。 ・なぜこんな制度が設けられたかというと、「政治家は、政治的意図で公務員を免職・降格して、息のかかった人物を登用したりしかねないから」だ。 ・つまり、「上司(政治家)は暴走する」という前提で、「上司(政治家)が「部下(官僚)」に手を出せないよう、防波堤が作られているのだ。 ・身分保障の歯止めがあるとはいえ、官僚の人事権は本来大臣が持っている。ところが、霞が関には長らく、「官僚の人事に大臣は介入しない」という不思議な不文律があった。だから、稀にこれを破る大臣がいると騒ぎになったのだ。 ・こうした様々な「制度」によって、「暴走する上司(政治家)」から「国益のために働く部下(官僚)」が守られ、官僚の世界が "聖域" 化されてきた。 "聖域" 化されているからこそ、官僚は、政策立案プロセスにおいても、こころおきなく主導権を発揮した。 ・そして、だからこそ、官僚が国益を離れて動き始めてしまった時、手が付けられないことになってしまったのだ。 ・戦うべき本当の相手は何なのか、「脱官僚」の本質は何なのか。 ・「官僚主導」の個々の現象面で、つまり、さまざまな政策決定の局面において、主導権を奪うことも、たしかに必要だ。しかし、局地戦を戦うだけでは、問題の根本的解決にはならない。 ・戦うべき本当の相手は、官僚の世界を "聖域" 化している諸制度、つまり公務員の人事や組織に関わる、広い意味での公務員制度だ。 ・そして、「脱官僚」によって何が実現するのか。官僚を貶めることではない。政治家の権威を高めることでもない。 ・「脱官僚」の本質は、政治家も官僚も国益のために尽くす、より良い政府を作ることだ。 第三章 自民党はなぜ公務員制度改革に敗北したのか 2 福田内閣での思わぬ前進 第二の急所「労働基本権」へ ・公務員の労働基本権が制約されていることは、広く知られる。 ・歴史的には、GHQ(連合国最高司令官総司令部)の占領政策の下、いったんは民主化の一環として従来の官吏にも労働基本権を付与。ところが、その後、労働運動の激化を背景に、再びGHQ指導により、公務員の労働基本権は大きく制約された。 ・そもそも、労働基本権とは、 ①団結権(労働組合を作って加入する権利) ②団体交渉権(使用者と労働条件について団体交渉を行う権利。その一部として、協約を締結する権利、いわゆる協約締結権も含まれる) ③争議権(いわゆるスト権) の三権だが、国家公務員や地方公務員の場合は、国家公務員法と地方公務員法により、一部制約される。 ・制約が正当化される実質的根拠 ◉公務員の職務には公共性があり、争議行為などがなされれば国民生活に重大な支障をもたらす。 ◉公務員の場合、市場の機能が作用する余地がなく、争議をすれば一方的に強力な圧力となる。 ◉(給与水準の決定は予算措置に直結するので)財政民主主義の下、国会審議により決定する必要がある。 「制約」で誰が得しているのか ・労働基本権の問題はまず、誰が「拡大」を求め、誰が「制約の維持」を望んでいるのかを理解しないと、議論の構図が分からなくなる。 ・底流として理解しておかないといけないのは、「労働基本権の ・考えてみれば、公務員は権利が制約されているからといって、劣悪な労働条件に苦しんでいるとの話はあまり聞かないだろう。なぜかというと、「労働基本権の制約」という、民間とは違う特殊事情があることを理由に、民間とは違う特殊な公務員制度が用意され、十二分と言ってよいほどに保護されているからだ。 ・代償措置として設けられているのが、人事院の勧告制度だ。 ・公務員は、労使交渉やストライキを通じて自らの労働条件を決めることができない。だから代わりに、使用者とは一線を画した中立機関たる人事院を設け、人事院が民間の給与水準を調査して適正水準を勧告する。そして、人事院勧告を参考にして、内閣と国会が給与水準を定める仕組みだ。 ・本来、内閣と国家は、人事院勧告をあくまで ・こうして、公務員は自力で労使交渉をすることなく、民間企業の労働者たちが交渉で勝ち得た成果にただ乗りできる仕組みになっている。 ・しかし、もし公務員が、民間同様に労使交渉で給与を決める仕組だったらどうだろう。とりわけ現在のように、公務員に対する国民の厳しい目がある中では、民間並みに待遇改善要求を押し通すことは難しい。かなり厳しい交渉結果に追い込まれる可能性が高いだろう。 ・また、民間の給与水準の調査というのが甚だ怪しい。一定規模以上の企業を対象としており、零細企業は対象に含まれていないし、当然ながら、業績不振で倒産する企業は調査対象から抜けていくわけだから、民間の文字通りの実態よりは高い水準が示される。 ・結局、現行制度は、労働者としての公務員にとって、とても 甘利 vs. 谷バトルの真相は "内閣人事局の空洞化" ・霞が関の幹部と公務員労組は、現行の公務員制度を抜本的に変えたくないという点で利害が一致する。そして、彼らの隠れみのとなってきたのが人事院だ。 ・だとすれば、公務員労組を有力支持母体とする民主党の議員が、(人事院の主張に沿って) "内閣人事局の空洞化" を是とし、公務員制度の抜本改革阻止に手を貸そうとすることは、何ら不思議な話でないのかもしれない。 ・人事院の掲げた、「中立・公正」と「労働基本権の制約」という二つの論拠は、どちらも、公務員制度という聖域を守るうえでの最終へ行きとも言うべきものだった。 「官尊政卑」と「官は民と違う」論の連結 ・これは、「役所は、民間企業とは全く異質であり、民間の経営手法など全く参考にならない」というものだ。実は、この二つの考え方(あるいは思い込み)は根底でつながっている。 ・役所も民間企業も、トップの責任者がいて、従業員を率い運営する組織であることに変わりはない。ところが、「官尊政卑」論に拠って立つと、一つだけ大きな違いがある。つまり、役所の場合、トップに戴く政治家は「私利私益」(あるいは、せいぜい、地元利権などの特定の利益)のために働き、部下の官僚は「国益」のために働く。そうした特殊な組織であるがゆえ、民間企業のようにトップに権限を集中させたりはできないし、人事制度もトップが部下の人事に介入できない仕掛けが必要……、となっていくわけだ。 第四章 民主党の "裏切り" で早くも風化する「脱官僚」 重要課題はことごとく先送り ・結論としては、麻生内閣と比べて、何ら進歩はなく、むしろ、部分的には大きく後退さえしている。 ・結局、「財務省は敵に回せない」などと言って自民党守旧派同様の "官僚への配慮" を続け、加えて、"公務員労組への配慮"まで行い始めた結果、自民党政権時代よりも、状況ははるかに悪化してしまったように見える。 第五章 「脱官僚」実現のための五箇条 ・第一に、官僚を使いこなす前に、まず官僚を選べ ・第二に、閣議を "お習字大会" から討議の場にせよ ・・・・・・閣僚は「各省の代弁者」より「内閣の一員」たれ ・第三に、「人事院」と「身分保障」を廃止し、「官僚は特別」論を駆逐せよ ・・・・・・「官僚主導」の根源である公務員制度を抜本改革せよ ・「官僚主導」の根源が、官僚の世界を聖域化する公務員制度である。その抜本改革に手をつけない限り、「官僚主導」の根を絶つことはできない。 ・では、公務員制度をどう変えたらよいのか。 ・「官は民とは異質」という論理と、「官僚は政治家と違って中立・公正」という論理が根底でつながって、特殊な公務員制度を正当化してきた。どちらも「官僚は特別」という話だ。 ・この「官僚は特別」論を排し、「民間並みの人事制度」に変えてしまえばよい。 ・そして、「民間並みの人事制度」に変える上で、象徴的なハードルが、「人事院」と「身分保障」だ。これらが廃止できず、部分的にでも残ってしまえば、その限りで民間並みにはならない。 ・「人事院」については、公務員の「労働基本権の制約」を解除することが鍵だ。制約されている協約締結権と争議権を両方とも付与し、その代わり「人事院」を廃止すればよい。 ・鳩山内閣は、二〇一〇年二月、「政治主導確立法案」と「国家公務員法等改正案」を国会提出したが、「労働基本権の拡大」は先送りした。これは解せない。 ・労働基本権については、議論はもう尽くされているので、早く決めて法案化すればよかったのだ。 ・「労働基本権の議論が継続中」という言い訳で、「人事院」を温存し、特殊な公務員制度を守り続ける手助けをするというのでは、民主党という党のお里が知れる。 ・結局、公務員制度を抜本改革したくない人たちの言いなりになっているということだ。 ・また、「身分保障」については、「まずは幹部に限って先行的に廃止すべき」と記したが、最終的には、すべての公務員について廃止すべきだ。 ・もともと「身分保障」がなぜ設けられたかという歴史的経緯に立ち返ると、明治期の第一次大隈重信内閣で、当時の政党政治家たちが、政党人を役所のポストに就けたいとの政治的意図だけから、官僚たちをポストから外し、免職や休職にしたことだ。 ・しかし、そのために、現時点で「身分保障」が必要だろうか。 ・一般職公務員の場合、こうした事態に対し、もっと合理的な、別の形の歯止めが既に設けられている。「能力・実績主義」だ。 ・一般職公務員の人事は、能力・実績の評価結果に基づいてのみ行うとの原則が、安倍内閣で改正された国家公務員法で定められている。 ・当然ながら、政治的意図に基づく人事も許されないのだ。 ・つまり、「能力・実績主義」の原則が定められた今日、もはや「身分保障」は不要だ。 ・当初の必要性が既に失われたにもかかわらず、「身分保障」を維持することは、単なる惰性に過ぎず、いわれなく官僚機構を "聖域" として続けることにほかならない。 ・よって、「人事院」と「身分保障」の廃止が重要だ。これを実現できるかどうかが鍵となる。 ・第四に、改革の戦術論は、過去の成功と失敗に学べ ・・・・・・全体像を描きつつ、同時に、急所の改革を先行実施せよ ・・・・・・「プロセスの公開」を武器とせよ ・改革に対して、よくある抵抗テクニックは、「全体像が描けないと、個別論を進められない」という「先送り」戦術だ。 ・天下り規制の論議の際には、「定年延長など改革の全体パッケージを議論しないで、天下り規制だけ先行するわけにはいかない」という議論があった。 ・もう一つ「トカゲの尻尾切り」戦術というのもある。 ・独立行政法人改革のとき、ムダ遣いの象徴として雇用・能力開発機構の「私のしごと館」が問題になった。 ・まさに「トカゲ尻尾切り」で、ごく一部の個別論だけで逃げ切られてしまったのだ。 ・療法を回避する戦術が、「全体像を描きつつ、同時に、急所の改革を先行実施」だ。 ・「脱官僚」のための改革であれば、急所は「幹部の人事制度改革」や「労働基本権の拡大」だ。これらを変えれば、「官僚主導」を一気に廃し旧来の制度を改める突破口になる。 ・一方、全体像としては、優秀な人材の確保・育成策なども含めた、抜本的な公務員制度改革、さらに、霞が関官僚の地方支配を打破する地域主義的改革、官製資本主義を打破する規制改革なども視野に入れて、設計図を描くことが必要になる。 ・強い抵抗が予想される改革を進めるとき、最も有効な武器は、議論のプロセスの公開だ。 ・鳩山内閣でも、事業仕分けまではよかったが、その後の二〇一〇年度予算編成プロセスでは、大事なことは密室で決められた印象だ。 ・各省で開催される民間有識者会議などは非公開とされるものが散見されるなど、むしろ自民党政権時代より公開度が低下しているように思われる面もある。 ・「官僚主導から政治主導へ」の転換は、国民が監視できてこそ意味がある。 ・「密室の官僚主導」から「密室の政治主導」への転換であれば、意味はない。それどころか、むしろ危険かもしれない。 ・というのは、かつての「密室の政治主導」では、官僚と族議員という二種類のプレイヤーが関わり、曲りなりにも相互抑制機能が働いていた。 ・ところが、「密室の政治主導」では、プレイヤーがより限定的になるため、何の抑制も働かない可能性が出てくるのだ。 ・第五に、「脱官僚」に足る政治家を揃えよ ・そもそも、「官僚主導」の肥大化はなぜ起きたのだろう。 ・最大の要因は、多くの政治家が、選挙に当選して自らの職を護ることに汲々とし、政策は二の次で、国家運営の責任をとろうともしなかったことだ。 ・ ・かつての公務員制度改革をめぐる論議で、「改革をやったら、優秀な官僚が集まらなくなる」という主張があったが、「官僚の質」よりよほど深刻なのが「政治家の質」だ。 ・当時、「優秀な官僚」論を主張した国会議員には、そんな暇があったら「政治家の質」向上を考えてほしかった。 ・この問題を解決しない限り、いかに「脱官僚」の掛け声をかけても、諸制度・慣行を直しても、結局は元の黙阿弥になるだけだ。 ・民主党政権が「政治家の質」の向上に真剣に取り組もうとしているのかは、残念ながら疑問だ。 ・民主党幹部が、当選一回の議員らに「選挙最優先」を指示し、事業仕分けから外したりした様を目にするにつけ、逆を向いているように思われてならない。 ・民主党が、「 "国家のこと" より "自分の選挙" を優先する国会議員」を育てる方針ならば、そんな政党に「脱官僚」を目指してほしくない。 ・「脱官僚」の結果、頭の中は選挙戦術のことばかりの政治家がたちが、「政治主導」と称して政策を決めるようになるなら、国民にとっては悪夢だ。 ・そういう政党や議員たちには、「官僚主導」の方がお似合いなのだ。 ・「政治主導」が「官僚主導」に優る拠り所は、「政治主導だったら、最後は、国民が審判できる」ということだ。だから、「脱官僚」「政治主導」は、当面、前に進めたらよいと思う。あとは国民の審判だ。 ―― 完 ―― |