
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年11月22日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
32 |
21.06 |
日本の難点 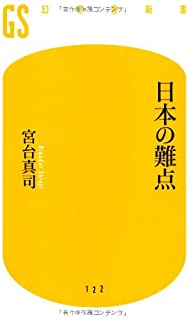 |
宮台真司 |
幻冬舎新書 |
◎ |
第一章 人間関係はどうなるのか ――コミュニケーション論・メディア論 社会情勢の変化はライフスタイルをどう変えたのか ・国家(行政)は「個人の自立」を支援するのではなく、「社会の自立」を支援するべきなのです。 ・言い換えると、国は、社会がそれなりに自立して回るように助ける役割に徹するべきです。 ・欧州の政策的な共通了解になっています。 ・安全保障について僕の持論を言えば、「軽武装・対米依存」から「重武装・対米中立」へとシフトすべきです。 ・重武装とは、対地攻撃能力を中核とした反撃能力による攻撃抑止能力を備えることです。それには専守防衛の憲法九条を変える必要があります。これは平和主義に反するでしょうか。 【私見 : 意見には賛成だが、実現可能性如何】 ・平和主義を守るために重武装化が必要であり、そのために憲法改正が必要であるならば憲法を変えるべきです。 【私見 : 改憲反対論者、非武装中立論者や、武器を持たず無抵抗で平和が手に入ると思っている輩には分かるまい。】 ・アジア諸国を感情的に包摂し、憲法改正による重武装化を成し遂げ、米国への負い目から自由になって、軍事・資源・食糧・技術・文化の包括的な安全保障戦略を、日本が自立して考えられるようになること。それなくして、実は社会的包摂性の回復や、 ‹生活世界› の回復はあり得ません。 第二章 教育をどうするのか ――若者論・教育論 モンスターペアレンツやクレーマー対策とは ・クレーマーやモンスターペアレンツの言うことを真に受けて聞くメカニズムがあるから、彼らが生き残ってしまうのです。 ・むろん、正当ではないクレームにもチャンスを与えることは「ガス抜き」として有効だから、チャンスはどんどん与えておきましょう。 ・でも、クレーマーの言い分を聞いてあげることと、言い分を真に受けることは、別の問題です。 ・門前払いはマズイですが、クレーマーが主張する「部分的最適化」を上回る全体に関わる合理性があるならばそれを一通り説明し、「なので、クレームはお受けできません」と言うしかありません。 ・クレームや実況や批判は、いわゆる世論とは何の関係もないことを肝に銘じよ。 モンスターペアレンツ保険は仕方がないか ・地域社会に ‹生活世界› を回復させる、そして、そのことでモンスターペアレンツを地域が許さなくするような施策が、絶対に必要になります。 第三章 「幸福」とは、どういうことなのか ――幸福論 日本人にもわかる「宗教」とは ・ユダヤ教とキリスト教とイスラム教は「同じ神」を信仰する。 ・どれも旧約聖書を聖典として数えます。 ・キリスト教では新約聖書が、イスラム教ではコーランが加わるだけです。 第四章 アメリカはどうなっているのか ――米国論 アメリカに守ってもらうために、対米追従は仕方がないのか ・日本は上陸してきた敵兵をやっつけるために有効だという理由で、大量のクラスター爆弾を保有してきました。 ・本土で激烈な地上戦を戦う時点で、すでに戦争は負けです。この時点から戦況を挽回することは不可能なのです。 【私見 : そう決めつけられるものか?】 ・なのに、なぜ日本は負け戦の地上戦に供える必要があるのか。答え。専守防衛を掲げているからです。なぜ専守防衛を掲げるか。交戦権を禁じる憲法九条があるからです。 ・専守防衛思想とは「軽武装×対米依存」図式です。いざとなったら米国を頼る思考です。頼れるかどうかが問題です。 ・日米安保条約は日本が攻撃された場合の出撃義務を規定していません。加えて、中国の重要性が高まった今日の米国が、日中の戦闘が始まったからといって中国を攻撃するとは到底思えません。 ・僕の持論は昔から「米国を敵に回す必要はもとよりないが『重武装×対米中立』を目指せ」というものです。 ・「重武装×対米中立」化には、最低でも三つの障害を克服する必要があります。 ・第一は、米国の機嫌を損なわないようにするためにどうするか。 ・第二は、アジア諸国の疑惑や懸念をどう除去するか。 ・第三は、憲法改正に必要な国民意思や、重武装を制御する頭脳(民度)をどう形成するかです。 ・また、「重武装×対米中立」化の目的は、安全保障の強化です。 ・安全保障とは、軍事の安全保障以外に、資源やエネルギーの安全保障、技術の安全保障、食糧の安全保障、文化の安全保障を含んだ、総合パッケージです。 どうして、日本の政治はダメになったのか ・日本では英国流の議院内閣制の本義が全く貫徹していません。それは、官僚内閣制になっているからです。 ・「官僚内閣制」というのは、国民が国会(議院)を通じて内閣を操縦する議院内閣制の本義が機能せず、官僚が国会(議院)を通じて内閣を操縦する形になっていることをいいます。 ・内閣を操縦する国会が、国民によってではなく官僚によって操縦される。官僚が国民の役割を代替しているわけです。 第五章 日本をどうするのか ――日本論 日本の農業、自給率は大丈夫か ・農水省によれば、一九六〇年に六〇六万戸だった農家は、二〇〇五年に二八五万戸つまり半分以下に減りました。 ・二八五万戸のうち、主業農家でなおかつ六五歳未満の農業専従者がおり農業所得が過半に及ぶ「農家らしい農家」はたった三七万戸。残りは農業を営まない「土地持ち非農家」、農業外所得が過半の「片手間農家」、そして「高齢農家」です。 ・こうした農業の空洞化は、農地の「転用収入」を目的として農地法を踏みにじってきたことに由来します。 ・農地が、税制上低コストで保有でき、公共事業で価格が上がった際に高額で売却可能な「錬金術の道具」になってしまった結果、平地の優良な農地でも耕作放棄地が増えています。 ・しかも有力な集票装置である農協の「農家らしい農家」でなく「土地持ち非農家」「片手間農家」「高齢農家」の利益だけを代表します。理由は、 (1)米作が農業生産額に占める割合が二二%に落ちたこと、 (2)販売力のない小農が農協に依存すること、 (3)ホームセンターより高い肥料や農機を売ること、 などです。 ・農協は、肥料・農薬・農機の販売や収穫物の買い取りなど経済事業では収益が上がらないので、農林中央金庫など金融事業に傾斜していて、もはや、いかなる意味でも日本の農家全体の利益を代表しているとは言えません。それでも巨大集票装置なので、理不尽な農業政策を推進させる単なる利権屋になっています。 ・愚作の象徴が七七八%のコメ関税です。 ・国際市場でのコメの価格上昇でかつて一〇倍以上開きがあった中国米との価格差は今や一・五倍に縮小、関税を約七割の関税削減が義務づけられている七五%の線(WTO案)よりも下に引き下げても輸入米と十分競争していける現状があります。それなのに高関税を維持する必要は全くありません。 ・米の価格維持のための減反政策で水田の四割を減らしながら、大量のコメを義務的に輸入することはどう考えてもバカげています。 ・関税維持の代償にミニマムアクセスを受け入れるよりも競争原理を受け入れた方が、コメ輸入量が増えないばかりか、将来的にはコメの輸出さえ可能になる。 ・農協のいいなりである政府の主張は、関税引き下げを行えば、苦境にある日本のコメ農家が大打撃を受けるというものです。しかし、米国やEUが農家への直接支払いで国内農業を保護する政策にとっくに転換した中、関税で国内市場を保護する日本の政策は、代償を考えれば不合理そのものでしょう。 ・なぜ農協がこうした国際的な保護政策の流れに反対するかといえば、農家への直接支払いを世論に継続して納得してもらうには、「農家らしい農家」への支払いが優位になるしかないからです。農協が「農家らしい農家」の利益をまったく代表していない以上、それでは農協に不利益になってしまいます。 ・日本の農業政策は、農業を守るというより、農協(が代表する「農家らしくない農家」)を守る政策にすり替わっています。 ・「農家らしい農家」ないしそれに協力する人たちに、政府が直接支払する補助金政策へと、転換する必要があります。 ・「国土保全」をキーワードにして、農業政策(農水省)、環境政策(環境省)、道路政策(国交省)、分権化政策(総務省)、内需化政策(経産省)を横断的に連携させることが、可能かつ必要だ。 ―― 完 ―― |