
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年06月27日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
34 |
21/06 |
いつ死なせるか ハーマン病院倫理委員会の六ヵ月 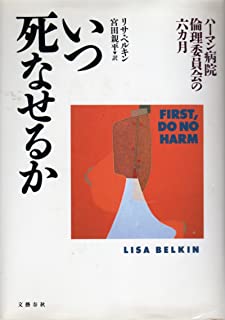 |
リサ・ベルキン |
文藝春秋 |
◎ |
委員会 ・医療倫理に関するほとんどあらゆる問題は、医療の目的はなにかというただ一つの疑問に集約されている。 ・その答えは単純で、患者をより健康にすること、もしくは少なくとも生活から楽しみを引き出せるようにしてあげることだ。この答えに合わない、ただ死を遅らせて悲惨な生を延長するだけの医療、委員会の役割はこうした無駄をやめることにある。 訳者あとがき 宮田親平 ・「末期医療」、この問題を生んだ原因はひとえに医学の急速な進歩ある。 ・とくに心肺蘇生術をはじめとする幾多の技術革新による延命治療法の出現が、生命の終りをあいまいにしたことにより、生の量的延長だけが医学の目的かという疑問が生まれた。 ・そこでいまや「クォリティ・オブ・ライフ」が医療のキーワードであり、このことにもう一つのキーワード「インフォームド・コンセント」に象徴される患者の知る権利も加わって、いくつかのオプションのなかから治療選択を行なわなければならない時代となった。 ・その際、意思決定を行なうのは患者自身であるというのがいよいよ合意になりつつあるが、では昏睡状態などにある患者ではどうなるか。そこでアメリカでは、州法で「リビング・ウィル」(延命措置を拒む意思表明)制度を定めている州が増えている。 ・一方、臨床の現場ではとうてい一人の医師では対応が困難なケースが増え、いっせいに各病院では「倫理委員会」が設けはじめられていた。これには激増する医療訴訟から医師を守るという意図もあったことはいうまでもない。 ・わが国ではなぜか疼痛緩和、ホスピス運動などとリンクしてガンの末期医療だけが注目されることが多く、一九八八年に厚生省が中心になって「ガン末期医療にかんするケアのマニュアル」が作成されたが、現実には末期医療は高齢者医療を含めあらゆる分野で問題となっているはずなのに、ガンに隠れてただ表面化していないだけと考えられる。 ―― 完 ―― |