
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2022年01月26日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
35 |
21.06 |
大東亜戦争ここに甦る 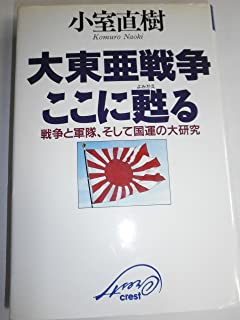 |
小室直樹 |
クレスト社 |
◎ |
まえがき 戦後、マスコミと政治家が犯した大罪 ・思えば戦後五〇年、わが国には東京裁判史観が蔓延し、戦争、なかんずく大東亜戦争を論ずるだけで “戦争屋” とされる空気が支配してきた。 ・だが、平和主義者という名の頑民がはびこったために、ヨーロッパは第二次世界大戦という泥沼に、自ら身を投じていったではないか。 ・歴史を真摯に観察すれば、平和主義者が戦争を起こしたという逆説に満ち満ちている。 ・そもそも東京裁判(極東国際軍事裁判)とは、国際法に基づく裁判でも何でもなく、連合軍最高司令官・マッカーサー元帥の命令に基づく裁判にすぎない。勝てば官軍、勝者が敗者にヴィクトリー・ジャスティス(勝者の都合)を押し付けた ・現に、マッカーサーは後年、上院で「第二次大戦は日本にとって自衛の戦争であった」と、自らが主唱した日本の侵略戦争説を明確に否定した。 ・さらにトルーマン大統領との会見では、「東京裁判は誤りであった。あの裁判は戦争を防止するうえで何の役にも立たない」と反省しているのである。 ・はたして、連合国は侵略戦争を繰り返してきたではないか。米国のベトナム戦争、ソ連のハンガリー事変、チェコ事変、アフガン戦争、英仏のスエズ戦争、中国のベトナム侵攻、すべて違法な武力行使(侵略戦争)である。 ・だが、東京裁判史観に基づくアメリカのマインド・コントロール(教育支配)に酔う日本の大新聞は、この大ニュース(マッカーサー発言)を報道することはせず、したがって多くの大衆は、依然として東京裁判は正義の裁判であり、あの戦争は侵略戦争だったとの間違ったイメージを抱きつづけている。 ・これでは、あの戦争で犠牲となった日本人はすべて犬死にということになり、その魂は永遠に浮かばれないではないか。 ・戦争とは外交の一手段にすぎない。 ・先の敗戦は日本民族の外交音痴が引き起こした悲劇だと言っても過言ではない。 ・しかも、現在の日本の政治家の外交音痴ぶりは、その戦前の政治家に較べても絶望的で、現首相・村山富市を筆頭に、ほとんど白痴的状況にあると言ってよい。 ・自国の歴史に侵略の烙印を押し罵詈雑言を浴びせているのに、連合国に巣くう死の商人の暗躍で、世界に戦争がはびこっている恐るべき事実には一言も触れようとしない。日本こそ、このことについて発言権を有する唯一の国だというのに! ・半世紀前の日本民族の歴史を “呪縛の世界” に埋め去ってはならない。現在の、そして未来の生きた現実的な英知として “歴史” は存在すべきものなのだから――。 第一章 帝国海軍、高度成長の秘密 ――なぜ開国五十余年で、世界のトップに伸し上がったか (1)「陸奥と長門は日本の誇り」 日本海海戦の勝因を研究した英国、しなかった日本 ・一九〇六年、イギリスは戦艦ドレッドノート(弩級戦艦)を完成させたのである。建艦技術上の革命である。 ・英国海軍は、日露戦争の勝敗を左右した日本海海戦(明治三十八年)を徹底的に研究した。この大海戦の勝負を分けたものは何であったか。決定的な威力を持ったものは何か。これについて明白な結論が出た。それは、戦艦の主砲たる大口径砲である。 ・ドレッドノートこそ実に、日本海海戦研究の研究成果であった。 ・ドレッドノートは、一〇門の一二インチ(三〇・五センチ)砲、主砲以外の小口径砲は、決戦用ではなく、水雷艇を追っ払うための三インチ速射砲二七門だけとした。 ・機関は、最新式(当時)の蒸気タービンを使って二一ノットの快速(それまでの戦艦は、速くて一八ノット)。 ・これだけの性能を一万七九〇〇トンにまとめたのだった。(三笠は、約一万五〇〇〇トン。一二インチ砲四門。一八ノット)。 ・日本海海戦で大勝したのは日本海軍である。それなのに、日本海軍は、その勝因の分析を行なわなかった。 ・連合艦隊が解散した時、東郷平八郎は、「勝って冑の緒を締めよ」と訓示した。が、この訓示は生かされなかったようである。 ・圧勝の結果、多くのロシア戦艦が日本に鹵獲(捕獲)された。これらをわが海軍に加えれば、勢力は倍増するであろうと、海軍首脳は有頂天となった。何の研究分析もなしに。 ・日本海軍は、本気になって研究しなかった。それで、何をしたか。引き上げたり分捕ったりしたロシア戦艦を、修理し、改造し、日本戦艦として加えようとしたのであった。 ・このコストを、なぜ、新戦艦の研究開発に回さなかったのだろう。 ・いや、日本が自力で建造した新戦艦は、完成された日において、すでに旧式化していた。明治四十三年に竣工した戦艦・薩摩がそれで、なんと二万トンを超す大戦艦である。 ・日本は歴史に学ばない。大東亜戦争の敗戦に際して、「敗者勝因を蔵す」をいっさい無視したように、どんな大切なことでも、棄てて省みない。このことを、まずここで銘記すべきである。 "師匠" 英国への再入門 ・ドレッドノートに触発されて、日本も弩級戦艦建造を始めた。が、あまり思わしくない。ま、月並みであった。 ・こんなことでは大海軍にふさわしくない。誰もが目を見張るような軍艦を造らなければ――。山本権兵衛はじめ、海軍首脳は決意した。 ・弩級戦艦の上の超弩級戦艦、超々弩級戦艦においては、英米をぐっと凌駕する艦を造るのだ、と。そのために、もう一度初心にかえって英国に、本気になって学び直す。 ・日本は、世界最大、最強の巡洋戦艦・金剛を発注した。 ・英国のヴィッカース社では、世界一の巡洋戦艦・金剛を、喜んで造ってくれた。主砲一四インチ砲八門、速力二七・五ノット。二万七五〇〇トンの巨艦であった。断然、世界一。 ・金剛がヴィッカース社で建造されている時には、日本から、技師、軍人から造船職工に至るまでの人びとが、続々と英国へ押し掛けて行って最新式の造船技術を学んだのであった。 ついに世界一の大海軍国に伸し上がる ・日本は、この最新式の造船技術を活用して、金剛の姉妹艦(同型艦)・比叡、榛名、霧島を国産した(大正三~四年完成)。 ・四隻の巡洋戦艦を手本にして、戦艦・扶桑、山城、次いで伊勢、日向が建造された。 ・このようにして、大正七年には、日本は、世界最新鋭の超弩級戦艦四隻、巡洋戦艦四隻を備え、押しも押されぬ世界一流の大海軍国へと伸し上がった。 ・その大海軍国日本が、百尺竿頭、なお一歩 ・巡洋戦艦・金剛が完成したのが大正二年。世界一とは言いながら、金剛は英国製、日本海軍は、まだ、英海軍の弟子であった。それから僅か七年後の大正九年。日本海軍は、独力で世界一の大戦艦・長門、陸奥を建造して、英米の心胆を寒からしめたのだ。 第二章 支那事変は、どう戦うべきだったか ――南京を一気に叩けば、大東亜戦争も起こらなかった 支那事変は、断固やるべき戦いだった ・なぜなら、当時の中国を支配していたのは、侮日・排日の空気。日本に対する反感は、全中国に澎湃として漲っていた。もはや、戦争をしないですまされる条件下にはなかった。 【私見 : なぜ、侮日・排日の空気となったのか。これが日本が戦争をする必然性とどうつながるのか知りたい】 ・戦争は不可避であったが、日本の戦争のやり方は拙劣をきわめた。戦争目的もなく戦争設計もなかった。戦争をするでもなく、しないでもなく、気が付けば戦争になっていた。これでは勝ちようがない。 ・「意志の集中、力の集中」こそ戦勝の秘訣である。日本の意志と力は、つねに分散していた。 ・中国の現状(当時)も分析せず、中国の本質も理解していなかった。つまり、中国を知らなかった。また、日本(とくに日本軍)の長所も短所も知らなかった。敵を知らず、おのれを知らなかったのである。これでは勝ちようがない。 ・もし、敵を知り、おのれを知っていたならば、適切な戦争設計があり、意志を集中し力を集中していたならば、日本は支那事変に勝っていた。その結果、大東亜戦争にも勝っていた。 ・当時、日本が一気に満州を征服したので、中国には「日本恐るべし」と再認識した人もいたが、これは少数派。もはや、反日を標榜せずには、国民の支持を得がたい時勢であった。 ・しかし、豈にはからんや。中国の一方の指導者たる蒋介石と汪兆銘こそ、当時の大陸における日本の最大の味方であった。味方というのが言い過ぎならば、日本の最大の理解者であった。 ・「抗日而非排日」(抗日にして排日にあらず――日本の無理無体には抵抗するが、やみくもに日本を排斥しない)とは、汪兆銘の有名な言葉である。だが、ここに気付く日本人は ・政治家、軍人の中にはそれを熟知していた者もいたが、彼らも日本国民の誤解を正そうとはしなかった。さらに致命的なことには、日本の指導者はその事実を政治的に利用しようとしなかった。 ・敵中に味方を求める。これこそ政治の要諦である。その真理を一顧だにせず、支那事変に突入していったという事実だけ採っても、日本人がいかに政治的に未成熟であったかが知れようというもの。 ・当時の中国は抗日、反日、排日、侮日でなければ夜も日も明けぬ。日本と戦えと叫べば、わっと人気が出る。この空気を利用したシナ大陸の政治家は多かった。 ・ところが、蒋介石と汪兆銘は違った。彼らの認識は、毛沢東が率いる共産軍こそ「内臓をむしばむ病毒」。だが日本軍は「外傷」にすぎぬ。これが蒋介石の持論であり、汪兆銘も同じ意見であった。 ・というのも、日本軍との戦争に深入りすれば、共産軍に付け込まれて命取りになるであろう。しかも、蒋介石汪兆銘も、日本軍の強さを肝に銘じていた。 ・ゆえに、この二人は日中衝突の防止を自己の任務として自覚していたのである。 ・なぜ、日本はこの二人の指導者を、もっともっと有効に利用しなかったのか。そうすれば間違いなく日本は戦争に勝てたはずだった。 なぜ中国人は日本を侮ったか ・中国侵略の元祖は英国である。次いでフランス。日本は欧米帝国主義諸国の後塵を拝していたにすぎぬ。なのに、なぜ日本ばかりが嫌われる。 ・古来、中国崇拝に凝り固まったていた日本が欧米崇拝に転向し、明治以降(特に日清戦争以降)、露骨に中国を軽侮するようになった。 ・「崇拝者が軽侮するようになる」――これほど相手の自尊心を傷つけ、怒らせることはない。対人関係においても、国際関係においても、この鉄則はゆるがない。 ・英仏米は未知の国であり、どこからともなく現われてきた。これに対し日本は、古来、中国の忠実な弟子であった。中国人にとって日本人は東方の猿に近い野蛮人にすぎなかった。その日本が、あろうことか、英仏米といっしょになって中国を軽侮し支配しようとする。 ・だから、スケープゴートとして日本ほど恰好なものはない。中国統一のために、「侮日、抗日」より有効なスローガンはない。 ・なんと言っても大きかったのは「日本軍は強すぎた」――このことである。 ・日清戦争以降、中国軍は「日本軍には敵わない」と逃げるばかり。日本軍は「進撃すれば、中国兵はすぐ逃げる」。双方、こう思い込むようになってしまったのだ。 ・ところが、昭和になっての神話が翳るような事件が起きた。南京事件である ・昭和二年(一九二七年)、国民革命軍総司令・蒋介石の北伐軍が南京に侵攻してきた時、外国居留民に対する暴行殺傷事件が起こった。 ・首都を占領すれば、恣に大掠奪をするのが中国兵の慣行。蒋介石の国民革命軍もまた、この前近代的陋習から自由ではなかった。 ・北伐軍に占領された南京では「日英帝国主義打倒」が叫ばれ、日英米仏伊などの居留民たちに、中国の暴兵と暴民とが荒れ狂った。 ・この時、風前の灯火のごとき在留日本人の生命を守るために森岡正平は何をしたか。 ・暴兵・暴民を刺激せぬように荒木 ・この無条件降伏に等しき屈辱に荒木大尉たちは耐えた。無抵抗主義に徹したのである。だが、その結果はまったくの無駄。いや、逆効果であった。日本領事館と居留民は暴徒に凌辱され、掠奪されたのであった。 ・他方、英米は、下関に碇泊中の砲艦に銘じて、南京城内に艦砲射撃を加えた。その効果は ・この時、日本の砲艦は何をしていたか。「米英の艦砲射撃に参加すれば、日本居留民は惨殺される」と言う森岡領事の懇願によって、発砲を控えていたのである。 ・この「度を過ぎた」無抵抗主義が中国人の侮りを招いた。日本人は悪鬼羅刹のごとく恐ろしいと思い込んでいたが、案外、臆病で御しやすい民族ではないか、と。これが中国における本格的侮日の始まり。 ・南京における日本の徹底的無抵抗主義は、日本国内でも物議を醸した。 ・そして陸海軍は、こんな屈辱は二度と繰り返さないぞと身構えたのである。 ・だが、一度落ちた「日本軍無敵」の偶像はふたたび戻らぬ。日本人は英米人に較べると本当は弱いのだと、中国人は思うようになった。 中国人は、原則に固執するが、きわめて現実的民族 ・支那事変(日中戦争)の和平の条件とは、満州国承認の要求は、 ・汪兆銘は蒋介石とともに、日中戦争を止めることに全力を挙げた。 ・「満州国承認以外のことならば、いかなる条件を吞んでも日本と和平するべきだ」と。これが汪兆銘の持論であった。 ・汪兆銘の発言は換言すれば、その他の項目においては無条件降伏に等しい譲歩をしても構わないが、満州国承認だけは断じて認められない。こういうことである。 ・孫文の三民主義(民族・民権・民生)の大原則からして、絶対に中国の領土を外国に割譲することはできない。これを認めてしまっったら、国民党政府そのものの存在意義が失われてしまう。ここのところを日本は理解すべきであった。 ・だが、当時の満州は日本の生命線。日本も譲れない。この矛盾をいかにすべきか。しかし、中国を本当に理解していれば解決は容易である。 ・中国人は理念上はあくまで原則に固執するけれども、現実面においては「諦める能力」を有している。タテマエでは原則を頑として ・このとき、満州はもはや日本のものである。いかに三民主義者とはいえ、この現実を認めない中国人はいない。だから、ホンネでは諦めてもいいと思っている。なぜなら、満州は化外の地、北狄(北の蛮族)が棲む地である。 ・孫文も蒋介石も、満州・蒙古をもって日本と取引することを厭わなかった。 ・蒋介石でも汪兆銘でも誰でも、満州国が実質的に日本のものとなることは、やむをえないと諦めたと思われる。中国人ほど政治力学の結果を客観視する人びとも珍しい。 ・だが、その一方で中国人は骨の髄まで原理主義者であるから、タテマエとしては、絶対に満州国を承認することはできない。 ・日本人は、この呼吸を吞み込むべきであった。呼吸を吞み込んで、満州国承認などは 中国統一とは長城以南すべての土地の統一 ・第二の条件とは――。万里の長城の内側は中国に渡すこと。これである。 ・中国人は満州や蒙古、すなわち万里の長城の外側に関しては、現実を優先させて理念を諦める。 ・だが、長城の内部となれば、話は別。中国人の態度はガラリと変わる。孫文が始めた中国の民族運動、すなわち三民主義の大原則からすれば、中国の統一は革命の必然的要請である。 ・中国統一とは、長城以南すべての土地の統一であらねばならぬ。このことをよく理解して、日本は北支をきっぱりと中国に渡すべきであった。これが第二の条件である。 ・ところが現実には満州事変後の関東軍は北支に兵を進め、北京を占領し、華北五省(河北、山東、山西、察哈爾、綏遠)の独立工作を進めていた。 ・満洲の次は北支か。関東軍の動きを中国は警戒していた。北支問題こそ、当時の日中関係の癌であった。 不平等条約の辛さを日本はよく知っていたはず ・第三の、そしておそらくきわめて重大な問題は、不平等条約の解消である。 ・当時の中国は、日本と欧米帝国主義諸国に不平等条約を押し付けられて苦しんでいた。 ・この不平等条約の辛さを、日本ほどよく知っている国はなかったはずなに、当時の日本は中国に対して同情を示さなかった。 ・日本が明治二十二年に民法、刑法をはじめとする近代ヨーロッパ式法律を大慌てに制定した目的は、国民生活のためなどではない。ひとえに不平等条約の解消にあった。 ・近代法を施行することによって、文明国としての体裁を整え、不平等条約を改正しようというのである。 ・日本ほど不平等条約の屈辱、苦しみを知っている国はなかった。その日本が、今度は中国に同情して不平等条約の改正に尽力する。これを天下に宣言し、実行していれば、どれだけ中国人の喝采が得られたか。 経済は親日、政治は反日 ・そもそも当時の日中関係の基礎は、ひとえに経済面におけるつながりである。 ・日本人の居留民は生活の場を求めて中国に移住していった。これに伴って、日中間の経済的つながりは強固になる一方であった。満州国は日本の生命線と称されたが、本当の「生命線」とは日中の経済関係のほうである。 ・一九三二年(昭和七年)のオタワ協定によって、日本は大英帝国およびその植民地から締め出されてしまった。さらにルーズベルトの採った対日関税政策によって対米貿易に大打撃を受けた日本としては、日中経済関係の発展にこそ、国家の生存がかかっていた。 ・他方、中国から見れば、資本主義の発育のためには日本との経済協力が不可欠でもあり、最も実効性があった。たとえば、上海における紡績業は日本人従業員約五〇万人、中国人従業員約一〇〇万人で、日進月歩で隆盛へ向かいつつあった。 ・経済的に言えば、当時の日中ほど、お互いに相手の協力を必要とする国はなかった。友好関係を結ばなければならない国は他になかった。そこに双方の未来がかかっていたと言っても過言ではない。 ・経済における親日と、政治における反日、尖鋭この上なき矛盾をいかにするか。今日においても、この構図は基本的に異ならない。 共産党は腹背の病、日本は皮相の病 ・昭和初期において、まともに日本と闘って国民党政府軍が勝てるわけがなかった。しかも、この国民党政府の敵は日本だけではない。もう一つの敵は共産党、さらには諸軍閥間の内部抗争もあった。まさに国民党政府は四面楚歌の中で戦っていた。 ・これらの戦争の中で、蒋介石が最も重視していたのは、対共産軍戦争である。 ・蒋介石としては、一刻も早く対日戦争を切り上げて、共産軍との戦いに没頭したかった。彼の脳裏に大きくのしかかっていたのは、中国共産党なのである。 ・つまり日本としては、蒋介石が安んじて共産軍討伐ができるような環境を提供してやればよかった。そうすれば、日本は支那事変を有利に終わらせて、日中関係を緊密にできたのである。 ・ところが現実や、いかに。第一次上海事件において、日本軍は「案外に弱い」という評価で中国人から見られるようになってしまった。 ・これで困ったのは日本ばかりではない。戦った蒋介石も困った。というのも、中国における対日戦争の主唱者は共産党である。共産党は終始、対日戦争こそ第一の急務と主張してきた。これに対する蒋介石は、対日戦なんかやったら国を滅ぼすと反対してきたのである。 ・ところが、上海事変で風向きが変わった。無敵日本軍に対するイメージが揺らいだことで、蒋介石の主張が大衆の支持を得られなくなり、その分、共産党の支持者が増えていったのである。 ・この流れの中で、一九三六年(昭和十一年)に西安事件が起こるのである。西安で張学良に監禁された蒋介石は、ついに従来の主張を捨てて国共合作を行ない、対日戦争遂行を決意せねばならなくなったのだ。 ・西安事件によって、日中戦争は不可避になった。だから、この翌年に起きた支那事変を「やるべぎはなかった」という議論はまったく無意味なである。 第三章 日米の運命は、なぜ逆転したのか ―― 真珠湾奇襲は、米海軍士官の常識だった ・米海軍軍人は、海戦史を研究してすぐ気付いた。日本海軍は、開戦直前の奇襲攻撃から戦争を始める、と。 ・日清戦争の緒戦・ ・これが日本海軍の行動様式だとすれば、日米戦争でもこれをやるにちがいない。当然の結論である。 ・では、アメリカのどこに奇襲をかけてくるのか。地図を見れば、ハワイ真珠湾。必然の結論である。日本空母による真珠湾の米艦隊奇襲。これは歴史好きのアメリカ海軍士官の常識であった。 第四章 帝国海軍、七二年間の宿痾 ――緒戦に大勝すると必ず、 "無連帯" に陥る不可思議 無知が招いた山本五十六の「必敗の信念」 ・ロンドン軍縮会議においては、何がなんでも対米七割という日本の宿願も空しく、結局、六割に押さえ込まれてしまった。 ・「日本海軍は米英と戦うようには作られていません」とは米内光政の口癖であった。 ・昭和十五年九月の山本五十六の発言。 「(日米戦を)ぜひやれ、といわれれば、はじめの半年か一年の間は、ずいぶんと暴れてごらんに入れます。しかし、二、三年となれば、まったく確信はもてません」 「連合艦隊司令長官としてではなく、一大将として、あるいは第三者の立場として一言したい。日米戦は長期戦となることは明らかです。日本が有利に戦いをすすめても、アメリカは戦いをやめることはない。そうなれば、戦争は数年になり、資材は使いつくされ、艦隊や兵器は傷つき、補充は大いに困難となり、ついにはアメリカに対抗し得なくなる」 第五章 真珠湾の奇蹟は、なぜ起きたか ――奇襲大成功で、世界の戦略的バランスは激変した なぜ、米太平洋艦隊は真珠湾にいたか ・米太平洋艦隊はずっと、西岸のサンジェゴ軍港にいた。 ・いくら日本の機動部隊だって、奇襲攻撃は不可能である。遠すぎる。 ・米海軍の士官たちにとっては、開戦前の日本海軍の奇襲は常識であった。 ・そんな危険があるのならば、米太平洋艦隊は、いっそのこと西海岸のサンジェゴ軍港に置いとけば――。これが、米海軍の、いわば "世論" であった。 ・しかし、ルーズベルト大統領が、太平洋艦隊をハワイに移動させたのである。 ・大統領の意図は、純軍事的なものというよりも、むしろ、政治的なものにあった。目的は日本を恫喝することにあった。 ・日本をオランダ領インドシナ(現在のインドネシア)に進攻させないようにする。これが、米太平洋艦隊ハワイ移動の目的であった。 第七章 運命の岐路――インド洋作戦 ――日独が共同して中東を押さえていれば、世界史は変わっていた 日本が勝ち逃げするシナリオとは ・米軍反攻の時期を遅らせても、結局、何になるというのだ。巨大な生産力を誇るアメリカ(当時、世界の約半分)にとって、反攻の時期は、遅れれば遅れるほど有利である。アメリカの軍事生産は、時が経てば経つほど加速度が付いて弾みも付く。 ・いくら反攻の時期を延ばしたところで、やはり、日本の勝利はおぼつかない。いや、延びれば延びるほど、日本の勝ち目はなくなるのである。 ・インドでは、反英の気運が高まりつつある。インド人を奴隷のごとく扱う英国の圧制に不平を持たないインド人はいない。それでも英国に屈服しているのは、英軍があまりにも強いからである。 ・インド人が、どれほど英国の軍事カリスマ喪失の日を待ち望んでいたことか。万人想像の外にあろう。 ・白人は強いから有色人種を奴隷扱いしている。この迷信が破らるるや、アジア人は狂喜する。 ・ネールもチャンドラ・ボースも、その他インド独立運動の志士たちも、「日本軍、ロシア軍を破る」のニュース(日露戦争)に欣喜雀躍した。そして、インド独立の決意を新たにしたのであった。 ・日本人なんて見たこともないのに、その白人に対する勝利をインド解放の なぜ英空軍は、弟子の日本に後れをとったか ・英東洋艦隊司令長官ソマビル中将は、日本艦隊のセイロン空襲が四月一日であることを知っていた。 ・日本海軍の暗号を解読していたからである。独自に解読していたことが戦後に判明した。 日独が完勝するための "現実的シナリオ" ・日本の政治家に、日本の軍人に、いや、山本五十六大将一人にでも「戦争設計」の能力があれば、大東亜戦争の初期に、ルーズベルトが最も恐れていたことが実現していたのである。 ・一国の政治家の外交能力――「戦争設計」能力も外交能力の一分野にすぎないわけだが――この能力の有無によって国運、ひいては国民の運命は大きく左右される。 ・表現を変えれば、戦争に無知な平和主義者が、結局、戦争を起こすというのが「歴史の鉄則」なのである。 ―― 完 ―― |