
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2022年02月09日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
5 |
21.01 |
天皇家の戦い 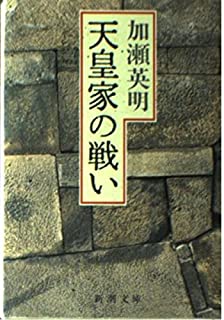 |
加瀬英明 |
新潮文庫 |
◎ |
最後の観兵式 ・第二次世界大戦を戦場で刀を吊って戦った軍隊は、一九三九年に潰滅したポーランド軍と、日本軍だけである。 近衛公のオカルト ・天皇は、御文庫の謁見所で金屏風を背にして、座っていた。 ・近衛は、内ポケットから和紙を取りだして、低い声で読みはじめた。 『敗戦は遺憾ながら、もはや必至なりと存じ候。』 『敗戦は「わが国体」に傷をつけることになろうが、アメリカや、イギリスでも、現在のところでは、世論はまだ天皇制の廃止までは要求していない。しかし、これからはどうなるか、わからない』 『国体護持の建て前より、もっと憂うべきは、敗戦よりも、敗戦にとものうて起ることあるべき共産革命にて候。つらつら思うにわが国内外の情勢は、今や共産革命に向って急速度に振興しつつりと存じ候……』 『東ヨーロッパ、フランス、ベルギー、オランダなどで、ソビエトが赤化工作を進めている。日本に対しては、モスクワから延安に送り込まれた岡野(野坂参三)を中心に日本解放連盟が組織され、朝鮮独立同盟、朝鮮義勇軍、台湾先鋒隊などと連絡して、日本を共産化することを狙っている』 『ひるがえって国内を見るに、共産革命達成のあらゆる条件、日々具備せられゆく観これあり候。すなわち生活の窮乏、労働者の発言権の増大、英米に対する敵愾心昂揚の反面たる親ソ気分、軍部内一味の革新運動、これに便乗するいわゆる新官僚の運動、およびこれを背後より操りつつある左翼分子の暗躍などに御座候』 『とくに憂慮すべきは、軍部内一味の革新運動に御座候』 ・木戸は立って、メモをとっていた。 「少壮軍人ノ多数ハ我国体ト共(共産主義)ハ両立スルモノナリト信ジ居ルモノノ如ク、軍部内革新論ノ基調モ亦ココニアリ。皇族方ノ中ニモ此主張ニ耳ヲ傾ケラルル方アリト仄聞す」 ・近衛 『以上のごとく、国の内外を通じ共産革命に進むべき、あらゆる好条件が日一日と成長しつつあり、今後戦局ますます不利ともなれば、この形勢は急速に進展致すべく存じ候。戦局への前途につき、何らか一縷でも打開の望みありというならば格別なれど、敗戦必至の前提の下に論ずれば、勝利の見込みなき戦争を、これ以上継続するのは、まったく共産党の手に乗るものと存じ候……』 ・それから近衛は、まず共産主義者に操られている「軍部内の一味」を追放することが必要であるといった上で、『共産革命より日本を救う前提先決条件なれば、非常の御勇断をこそ望ましく存じ奉り候。』と結んだ。 赤色革命恐怖症 ・二月十九日、牧野伸顕伯爵が御文庫の謁見所に入った。 「赤は日本国民の士気を阻喪させることによって、日本を敗戦に導き、赤化しようとはかっております。とにかくスパイでなければわからぬようなことが、外へ漏れておりまする。赤の手先は、軍部、諸官庁に根を張っているといわれておりますが、意識することなしに赤の説をとり入れて、不知不識にその手先となるようなことも、多々御座います」 ・牧野がそういうと、天皇は強く頷いた。 ・終戦は、天皇が決められることではなかった。ちょうど開戦のように、政府と軍部が決定するべきものであったのだ。 ・といっても、政府や軍が、天皇に対して責任を負っているように、天皇は国民に対して責任を負っていた。 ・そして、天皇は皇祖に対しても責任を負っていた。天皇にとっては、皇祖や、神々を祭ることが、そのまま日本を存続させることであった。日本は神々を祭る皇家なしには、日本ではなくなってしまう。とにかく二千年近く、天皇家はその家系に、自分たちなしには日本が存在しないという信仰を伝えてきたのだった。 ・天皇制を維持することは、絶対に必要であった。天皇制が廃止されるようなことがあったら、日本はなくなってしまう……。 「天皇は自決されよ」 ・ソ連に和平の仲介を依頼しようということは、五月に最高戦争指導会議によって決定されていた。 ・ソ連に働きかけて、仲介させようという案を持ち出したのは、外務省であった。 ・日本の敗戦によって戦争が終れば、ソ連と米英が対立するのが明らかである以上、ソ連は日本が無力化して、米英によって占領されるのを好まないだろうから、日本のために介入するだろうと読んでいた。 ・会議は南樺太の返還、千島北半分の譲渡、北洋漁業権の解消、旅順、大連の咀嚼を認めること、満州国の中立化、北満鉄道権利の譲渡、津軽海峡の解放などをはじめとして、ソ連への大盤振舞いを認めた。 ・陸軍は満州を空にしていたために、ソ連が参戦することに対して恐怖感に駆られていたので、あっさりと賛成したし、外務省はかなりの自信を持っていた。 【私見 : 日本は何とノー天気だったか。ソ連を頭から信じていたとは。すでにヤルタ会談等、戦勝国間で日本への対応は話し会われていたのに。ソ連の参戦もアメリカは承知していたし、日ソ中立条約も無視されている。】 ・七月も終りに近づくと、さすがにソ連が日本のために和平の仲介をする熱意がまったくないことに気付かざるをえなかった。 ・近衛はこれ以上、降伏が遅れれば、連合国が天皇制の廃止を要求するだけでなく、前大戦のロシアのように共産革命がかならず起きるだろうと信じていた。 皇居に原爆が…… ・大本営にはすぐに、広島に対して「特殊高性能爆弾」による攻撃が行われ、「大被害」を生じたという短い第一報が入った。 ・死んだ十数万人のなかには、日韓併合の時に日本の王公族となった李王家の一人である李ぐう(金偏に禺)公がいた。李ぐう公は、李王家の当主である李王垠の弟で、第二総軍参謀として広島にいた。 ・閣議で、広島に対する「特殊弾攻撃」が話題にのぼると、阿南陸相が「原子爆弾なぞは空想の産物であり、アメリカのデマ放送にうろたえるべきでない」と強弁した。軍は、もはや国民が何千、何万人死のうと、まったく関心がなかった。 ・佐藤大使は、クレムリン宮殿の一室で、モロトフ外相と面会した。七月十七日に東京から受け取った訓令の通りに、天皇の「大御心」を伝えようとすると、モロトフは手をあげて制して、ソ連の対日宣戦布告文を読みあげたのだった。 ・九日の朝刊は、李ぐう公が広島で六日の空爆により、「戦死」したと報じた。朝鮮王公族は皇族として扱われていたが、皇族が国内で戦死したのは、これがはじめてだった。 ・午前十時に、広島の江波町にある陸軍飛行場では、一機のDC3型機がプロペラを回しはじめた。輸送機が動きだすと、滑走路のわきに並んだ第二総軍の幹部将校や、居あわせた将校や、兵がいっせいに敬礼した。 ・並んだ将兵のうち、多くの者の顔が焼け爛れ、頭や腕に繃帯を巻いていた。飛行場は草がいっせいに一方に靡いて、一面、赤茶色に焼け焦げ、何本か枯木が立っていた。爆心地から、三キロしか離れていなかったのだ。 ・飛行機は、壊れた建物や、航空機の残骸のわきを滑走して、広島の上空にのぼっていった。飛行機は、李ぐう公の遺体を乗せていた。そして、李王家の墳墓の地である京城の空へ向けて、消えていった。 ・最高戦争指導会議にて 天皇は、大東亜戦争が始まってから、「陸海軍とも、予定と結果がどうもちがう」、本土決戦には勝つ自信があるというが、参謀総長の報告とちがって、九十九里浜の防備すらほとんどできていない、兵士に銃剣すら行き渡っていない、このような状態で本土決戦に突入したらどうなるか、「どうして、この日本という国を、子孫に伝えらるのだろうか?」といった。 「……堪え難いこと、忍び難いことであるが、わたしはこの戦争をやめる決心をした……」 「自分のことや、皇室のことなど心配しなくてもよい」 皇族は泣かなかった ・天皇は声を震わせて、思い詰めたようにたずねられた。 「今日の皇族の会議において、もし朝鮮の処分問題がでた場合、わたしはどうしたらよいのだろうか。これから李王以下の処遇をどうするのか、もしたずねられたら、いったいどういって、答えればよいのだろうか?」 ・日本の降伏条件を初めて規定したカイロ宣言では朝鮮の独立がうたわれていたが、朝鮮の王公族は日本の皇族として扱われていたのだった。 ・会議室では、各宮は皇族の順位に従って、高松宮、三笠宮、閑院宮、賀陽宮、賀陽宮の長男の ・天皇は座ると、すぐに話し始めた。 「本日、みなに集まってもらったのは、十日の最高戦争指導会議で表明した、わたしの決心とその理由を話し、この一大非常時において、皇族一同が一致協力してもらいたいと思うからである。天皇の統治の大権は変更しないという条件を連合国に申し出て、ポツダム宣言を受諾するという決心を、わたしはした。今朝、連合国のほうから回答がきたが、この点は認められたと思う……」 ・天皇は長期の戦争で国力が疲弊してしまった、最近の戦闘が「敗北に敗北を重ねている」うえ、九十九里浜の防御陣地も完成しておらず、本土決戦の勝利は「とうてい信じられない」し、連日の爆撃によって国民が「悲惨な状況に置かれている」といった。 ・「もしこのまま戦争を続ければ、帝国臣民の苦しみ、世界人類の不幸は、計りしれないものがある。もう戦争を続けるわけにはゆかないのである。わたしは耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、明治天皇がかつて三国干渉の際に、涙を吞まれて臥薪嘗胆の御決意をなさったのと同じ気持ちで、苦しさを忍ぼうと決心した……」 ・天皇は「皇族の全員が平和を達成する目的のために協力することを望む」といって、話を終えた。 天皇はカイゼルではない ・八月十四日の御前会議で、天皇が下した二度目の聖断によって、終戦は決った。 ・これは、東郷外相をはじめとする和平派の勝利であった。東郷は外交官として外国をよく知っていたので、阿南陸相らの軍人たちとちがって、日本を他の国と同じ水準においてみることができた。 ・しかし、軍人たちは日本の外の世界をまったく知らなかった。そこで軍人たちは、外国と戦争をしているというのに、日本のなかに閉じ込められて、日本だけを考えて、戦争を行なっていたのだった。 ・日本は永年、孤立した島国であった。そして一つの言語を話す一民族が、他国にほんとうに触れることもなく生活し、一つの宇宙をつくってきた。 ・そして、これが他国であれば、どのような国でも、周囲と交流せねばならなかったので、物事を相対的に考える訓練が行われてきたが、孤立は一つの宇宙をすべての世界として、絶対化させた。 ・軍人たちは、このような "絶対化の病" とでも名付けるべきものにかかっていた。 ・むろん、今日でもまだ、多くの日本人がこの病にとりつかれている。 ・そして、昭和二十年に、軍人たちは日本や、国体という抽象的な概念を護ろうとした。そして、彼らは形のあるものを護ろうとする関心を、いっさい持っていなかった。 ・このためには、まず国民を犠牲にして、最後には自分たちすら全員死のうとしていた。彼らには「生きる勇敢」さはなかったが、「死ぬ安易な勇気」だけはふんだんに持っていた。 ・一方、天皇にとって、国体とは天皇と国民から成り立つものだった。 ・しかし、軍人が信じていたように天皇制と軍が一体だとは考えていなかったので、軍を切り捨てることができた。 ・天皇の側近で、戦争をやめることによって天皇制を救おうとした者からみれば、皇室が護持されて、政府と軍のみが降伏する形をとることによって、とくに天皇制を軍から解き放つことで、皇室を戦争から切り離すことができると考えたのだった。 ・そして、天皇が大御心により太平を開くことによって、国民を救った形をとったので、天皇は戦争を超越して、その上に身を置くことができたのである。 ・しかし、終戦は天皇個人の意志によって、もたらされたものではなかった。 ・たしかに天皇は昭和二十年に入って、フィリピンをはじめとして戦局が悪化してから、戦争に見切りをつけ、たとえ降伏という代償を支払っても、終結を図ろうという決意をした。 それでも、昭和の日本は、誰も最終的な決定者がいないという、奇妙な国家といえた。 ・天皇は国務については内閣によって輔弼――補佐――されたが、軍は天皇によって親率されていたので、国務の外にあって、統帥権が独立していた。 ・しかし、天皇が国務、統帥ともに、自らの意志で動かしたことはなかった。 ・軍の統帥にあたっては、参謀総長と軍令部総長の陸海の幕僚長が輔弼したが、内閣の場合と同じように、天皇は軍が決定したことを、決定の過程で質問することはあっても、そのまま裁可した。 ・明治憲法は、国務と統帥の二元制度をとっていた。 ・それでも明治天皇の存命中は、天皇がかなりのところまで親政したし、内閣も、軍も、明治維新のために共に働いた同じ下級武士の出身者によって上層部が占められていたので、危機にあたっては密接に協力しあえた。 ・しかし、大正から昭和になると、政府と軍、あるいは陸軍と海軍は、今日の与野党や、圧力団体のように、分裂し、相手を認めずに抗争していた。 ・それにもかかわらず、もう一方では西園寺公望といった元老が、大正デモクラシーをもたらした当時の世界の風潮に染まって、裕仁皇太子にイギリス流の立憲君主となるように徹底した教育を施した。 ・日本にとって大正時代は、第一次大戦とシベリア出兵があるが、大きな外征戦争はなかった。この十五年間は、内閣と軍が深刻に対立するような要因がなかったし、大正天皇が生来、虚弱であったうえに、脳を悩まれていたために、イギリス流の「君臨すれども統治しない」という前例がつくられたのであった。 ・そして昭和になって、軍が暴走しだすと、政府と軍は違った方向に走り、国家が外に対して、当然、備えているべき統一された国家意志がなくなってしまった。 ・統帥権の独立は、明治憲法第十一条によって規定されていたが、この二元制度はプロシアを模倣したものだった。そこでカイゼルを必要としたのに、イギリス風の君主が上に座ったので、日本には、世界にも珍しい無責任体制が生れた。 ・このために、天皇や有力な文官たちが、昭和二十年のはじめに、すでに戦争をやめることを望んだのに、さらに数百万人にのぼる死傷者がでたのだった。 ・八月十日、十四日の二回にわたる聖断について、当時、天皇を囲んでいた人々は、みな、あの夏の数日にもし鈴木内閣、あるいは鈴木首相が終戦ではなく、戦争継続を決定していたとすれば、天皇はそのように裁可していたはずであるといった。 ・天皇がもう戦争をやめたいと思っていたのは、あくまでも個人的な意志であり、内大臣として天皇の個人的な秘書長といえる木戸が天皇の意志を鈴木首相に伝えたにせよ、鈴木首相のほうから終戦の決定を下すように願い出ないかぎり、天皇の意志は公のものにすることができなかったのである。 ・それでも、阿南大将をはじめとして、十四日の朝までは徹底抗戦を説いていた狂信的な軍人たちが、どうして天皇の一言によって豹変したかは、不思議である。 ・軍人として、若いころから徹底的に天皇の絶対性を叩き込まれていたこともあろうが、結局は、どの日本人についてもいえるように、個人として考えたうえで築いた信念がないために、自分に対して責任を負う必要を感じず、拠りどころにしている上の者からいわれると、安易に転換することができたのだろうか。 ・これは、天皇への帰一であった。 ・もっとも、十五日を過ぎると、日本人のほとんど全員が一ヵ月以内に新しい環境に、巧み――というよりは、ごく自然に適応してしまうのである。 ・日本では、人格と思想は無縁である場合が多い。だから簡単に脱ぎ捨てられる。 ・日本では、主義や思想は表面的なものであるのかもしれない。 ・日本では、事実よりも言葉を大切にする。もっとも、すぐ後に政府は同じように「降伏」を「終戦」、「占領」を「本土駐留」、あるいは「進駐」といい換える。 「陛下に詫びよう」 ・日本を戦争に導いた責任は、軍人と新聞にあった。そして軍は解体され、罰せられたが、新聞はそのまま残っている。軍服に対しては深い猜疑心が植えつけられたが、どういうわけか新聞に対する警戒心はないのだ。 ・日韓併合をもたらした韓国併合条約以来、「韓国皇族」は朝鮮王公族と呼ばれ、日本の皇族として扱われてきた。 皇族首相の門出 ・戦争を終らせたのは連合国ではなく、あくまで天皇の「御聖断」であった。御聖断は日本だけでなく、世界をも救ったのである。 ・海外で、この事実がまったく理解されないのは残念である。 ・「御聖断」により「太平」が開かれたことによって、日本は戦争の加害者から、世界に平和をもたらした平和国家となったのだった。 ・だからこそ、降伏は「降伏」ではなく、「時局の収拾」であり、敗戦はであるよりは「終戦」であったのだ。そして、国民は "大戦の戦士" から "平和の戦士" となったのである。 ・今日、日本が「平和国家」である自信は、この「御聖断」からきているにちがいない。 ・だからこそ、日本の平和主義は海外の人々によって、理解しにくいのである。 軍旗は燃えつきた ・二十九日、天皇は、「やはり退位すべきだろうか」とたずねられた。 「そうすれば、戦争責任者を連合国に引渡すことをせずにすますことができるのできないか。引渡すのは、忍びないことだ。私には忍び難い。自分が一人退位して、おさめるわけにはゆかぬだろうか」 天皇は言った。 ・木戸は、聖慮の宏大なることは、まことに有難いきわみでございますが、もし、今、退位を仰せ出られるようなことがあれば、皇室の基礎が動揺し、その結果、連合国のあいだで「民主的国家にしようという議論」を呼び起しかねないので、相手方の出方をみてお考え遊ばされるように、と答えた。「民主的国家」とは、共和制の意味だった。 皇祖皇宗に詫びる陛下 ・天皇はいつも農作物の出来ぐあいを心配していた。天皇は政治権力者であるとともに、日本国民の平和と繁栄を祈る神官であった。 ・歴代の天皇はずっと皇祖を祭り、民草の幸福を祈ってきた。そして、天皇も例外ではなかった。 ・これは天皇家の伝統であったが、歴史を通じて天皇がさまざまな祭祀を行うことによって、皇祖であるとされる天照大神がのこした「葦原の ・天皇は吹上御苑の東南にある宮中三殿に、毎年二十四回行って、古式に則って拝まれた。元旦の四方拝をはじめとして、神嘗祭、新嘗祭、大祓、毎月一日に行われる旬祭といったお祭りであるが、ほかの日には、毎朝、侍従が勅使となって代拝を行なった。 ・天皇が吹上御苑のやはり東南にある小さな水田で、自ら田植えをされ、稲を育てるのも、天照大神が高天原の ・天皇はいつも軍事施設が受けた損害よりも、民間の被害に大きな関心を持っていられた。 ・いってみれば、天皇は神話に生きていた。天皇は、神話によってつくられているのであった。 ・私たちが今日、天皇の即位の詔勅や、紀元二千六百年や、開戦や、終戦の詔書のなかにかならずでてくる「皇祖皇宗」という言葉を読んで、空疎なものと感じても、天皇にとって皇祖皇宗――天照大神にはじまる天皇の歴代の祖先――は、生々として存在していた。 ・日本が戦争に敗れると、天皇は宮中三殿において、敗戦を皇祖皇宗や神々に報告しなければならなかった。 朝鮮王族の流転 ・李王垠は、日本が三十五年前に武力の威嚇のもとで日韓併合を行い、韓国の独立を奪った時の最後の皇太子であった。 ・垠も側室から生れ、父の李太王は李朝第二十六代の国王であったが、日露戦争後、韓国が日本の保護国になったのに対して、独立を回復しようとして、国外へ密使や密書を送ったのが発覚して、統監――併合前の事実上の "総督" である――によって退位を強いられ、垠の兄である ・「第一条 韓国皇帝陛下ハ、韓国全部ニ関スル一切ノ統治権ヲ完全且ツ永久ニ日本国皇帝陛下ニ譲与ス」から始まる韓国併合条約は、第三条、第四条において、韓国皇族が尊称、威厳、名誉を守られ、「十分ナル歳費ヲ供給」することを約束していた。 ・李王垠は、今や帰るべき祖国を喪失していた。 ・朝鮮が独立してしまえば、日本皇族の一員として扱われている根拠もなくなってしまうのだ……。 ・一九二〇年、李王垠は梨本宮守正王の長女である方子女王と結婚した。 ・垠がはじめて日本に連れてこられたのは、十二歳の時だった。二年後に韓国は日本に併合されるが、この時はまだ、王世子――皇太子――であった。 ・垠は人質であるとともに、日本に着くと、「日本人化」をはかる教育が授けられた。 ・垠は、学習院から、陸軍幼年学校、陸軍士官学校へ進み、日本軍人として近衛歩兵第二連隊、参謀本部付に勤務し、北支那派遣軍付として出征したほか、終戦まで国内で旅団長、師団長、第一航空軍司令官などを歴任した。 ・方子女王との結婚は、日本によって一方的に決められた。 ・二人は婚約すると、仲が睦まじかった。 ・だが、このかげでは、一生独身生活を送らねばならなかった韓国の王女がいた。 ・垠が九歳の時に婚約し、その時、王女は十一歳であった。韓国の宮廷では、一度女子が婚約して、どのような事情であれ、結婚が実現しなかったとすれば、生涯独身でいなければならなかったのである。 ・李王垠は日本の皇族の一員として扱われたが、やはり「よそ者」であった。 ・関東大震災では、朝鮮人が独立運動を起し、方々で暴動をひきおこしているというデマが飛び、数千人の朝鮮人が虐殺されたが、李王邸にも日本人の暴徒が向うおそれがあるという噂が流れた。 ・垠は「朝鮮人が、こう誤解されているのは不幸なことだ」といって憤った。 ・垠は、十二歳で日本へ出発する最後の夜に、父の李太王に呼ばれて、こういわれていた。 李太王の正室である閔妃は、日本がロシアと朝鮮の覇権を争っていた時に、ロシアと結んだため、ソウルにいた日本の守備隊と大陸浪人の一隊に惨殺されている。 「日本へ行ったならば、絶対に自分の心のなかをみせてはならぬ。そうしなければ、生命も、安全も保障されないだろう」 そして李太王は筆をとると、「忍」という字を書いた。 ・李王垠は、方子に対しても、喜怒哀楽はほとんど表情にださなかった。 ・たまに方子妃に、こういうことがあった。 「私はもう朝鮮人ではなくなっている。かといっても、日本人になりきるわけにはゆかない。結局は、どっちつかずなのだ」 「李王家は日本の皇族待遇を受けて、手厚く庇護されているが、このために朝鮮の民衆は私から離反してゆくばかりだ……その距離をちぢめようとすれば、日本との距離を大きくすることになる」 李王朝と天皇制 ・朝鮮王公族は皇族の一員としての待遇を受けていたが、身分は他の皇族のように皇室典範によらず、日韓併合の後に制定された王公家規範によって、規定されていたので、正しくいえば皇族ではなかった。 ・もっとも、朝鮮王公族というのは俗称であって、李王公家は日本の王公族であった。 ・日本には朝鮮王族として李王垠と方子妃と、朝鮮公族として李鍵公と ・日本の天皇家は敗戦という未曽有の困難にもかかわらず、生き延びることができたが、李王家はいちおう王家として存続したのにもかかわらず、三十五年間の植民地化という困難を乗り切ることができなかったのである。 ・朝鮮が解放されても、国民のうち誰も復辟を望む者はなかったのである。 「天皇之ヲ統治ス」 ・幣原が総司令部でマッカーサーと会った時に、老首相はマッカーサーから、新しい憲法のなかに戦争と軍備を放棄する条項を入れることを強いられていた。 ・マッカーサーは死ぬまで、「戦争放棄条項」が、幣原によって突然いいだされ、自分が賛成したといい張り、幣原も何人かの親しい友人にはマッカーサーから切りだされたものだと語っているものの、公的には最後まで自分からマッカーサーに対して提案したと主張している。 ・これは、大きな謎となっているが、事実はマッカーサーが幣原に押しつけたものであったろう。 ・しかし、幣原が押しつけられた、というと、正しくないかもしれない。 ・おそらく幣原は「戦争放棄」を行うのが、天皇制を護るのにもっとも有効な方策であると、マッカーサーから脅されたこともあったが、この「戦争放棄」の理念をきかされると、敗戦まで、そしてとくに外相時代に横暴な軍によって手痛い目にあわされてきただけに、簡単に共鳴してしまったというのが真相ではなかろうか。 ・総司令部では天皇と日本政府に、文字通り強制しようとする憲法案を作成する作業が進められていた。 ・日本占領にあたって、マッカーサーはワシントンから、日本の「民主化」をはかるために、憲法を含めて、「あらゆる ・マッカーサーは、トルーマンによって免職されて帰ることになるが、マッカーサーは去っても、何百万人というマッカーサーを後に残していったのであった。 ・今日の社会党や護憲派、いわゆる "平和主義者" たちは、現代のマッカーサーたちである。 大日本帝国の終止符 ・宮中の祭祀がこれほど頻繁に、そして煩雑になったのは、明治になってからのことである。 ・明治新政府は王政復古を行い、皇室を権力と権威の源泉としたが、幕府に対して、朝廷をいただく新政府の権威を強調するために、太政大臣、右大臣、左大臣といったように、古い律令時代に遡った官制を復活するなどして、新しい天皇制国家を造りあげていった。 ・御一新は欧化の時代であったとともに、 "日本化" の時代でもあったのである。 ・そして明治新政府は、神道を国家の宗教として、全国にわたって廃仏毀釈を行なったが、同時に宮中の祭祀を整備し、複雑化したのだった。 ・たしかに、四方拝は宇多天皇の寛平二年以前から一千年以上にわたって行われ、春分の日にあたる春季皇霊祭は、さらに以前に遡るが、紀元節祭から、一月三日の元始祭、神武天皇祭、祈年祭や毎月の旬祭といったように、ほとんどが明治になってから新しく制定されたか、永く中断されていたものを復活させたものである。 ・天皇に対する戦争責任論は、連合国からだけではなく、国内で共産党が天皇を「戦犯」として激しく攻撃していたのはいうまでもないが、保守派のなかの識者のあいだでも囁かれていた。 ・近衛が遺書とともに、天皇が優柔不断であったために戦争を招いたという手記をのこし、それを天皇が読まれた。 ・天皇は、思い悩まれていたのだろう。紀元節前後のある日、藤田侍従長が御文庫の御政務室に上奏があって入ると、言われた。 「申すまでもないことが、戦争はしてはならないものだ」 「わたしは今度の戦争について、どうかして戦争を避けようとして、打てるだけの手は、ことごとく打ったのだよ。それでも、わたしの力の及ぶかぎり努力して、一生懸命やったのだが、ついに効をみず、戦争に突入してしまった。まことに残念なことだった」 「ところで、藤田、この戦争について、このごろ一般で申すそうだが、この戦争はわたしがやめさせたので終った。それができたぐらいなら、どうして開戦前に戦争をとめることができなかったものかという議論であるが、なるほど、この議論はいちおうの筋が通っているようにみえる。いかにも、もっともらしく聞えるのだね。しかし、そうではないよ」 「申すまでもないが、わが国には厳として憲法があって、わたしはこの憲法の条項によって行動しなければならない……この憲法によって、国務上ちゃんとだね、権限を委ねられ、責任を負っている国務大臣がそれぞれいる。この憲法に明記してある国務の各大臣の責任の範囲内には、わたしの意志によっ勝手に容喙し、干渉し、掣肘することは許されない」 「だから憲法上の責任者が最善を尽して、ある方策をたて、規定に従って提出して、わたしの裁可を請われた場合には、それがわたしの意に満ちても、意に満たなくても、よろしい、といって、裁可する以外にとれる道はないのだよ。専制国家ならちがうが、立憲国の君主として、わたしはそうするほかないのだよ」 ・そして、戦争を「やめた時は、開戦の時と事情が異なっていた」といわれた。 ・戦争継続か終戦か、両論に分れて対立していたところに、鈴木貫太郎首相が、自分にどちらに決すべきか、きいたからというのである。 ・それに日本は「熾爆撃、あまつさえ原子爆弾を受けて、惨禍が増大し、これ以上、無理な戦争を続けては、皇国が滅亡する」と考えたからだった、といわれた。 ・紀元節の二日後に、日本側と総司令部側が政府の憲法改正案について打ち合わせるために、麻布の外相官邸で会議が行われた。 ・「第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」から始まる政府改正案は、もう総司令部に提出されていた。 ・吉田外相や、憲法改正問題の主務大臣となっていた松本国務相が庭にテーブルをだして待っていると、コートニー・ホイットニー准将と、チャールズ・ケーディス大佐が、佐官を二人順えてやってきた。ホイットニーは民政局長であり、ケーディスは局次長である。 ・ホイットニーは座ると、口をひらいた。 「最高司令官は、先日、あなたがたが提出した憲法改正案を、自由と民主主義の文書として認めるわけには、まったくゆかないといわれた……」 ・そういいながら、連れてきた佐官に二十ページほどの厚さがある文書を、日本側の出席者に配らせた。 「これが最高司令官が、今日の日本が要求している諸原則を満たしているものとして、承認し、あなたたちに手渡すように命じたものである……」 ・英語でタイプが打たれ、前文から始まって、十一章、九十二条にわたる完全な憲法案であった。 ・そして、前文には「平和を愛する諸国の公正と信義に、日本の安全と生存を委ねる」といったことがあり、第一条には天皇が「日本」の「象徴」であって、その「地位」は「民意に基づく」とうたわれていた。 ・そして、読み進むと、日本は軍隊も、交戦権も持たないことになり、議会は一院制で、また、土地はすべて国有化されることになっていた。 ・日本側が読み終えて、蒼ざめると、ホイットニーが「連合国から天皇を戦争犯罪人として裁けという圧力が、日増しに強くなっているが、もし、この憲法法案を受け容れれば、天皇は安泰になると考えてよい」といった。 ・そして、「もし日本政府がこの案を拒否するならば、最高司令官は自分から直接、日本国民に示してもよいと考えている」とつけ加えた。 ・この瞬間、八月十五日から生き延びてきた大日本帝国は崩壊したのだった。 「陛下、こちらを向いて」 ・国民のなかへ入ってゆくという御巡幸は、総司令部の示唆によって始められたのだった。 ・総司令部は「人間宣言」や、皇室財産凍結といった一連の措置を通じて、天皇の権威を傷つけ、神棚から下ろすことをはかっていたのである。 ・ある元総司令部高官の言葉を借りれば、「眼鏡をかけ、近眼で、猫背の小男を見れば、天皇に対する信仰も崩れるだろう」と計算したのだった。 デモ隊が皇居へ向った…… ・五月に開廷する極東軍事裁判のために来日した、連合国の検事や判事たちが “裁判ゴッコ” に熱中している間、共産党と、その支持者たちは “革命ゴッコ” に耽っていた。 ・五月一日、宮城前広場で「第十七回メーデー」が開かれた。 ・大会は、二十二項目の決議と、十九項目の要求と、連合軍への感謝のメッセージを採択して終った。 ・大会後、共産党幹部は総司令部へ行って、連合軍への感謝のメッセージを届けた。 ・共産党は、「革命」への早道として、食糧不安を最大限に活用することに努めた。「配給の人民監視」「憲法より “めし” を」をスローガンにして、東京では区民を煽動し、配給所長の吊し上げや、隠匿物資の摘発や、区民大会を組織した。五月十九日には、全国各地で「食糧メーデー」を催すことを企画していた。 敗れた皇帝の「閲兵」 ・議会では、与野党が、占領軍の押しつけた日本国憲法案を討議していたが、日本では新憲法案が、占領軍によって起草され、文字通り強要された事実を、ごく限られた一握りの人々しか知っていなかったが、天皇はその一人であった。 ・極東国際軍事裁判のキーナン主席検事は、天皇を戦犯として裁くことは「誤り」であり、敗戦まで「日本国民の上に乗っている傀儡にすぎなかった」という談話を発表している。 ・新憲法案によれば、皇室財産が国有化されることになっていた。 ・終戦時の皇室財産は、厖大なものだった。 ・皇室が所有していた土地は百三十五万町歩におよび、面積にして日本の面積の三パーセントを越え、神奈川県の五倍以上に達するという広大なものだった。 ・このなかで、林野は帝室林野局が管理、経営したが、五億六千万石という木材の蓄積高は、日本の総蓄積量の八パーセントにあたった。このほかに、御資財本と呼ばれ、日銀、満鉄など二十九社の有価証券が、終戦時には現金をあわせると約三億四千万円あった。 ・終戦時の日銀券発行高が二百八十六億円であったことを考えると、いかに大きなものかがわかる。 ・もっとも、明治維新までは、皇室は一口に「禁裏拾万石」といわれ、小藩程度の収入しかなかった。当時の皇室の窮迫ぶりは、天皇が酒や生魚にも事欠いていたといった多くの挿話となって伝わっている。 ・「御一新」を行った明治政府は、天皇の権威と権力を裏付けるために、神道の国教化とならんで、徐々に皇室財産を厖大なものに増していったのだった。 「象徴」天皇の誕生 ・アメリカ人記者が書いた記事には、「 “マッカーサー憲法” の大部分は……総司令部において書かれた」のであったと報じている。 ・『朝日新聞』は「新憲法の公布に際して」と題する社説を掲げて、将来、憲法を改正する必要が起った場合に、改めることに躊躇してはならない、と主張している。 「憲法は、国家の基本法であるから、しばしば改正することは、もとより望ましいことではないが、人民の福祉のために存在する法律である以上、恒に生命のあるものとしておかねばならない」 「慎重は要するが、憲法改正については、国民として不断の注意を怠らないよう心がけるべきである」 マッカーサー元帥の帰国 ・終戦から四年後、七月四日のアメリカ独立記念日に、マッカーサー元帥は「日本紀共産主義の世界侵略にたいする防壁である」という談話を発表している。 ・前年一月にはアメリカの陸軍長官が、日本を共産主義に対する防壁とせよ、と講演している。 ・昭和二十五年元旦には、マッカーサーは年頭に当って、「日本国憲法は、日本国の自己防衛の権利を否定しない」という声明を発表した。 ・一月には、世界の共産党の指導機関であるコミンフォルムが、日本共産党の「平和革命」路線を非難した。日本共産党幹部は直ちに自己批判」して、ふたたび暴力革命方式をとることに決定し、いわゆる “火焔ビン闘争” が始まることになった。・これをきっかけに、総司令部は六月に、政府に共産党中央委員二十四人の公職追放を指令した。 ・総司令部が、共産党幹部を追放した十九日後に、北朝鮮が韓国に大挙して侵入した。在日米軍が国連軍として出動し、七月はじめにマッカーサー元帥は政府に、七万五千人からなる国家警察予備隊の創設を命じた。 あとがき ・天皇家は日本の歴史のなかで政治権力を握った時期もあったが、一貫して神道の宗家であり続けて来た。 ・天皇は今日でも神道の最高神官であって、歴代の天皇がそうしてきたように、宮中において祭祀を司り、共同体である日本民族の安寧と繁栄を祈ってきた。 ・日本のどこかで地震や、洪水が起れば、天皇が悲しまれる、というのは、天皇が神々と国民との間の媒介者としての役割を負っているからである。 ・日本国民は今日でも、部族的な性格を備えている。同質性が高いとか、家族的な国家であるといわれるが、「外人」ということば一つが示すように、外に対しては排他性が強い。そこで日本人は共同体としての純度がきわめて高いといえるが、部族として原始的な凝固力が強く働いている。 ・このような部族性はふだん意識されることはないが、日本人の意識の深いところに潜んでいる。天皇は部族としての日本民族の核であるが、この意味ではチベットのダライラマと同じような役割を与えられてきた。 ・外国の皇室や王室がはっきりと意識されて存在してきたのに対して、天皇家は民族の無意識のなかで生きつづけてきただけに、他国にはみられないような強い力を持っている。 ・天皇制が今日まで存続してきたのは、短い期間を除いて、天皇が政治から超越した場に身を置いてきたからであった。 ・明治以後は、便宜的に政治権力が天皇に集中するようになった。歴史を通じて天皇に蓄積されたカリスマティックな力はあまりにも大きすぎるものであった。 ・日本人は長いあいだ外国から隔絶されて、日本のなかで生活を営んできた。そこで自国を相対化してみる訓練を欠いてきたと同時に、共同体としての純度が高すぎるために、思想的にも日本のなかだけで通用する尺度を絶対化しやすいし、外の世界の現実から遊離した、部族的な幻想に囚われやすい。 ・太平洋戦争に突入するまでの日本の道程と、昭和二十年におとずれた破綻は、日本民族のこのような脆さによってもたらされたものであった。 ・前大戦の敗戦から多くの教訓を学ぶべきであるのに、今日でも日本も日本人もあの時代からあまり変わっていないようである。 ―― 完 ―― |