
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年12月15日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
56 |
21.12 |
火縄銃から黒船まで ―江戸時代技術史― 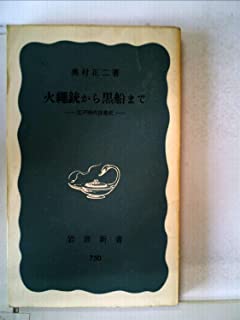 |
奥村正二 |
岩波新書 |
◎ |
Ⅰ 江戸時代を見る眼 1 問題の提起 なぜ江戸時代を取り上げたか ・江戸時代はいまも人びとの生活や心の奥底に生きている。 ・戦後突如として現れてきたように見える問題でも、掘り下げてみるとこの中に、多くの場合江戸三百年の歴史の投影を見ることができる。 ・日本に馬車がなかったのは幕府が許さなかったからである。主要な河川に橋を架けることも禁じている。 ・日本には牧畜の伝統がなく、古来馬匹改良の努力に欠けていた。 ・ここまで遡ると、明治政府が鉄道一辺倒の陸上交通政策を志向した事情もわかるし、いま見る歩行者無視の道路事情も、実は江戸時代そのままの土壌の上へ、それとは異質の西洋文明を無制限に輸入したためであることに思いあたる。 ・少なくともこの問題に関しては、明治以降の推移をたどっただけでは、必ずしも現在を正しく評価したことにならない。将来を展望する場合にも、以上の歴史は一応念頭におかねばならないことだろう。 技術水準を決める二つの要素 ・第一は顕在的な技術力、すなわち現実に存在したと思われる技術の表で、昔の技術を示す遺物や記録から判断されるものの評価である。 ・第二は技術ポテンシャル、すなわち新しい技術を受入れあるいは創造する力の評価である。 ・日本は幕末から明治斯年にかけて、各界で不思議と多数の人材を生み出しているが、技術の世界もその例外ではない。導入技術を完全に日本のものとするため、それと四つに組んで悪戦苦闘した技術者は数が多い。その傘下で献身的な努力を重ねた職人の数は無数である。 ・これらの人材で構成される層の厚みとひろがり、かれらを育てた環境、とくに幕末の藩校におけるエリート教育と寺子屋における庶民教育がその中で果した役割等が、問題点として取り上げられねばならない。 どの技術分野を取り上げるか ・鉄砲、船、鉱山はいずれも幕藩体制の消長と根源的に結びついた重要なものであり、明治以降の近代技術ともきわめて深い関係を持っている。 ・それ以外に、生糸、織物、金物は取り上げねばならぬ。江戸中期まで輸入品の大宗であった生糸が、幕末には一転し輸出の王座を占める。この間の養蚕製糸の技術発展などは、技術史研究家にとって最も興味をそそられる部分である。 ・またすべての産業技術を通じて人材育成の基盤となった教育その他の要因も、横断的にあたる必要がある。 2 技術をとりまく環境と条件 持てる国日本と幕藩体制 ・江戸時代を通じて人口は大体二五〇〇万から三〇〇〇万人の間を上下した。 ・金銀銅の産出高は世界有数で、砂鉄も十分にあった。 ・エネルキー資源としてはいたるところに森林があり、石炭に注目する必要も起らなかった。 ・農民は勤勉で、食料の生産は一応人口を賄うことができた。当時の日本は持てる国であったといってよい。 ・一六〇三年(慶長八)に幕府を創設した家康は、将軍として諸大名に君臨すると同時に、別に広大な直領地いわゆる天領を持ち、天領に対しては直接に自分が領主となる態勢を作り出した。 ・目ぼしいところをすべて天領として押え、残余を適当に各藩へ分割して、常に勢力均衡が計れるようにした形を幕藩体制とよんでいるが、これが二百数十年にわたって幕府を存続させた力の根源である。 幕藩体制の障壁 ・藩が鉱山の試掘、採掘をするには、幕府の許可が必要とされていた。しかし許可を得て事業をおこなったのでは、藩の財政に寄与することが少ないので、秘密の採掘もおこなわれた。 ・幕府は隠密を使って、各藩の各藩の産業財政事情を調べる。もし藩の財政が豊かだと見られると、幕府は必ずその財力を殺ぐような大工事を下命して、各藩勢力の均衡をはかる。 Ⅲ 御朱印船・千石船・黒船 2 船と航海術 鎖国の窓口・長崎への来航船 ・鎖国は日本人の海外渡航を禁じたもので、外国船の来航を拒んではいなかった。だから鎖国の後も長崎へは、外国船が引き続いて来航している。 3 急転する幕末と西洋船 断絶を破る四つのいとぐち ・カッテンディーケも、海軍に関する知識をまったく持たなかった日本人が、わずか四年間で「外国人の助力を借りずやっていけるまでに成長したことを驚嘆せずにいられない」と述べている。 Ⅴ 歯車とからくり ――水車・和時計・ろくろなど―― 日本の産業革命と水車 ・明治日本の産業革命は、実は水車を主要動力源として遂行されたのである。 鎖国前の輸入時計 ・日本へ最初に機械時計が伝来したのは一五五一年(天文二〇)で、ザビエルが大内義隆に献上したものだといわれている。 からくり人形とその評価 ・立川昭二氏(北里大学)の著書『からくり』より、 ‹江戸時代のからくり人形は、一部上層階級の持ちものとして玩具の世界に閉じこめられていたようで、そこに含まれた技術が当時の産業に寄与したことはなかったようだ› ・しかし立川氏はこれらの自動人形を江戸泰平の三百年間、抑圧され蓄積されてきた創造的エネルギーの大きさを示す一つの指標と評価し、そこから幕末日本には、明治以降に流れこむ西洋のメカニズム文明を即座に受入れる探求心と理解力が用意されていたとの説をたてている。 ―― 完 ―― |