
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年12月27日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
57 |
21.12 |
徳川が作った先進国日本 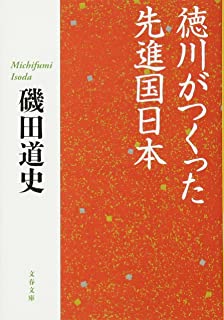 |
磯田道史 |
文春文庫 |
◎ |
はじめに ・わたしたちは江戸時代という遺産をもっています。江戸時代二百六十年は、この国の素地をかたちづくった時代です。 ・落とした財布が世界で一番もどってくる日本、自動販売機が盗まれない日本、リテラシー(識字率、読解記述力)の高い日本人、これらは明らかに「徳川の平和」のなかでできあがったものです。 第1章 「鎖国」が守った繁栄 1806年(文化3年) 「徳川の平和」の岐点 ・日本に公式に通商を求めてきた最初の接触は、寛政4年(一七九二年)にロシアから来た使節ラクスマンでした。 ラクスマン、レザノフと日本との出会い ・江戸時代の日本は「鎖国」していた――といわれますが、文字通り「国を ・そもそも、「鎖国」という言葉そのものがラクスマンシュッ減のころはまだ存在しません。 ・幕府首脳がこの言葉を使いだすのは十九世紀も半ばになってからで、まだ半世紀も先のことなのです。 ・むしろ「鎖国」というのは、ラクスマンやレザノフによる「ロシアの接近」を機に強く意識されていったといえるかもしれません。 ・否が応でも対応を迫られた幕府が、彼らの「開国」要求を撥ねつけるために、まるで家康以来の伝統「祖法」であったかのように「鎖国」という観念を急速に形づくっていったというのが実情に近いのではないでしょうか。 ロシア船襲撃事件 ・徳川幕府の通商拒絶によって、レザノフは国外退去となります。 ・しかし、半年以上も幽閉さながらの状態に置かれたあげく、手ひどい仕打ちを受けたことに激しく憤り、日本への報復を計画します。 ・文化三年(一八〇六年)九月、レザノフの指令を受けたロシア軍艦ユノナ号が突如、樺太南部の松前藩の施設を襲撃しました。 ・この事件は鎌倉時代の蒙古襲来、すなわち「元寇」以来の対外危機ということから、「露寇」事件(文化露寇)とよばれています。 ・さらに翌文化四年(一八〇七年)四月、ロシア軍艦二隻が択捉島に出現し、幕府の警備施設を襲撃します。 開国論と鎖国論 ・幕藩体制は、将軍の武威「幕府は強いぞ」という権威で成り立っていました。 ・将軍が統治者として認められ、権力を行使できるのは、諸大名を圧倒する武力をもっているからでした。 ・幕府の本質は「軍事政権」であり、その権威の源泉は武力で、一度でも弱いとみなされれば、この政権はもちません。 武力衝突の回避へ ・明治三十七年(一九〇四年)、日本とロシアは世界初の大規模近代戦争といわれる日露戦争を繰り広げますが、そのほぼ百年前、「第〇次日露戦争」とでもいうべき戦争へと突入していたかもしれなかった、という事実は特記すべきだと思います。日本史には「幻の日露戦争」が存在するのです。 「民命」の重さ ・われわれが時代劇で見る江戸時代は、主に天保(一八三〇~四四年)以後の姿です。 ・日本の近代はアメリカ=ペリーが開いたように語られますが、それは違います。ロシアこそが国境を接する唯一の西洋国であり、まずロシアとの対峙という前史があって、日本の近代化があるわけです。 第2章 飢饉が生んだ大改革 1783年(天明3年) 飢饉が明らかにした政治の矛盾と限界 ・天明の飢饉の死者は、全国で百万人以上に上るとの推計がなされています。 第3章 宝永地震 成熟社会への転換 1707年(宝永4年) 豊かな農村社会へ ・十八世紀以降、人びとは農業の効率を求め、全国で多くの農書が普及していきました。 ・さらに農民たちは農書に学ぶだけでなく、農具の改良にも力を注いでいきます。 ・そして、農書の普及とともに農村に浸透していったのが「読み書き」の能力です。 ・人びとは農書を読む力をつけるために寺子屋に通い、読み書きを学びました。 ・精密な農業は農民に「知的」であることを要求します。 ・それで、農民たちは積極的に生活向上のための「学び」に取り組み、読み書き、そろばんの能力を身につけるようになります。 ・この時期、普通の農民でも相当な数の蔵書をもっていたことが明らかになっています。 ・こうした教育水準の上昇、そして世界に冠たる高い識字率は、暮らしの質や充足感を引き上げ、農村社会を「成熟」させることになりました。 ・そしてそのことが、江戸時代後期に花開く分厚い民間社会のベースをつくり上げることにもなったのです。 第4章 島原の乱 「戦国」の終焉 1637年(寛永14年) 武家政治の大転換 ・五代将軍徳川綱吉は、武士だけでなく、庶民にも新たな価値観を浸透させました。それが「生類憐み令」です。 ・これは非常に誤解されている法令で、悪法の象徴のように扱われています。しかし、決して犬の命だけを尊重しよう、犬だけを大事に使用というおかしな法令ではありません。 ・具体的な条文にはこうあります。 「犬ばかりに限らず、 つまり、生きとし生けるもののすべてを将軍が保護する、という法令だと解釈するのが正しいのです。 ・しかも、これは一片の法律ではなく、実際には、老人を姥捨て山のようなところに捨ててはいけない、病人や行き倒れとなった人の治療を放棄して打ち捨て、殺してしまってはいけないという、二十年ほどかけて出され続けた、社会的な弱者を救済するさまざまな法令群を「生類憐み令」と総称しているのです。 ・綱吉の根本意図は、人びとに「慈悲」や「仁」の心をもたせることでした。 ・学問では歴代将軍中屈指の頭脳と教養を有していました。 ・当時、幕府の正式な学問として扱われていた儒学に深い造詣をもち、将軍自ら講義を行うほどの実力者だったのです。 ・その綱吉だからこそ、政治思想や価値の大転換が可能だったのかもしれません。 ・その結果、「命」を尊重するという価値観が根付いていきました。 ・綱吉は悪い犬公方とされていますが、実は、彼こそが徳川の平和に大きく貢献していました。 ・それは、政治・統治の面でみれば、「殺す支配」から「生かす支配」への転換だったといえるでしょう。生命重視への大転換がまさに綱吉によって図られ、徳川の平和が完成したのです。 ・平和はたやすく達成できるものではありません。平和と言う観点から見ると、島原の乱から綱吉にかけての時代こそ、日本史の中の大きな転換点でした。それはまさに「未開から文明への転換」と言えるかもしれません。 ―― 完 ―― |