
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2021年03月21日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |
8 |
21.02 |
漢字の社会史 東洋文明を支えた文字の三千年 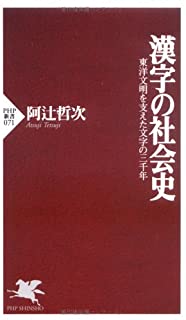 |
阿辻哲次 |
PHP新書 |
◎ |
はじめに ・漢字は三千年前の中国人が作ったアイコンなのである。 ・欧米人には漢字がわからない、と人はいう。だがそれは漢字が文字として、中国語や日本語など特定の言語を表記するために使われたからであって、言語と切り離せば、それは欧米人にとっても十分に有効な、情報伝達のための効率のよいメディアなのである。 第一章 文字と古代国家 1 神聖な文字 漢字誕生をめぐる ・文字の発明に関する伝説は、中国に古くから伝えられていて、それによれば、漢字は黄帝という太古の聖王に仕えた ・蒼頡がある時、野原に出てなにげなく地面を見ると、そこには鳥や動物の足跡がいっぱいついていた。 ・だがその足跡をよく見てみると、それぞれに馬なら馬の、ハトならハトの足の特徴がはっきりと示されているから、動物そのものを見なくとも、足跡を見るだけでそれがなんの鳥獣の足跡であるかがすぐにわかった。 ・そのように足跡から動物を特定できるのは、「類を異にするものはそれぞれ形が異なっている」から、つまり動物ごとの特徴がその足跡の中にうまく表現されているからである、という事実に蒼頡は気づいた。 ・かくして彼は、鳥獣の足跡と同じようにさまざまな事物の特徴をうまく抽出し、それを造形的に表現することによって、その事物を意味する文字を作ることに成功したという。 ・蒼頡がこうして漢字を発明したという伝説を「蒼頡造字伝説」という。 第二章 国家と行政と文字 1 国家統一書体の完成 始皇帝の登場 ・始皇帝が実施した中でももっとも大きな変革は、全国を三十六の郡に分け、さらに郡をいくつかの県に分けて、そこへ中央から官吏を派遣して、中央集権統治体制を確立したことである。 3 記録素材の変化――竹から紙へ 木簡の多様な形と用途――「檄を飛ばす」「刺を通ず」 ・特殊な用途に使われる木簡のひとつに「 ・今も日本語で使う「檄を飛ばす」というのは、もともと戦争などの緊急事態に際して危急を訴え、警戒を呼びかける文書を各地に届けることを指したのである。 ・また私たちが日常的に咲かう「名刺」も、木簡の文書に由来するものだった。 ・名刺はもともと「刺」または「 第三章 規範の確立 5 印刷のはじまりとその影響 印章の起源と発展 ・印章がないと日常生活に支障をきたすほどに、印章が幅を利かす国は、世界広しといえども日本だけで、現代の中国ではもはや印章は書画の署名に使うか蔵書印くらいにしか使われなくなっている。 第四章 東アジアの文字事情 1 漢字を媒介とした文化圏 表意文字「漢字」の伝播力 ・言語的にまったく異なる日本語を使う日本人が、なぜ漢字を自由に使いこなすことができたのだろうか。 ・それは究極的には漢字が表意文字であったからだといえるだろう。 ・表意文字はその背景にある音声言語と切り離しても、文字の字形だけで本来の意味を伝えることが、ある程度は可能なのである。 ・たとえばここに「海」という漢字があるとして、この漢字がどのような意味であるかを知るには、別にその字を中国語でどう発音するかを知っている必要はない。 ・これが良くも悪しくも表意文字の最大の特性であって、漢字一字ごとがもつ意味と、それぞれの言語での単語の対応関係が、つまり上の例でいえば「海」という漢字が、日本語での「うみ」という単語を意味するものであることが、たやすく理解できるしくみになっている。 ・こうして「海」という漢字の日本語での読み方が「うみ」と定められた。これが訓読みである。 ・そしてそれとは別に、中国語での発音をそのまま自国の言語内に導入して、それぞれの漢字の読みを定めることもできた。これが音読みで、これによってさらに漢字を表音文字的に使って自国語を表記することも自由にできた。「万葉がな」がまさにその例である。 ・表意文字としてのこのような特性が、漢字が中国以外の広い地域にも伝播していったもっとも大きな要因であった。 3 文字と外交 中華思想のもとにおこなわれた外交 ・中華思想によれば、「夷狄」が「中華」を慕うのは当然であって、「夷狄」が中国に反逆することは絶対に許されない。 ・このような意識は二十世紀はじめまで中国の統治者階級に根強く残り、科学的な思考と産業革命を経験して近代化したイギリスなどの西洋諸国家が外交を求めても、「野蛮な国からの朝貢」としか認識できなかった。 六十以上の国と外交した唐代 ・中華思想によれば、中国国内を統治する「天子」の恩恵は周辺の「夷狄」の国々にも及ぶものだから、周辺国家も世界の中心にいる「中国」の「天子」のおかげで、やっと文化的な生活が維持できる。 ・したがって「夷狄」の国家では定期的に使者を派遣して、ささやかながらも自国の産物を献上し、中国の天子の恩恵に浴せることに感謝しなければならない。 ・こうして周辺国家が中国の皇帝に使者を送り、貢物を献上する制度が「朝貢」である。 ・朝貢もまた、中華思想によって「天子」が「夷狄」の国家に与えた恩恵であった。 ・なぜならばもともと中国は「地大物博」(土地は広く、物資は豊か)の国であるから自給自足が可能で、「夷狄」の国から取り寄せるべき物資や産物など、本来はなにもない。 ・しかるに〖夷狄」の国は生産力が低くて資源も少ないから、中国と交易しなければ文化的な生活を維持していけない。そのために「夷狄」の君長たちは中国に使者を派遣して、彼等にとって必要不可欠な物資を入手するための公益活動をおこなうのである。 ・だから外国との貿易は、中国側にとってみれば、皇帝から周辺の国家に対して与える一種の恩恵にほかならない、とされる。 ・こうして中国では、本来は相互に平等で互恵であるべき貿易活動にまで中華思想をはびこらせ、朝貢してくる周辺の「夷狄」国の王に中国式の官位を与えて属国の王に任命し、中国を至上とする宇宙のなかに取りこんだ。 ―― 完 ―― |