
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2024年05月26日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
10 |
24.05 |
日本人のための戦略的思考入門 ――日米同盟を超えて 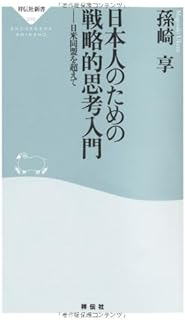 |
孫崎 亨 |
祥伝社新書 |
◎ |
第一章 戦略とは何か 戦略とは何か――「相手をやっつける手段」からの脱却 ・世界の多くの政治家は「相手より優位に立つ」ことを求めて政治に臨んできた。 ・アメリカを代表する国際政治学者であるジョセフ・ナイ教授は、「キッシンジャーやニクソンは、アメリカの国力を極大化し、アメリカの安全保障を阻害する他国の能力を極小化しようとした」と記述している。これは、いわゆる「ゼロサム・ゲーム」である。 ・ゼロサム・ゲームとは、経済学・数学における「ゲームの理論」から来た用語で、参加者の得点と失点の総和がゼロになる状況を言う。つまり、自分の得は相手の損、相手の損は自分の得。勝つためには、相手のマイナスを探し、弱点を突けばよい。 ・今日、戦略を考える際、「ゲームの理論」やコンピューターの利用が不可欠である。不思議なことに戦略関連の人には囲碁プレーヤーが多い。 ・「ゲームの理論」とは、利害の一致しない状況における当事者間の、合理的意思決定や合理的配分方法とは何かを考えるための理論である。 ・囲碁の古典的格言に「囲碁十訣」がある。これが見事に戦略論の基本をついている。 貪不得勝 (むさぼれば、勝ちを得ず) 入界緩宜 (界――相手の勢力圏――に入っては、宜しく緩やかなるべし) 攻彼顧我 (彼を攻めるに、我を顧みよ) 棄子争先 (子――少数の石――を棄てて、先を争え) 捨小就大 (小を捨てて、大に就け) 逢危須棄 (危うきに逢えば、すべからく棄てるべし) 慎勿軽速 (慎みて軽速なるなかれ) 動須相応 (動けば、すべからく相応すべし) 彼強自保 (彼強ければ、自ら保て) 勢孤取和 (勢い孤なれば和を取れ) ・一九六八年のチェコ事件では、チェコの民主化がソ連体制全体につながるのではないかと懸念し、軍事侵攻を行なって以降、ソ連共産党は内外の支持を急速に失った。 日本にとっての「大きな問題」とは ・戦略は「戦争で、相手をいかに完全に壊滅させるか」を求める 重要なのは相手でなく自分に悟らせること ・「闘争を続けることの無益さ、精神的な損失の大きさなど」を「相手(国)に悟らせること」だけでなく、実は「自分(の国)に悟らせる」、これが極めて重要だ。 ・核兵器時代、米国、ロシア、中国の責任ある戦略家は「戦争を避けることに自国の利益がある」という発想を必ず身につけている。 ・シェリングの考え方。シェリングは二〇〇五年、「ゲームの理論的分析を通じて紛争と協調への理解を深めた」功績で、ノーベル経済学賞を受賞した。 「『勝利』という概念は、敵対する者との関係ではなく、自分自身がもつ価値体系との関係で意味をもつ。このような『勝利』は、交渉や相互譲歩、さらにはお互いに不利益となる行動を回避することによって実現できる」 ・戦争から逃げるのではない。得であるから戦争を回避する。たとえ「敵」であれ、どこかに共通利益が存在することが説かれている。 ・日本が「北朝鮮の脅威」「中国の脅威」とどう向き合うかを考える時、共通利益や相互依存を考える必要がある。「今、戦争状態にない」ことこそ、最大の共通利益である。これを維持し拡大することが最大の戦略である。 ・重要なのは相手との関係ではない。自分の価値体系との関係である。自分の価値体系の中で争点をどう位置づけるべきか、それを考えた時、紛争の回避が実は利益をもたらすことがわかる。これを理解することによって、戦略に新たな世界が広がる。 孫子の再発見 ・「百戦百勝は善の善なる者に非ざるなり。戦わずして人の兵を屈するは、善の善なる者なり」「用兵の法は、国を全うするを上と為し、国を破るはこれに次ぐ」。孫子である。 ・孫子の再発見が第二次大戦後の戦略論の特質である。 ・行動には、常にコストがつきまとう。「コストに見合う成果が出るか」、これが戦略的思考の要である。 ・ドイツの戦略家クラウゼヴィッツは「戦争とは相手にわが意志を強要するために行なう力の行使である」「この目的を確保するために我々は敵を無力にしなければならない」と指摘した。 ・この流れをくむモルトケ(プロイセン王国の参謀総長)は「敵国政府のあらゆる戦力の根源、すなわち経済力、運輸通信手段、食料資源、さらには国家の威信すらも奪取しなければならない」と指摘している。 ・クラウゼヴィッツやモルトケは「戦略とは相手国の完全破壊を目指すもの」であることに何の疑問も抱いていない。しかし、「その過程で味方がどれぐらいの被害を被るのか」「この被害と目指すもののバランスがとれているか」の判断が欠けている。 日本をめぐる安全保障環境の変化 ・一九六〇年の日米安保条約時、日本の指導層は米国戦略に巻き込まれる危険性を察知し、日米安全保障の対象を極東に限定し、軍事行動を国連憲章の枠内に留めた。 ・しかし、冷戦後の米国の戦略と巧みな工作の中で、日本の指導層はかつての先輩の苦労に顧みることなく、今や、「米国に追随する」こと以外考えていない。 ・二〇〇五年十月、「日本は米軍と共通の戦略のもとに世界に展開する」という政府間合意を結んだ。このことによって、日本が危険な領域に踏み込んでしまったことについて、ほとんど報道はない。したがって、多くの国民は変化の事実すら知らない。 ・そして、安保条約五〇周年をかけ声に、日米関係強化が叫ばれる。「関係の深化はいいことだ」という言葉の響きを頼りに、一段と軍事協力が進む。 ・逆に冷戦後、米国内には「今や同盟は古い、今後は個々の紛争ごとに連合を作ればよい」との考えが出てきた。 ・しかし、それだからといって、米国は次の事件の時に、参加国に恩義を感ずることはない。 ・米国は、連合に参加したのは「各々の国に利益があったからである」とみなす。そこには貸し借り勘定はない。流動の激しい今日、長期的で広範な同盟というスタイルは古いと指摘したのである。 ・この論の代表的論客は、ラムズフェルド前米国国防長官である。 ・同盟という名の下、日本を利用する、しかし同盟という名の下で日本に利用される余地は減らす。その道を今、米国は歩んでいる。好き嫌いではない。事実である。 第二章 なぜ日本人には「戦略」がないか 戦略を学ぼうとしない日本 ・ <途中> |