
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2024年06月16日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
1 |
24.06 |
拒否できない日本 アメリカの日本改造が進んでいる 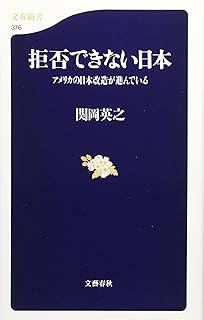 |
関岡 英之 |
文春新書 |
◎ |
2 対日圧力の不可解なメカニズム わずか二十分の階段で決まった「日米構造協議」 ・アメリカは「系列」や「談合」といった日本独特の商習慣は外国企業を差別する「非関税」障壁で、自由な競争を阻害していると非難して、ただちに撤廃するよう要求した。 ・亜米利加は特に談合を厳しく非難し、公正取引委員会による取締りの強化や独占禁止法の運用強化など、日本の制度や政策の詳細に立ち入ってあれこれ具体的な要求を突きつけた。 ・またアメリカは、日本の「不合理な」流通システムなどが内外価格差を生んでいると主張して規制緩和を要求し、「これは日本の消費者のためにもなる」と恩着せがましく言いふくめた。 ・アメリカの要求はいわば日本という国の改造計画というに等しいものであり、主権国家に対する要求としては例を見ないほどぶしつけで厚かましいものだった。 エシュロンの通信傍受 ・エシュロンというのは、アメリカ・イギリス・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドというアングロ・サクソン系の五ヶ国が第二次世界大戦以来、共同で運用しているといわれる世界規模の通信傍受システムのコード・ネームである。 ・傍受した通信内容は、アメリカの国家安全保障局(NSA)や中央情報局(CIA)によって解析されているといわれている。 身の毛もよだつアメリカの独善 ・つまり、相手国が不正行為を行っている可能性があるならば、たとえ同盟国といえども、アメリカは相手の通信を勝手に傍受し、盗聴によって入手した情報をアメリカの国益のために活用する権利があるというわけだ。 5 キョーソーという名の民俗宗教 アングロ・サクソンが独占するノーベル経済学賞 ・このことは、近代経済学がもともと普遍科学などではなく、アングロ・サクソンの価値観を反映したひとつのイデオロギーに過ぎないことを、もしかしたら示唆しているのかもしれない。 ・とりわけ一九八〇年代以降、ミルトン・フリードマン流の新古典派経済学が主流となってからは、アメリカのノーベル経済学賞受賞者は、市場原理主義者やシカゴ大学関係者に偏在している。 ・たんにアメリカの一学派のイデオロギーに過ぎない市場原理主義があたかも科学的真理であるかのごとく絶対化される。 ・英語、ドル、時価会計、英米法、そして近代経済学。すべてアングロ・サクソンの世界 "文化" 遺産ではないか。 勝ちさえすればすべてが正当化される ・アメリカ人は競争に勝つことしか関心がなく、勝ちさえすればすべてが正当化されると思いこんでいる。 ・それは自己に対して極めて甘い反面、社会的弱者に冷淡で、他者に対して独善的に振る舞う傾向をはらんでいる。 ・こんにちアメリカは、国内や途上国の貧困や格差といった問題を無頓着に放置し、他方では自国の主張を他国や国際社会に一方的に押しつけるユニラテラリズムや、他国を厳しく批判しながら自国に都合良くルールを曲げるダブル・スタンダードを批判されながら少しも改めようともしない。 あとがき 「継受法」と「固有法」という視点でみると ・継受法とは外国から継承接受した法体系であるのに対して、固有法とは自国独自の倫理や慣習に則って編み出されたものをいう。 ・これを日本の歴史にあてはめてみると、古代の飛鳥・奈良・平安約六百年間は、主として当時のグローバル・スタンダードであった中国の律令制度を導入した継受法の時代であった。 ・一方、明治維新から現在に至るまでの百数十年間は連続して「欧米継受法の時代」とみることができる。 ・そしてこのふたつの継受法の時代のはざまに、約七百年間に及ぶ「固有法の時代」があった。 ・西暦一二三二年に鎌倉幕府の執権北条泰時は貞永式目(関東御成敗式目)を制定した。 ・その頃、京の公家社会は中国から継受下律令体系で運営されていたが、貞永式目はそれをことさら参照することもなく、当時辺境だった東国の武家社会の慣習を成文化したものだ。 ・いわば日本固有の価値観に基づいて自律的に創られたものであった。そしてその後、鎌倉・室町から安土・桃山まで実に約四百年間この国の基本法となった。 ・江戸幕府は新たな国法として「武家諸法度」を制定したが、貞永式目はその後も徳川三百年を通じて寺子屋の教本として命脈を保ち、庶民の心の秘奥に深く沈潜した。 ・一方、貞永式目の制定とほぼ同じ頃、日本の仏教界では大陸から招来した旧仏教に飽きたらない想いを抱いていた法然、親鸞、道元などが独自の思想を模索して、やがて日本固有の鎌倉新仏教を誕生させた。 ・この時代の日本人は当時のグローバル・スタンダードを鵜呑みにせず、法にせよ、思想にせよ、自らにふさわしいものはなんなのかと、おのれの頭で必死に悩み考え抜いて、ついには他国に例のない独自の境地を切り開いたのだ。 ・この精神革命は日本人全体の創意にも大いなる刺激を与えた。自己の内面世界をひたすら凝視し続け、精神的探求を深め続けていった結果、やがて日本的個性が充溢した、まごうかたなき固有の文化が開花した。 ・世阿弥の能、利休や織部の茶、待庵や桂離宮などの建築、夢窓疎石や小堀遠州の庭、光悦や光琳の書画工芸……。 ・こんにち海外の人々がその独創性に驚愕し、かけがえのない世界の至宝として賛嘆を惜しまない「日本的なるもの」がうみだされたのは、なべてこの固有法の時代に集中している。 【私見 : 今の日本人はこのことを自覚しているか。もっと過去の日本を見つめ直し、大切にしなければならないものがあるように思う】 固有法時代の日本的なるもの ・かつてわたしたちを真の創造性に開眼せしめた源泉が、固有法の時代の日本人の精神、すなわち他者にとらわれず、徹底的に自己と向き合い、内発的な価値に導かれながら、おのれの頭で悩み考え続ける精神の営みだった。 ・日本人自身の未来のために、日本人自身の頭で考え、日本人同士で意見をぶつけ合う。その千載一遇の機会が、ついにいまめぐってきている。 ―― 完 ―― |