
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2024年12月20日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
20 |
24.11 |
日本資本主義の精神 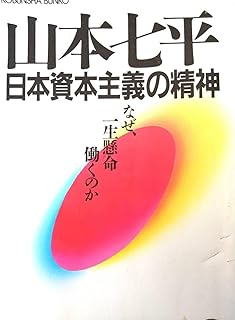 |
山本 七平 |
光文社文庫 |
☆ |
第一章 日本の伝統と日本の資本主義 2 血縁社会と地縁社会 日本は、「血縁イデオロギー」の社会だ ・社会学者の小室直樹氏 「世界各国どこにでもある普通のものであって、日本にだけないっていうもの、つまり社会学的に決定的に重要でありながら日本にはないっていうものがある。それは契約を基礎としたところの宗教、ないしは規範の考え方ってのは日本にはない。アメリカ人やヨーロッパ人も、中国人はよくわかる。韓国や北朝鮮の人もわかる。しかし日本人だけはどうしてもわからない。ところが、日本の場合には、契約もないけど、また血縁がないんですね。血縁のようにみえるけど分析してみると血縁でもなんでもない。たとえば、日本で婿養子って制度がありますけども、血縁人間の集団をつくるんだったら、ああいうことはありえない。したがって家族なんていうものも、血縁でもなんでもないんで、一つのイデオロギーでしょう」 ・日本において、血縁社会の原則を明確に法制化しているのは、明治における皇室典範だけだといわれる。 ・すなわち皇位継承は男系の男子に限り、その継承順位は血縁の順位であって、擬制は一切認められていない。簡単にいえば、天皇家の養子になることはもちろん、婿養子となることも、またそれらによって皇位を継承することも、一切不可能なのである。 ・そして、純然たる血縁社会とは、この原則が社会のすべてを律し、その原則で歴史が形成されている社会である。その意味で、アラブ人の社会は確かに血縁であり、華僑もそうだといわれるが、日本は昔からそうではない。血縁のように見られるものに非血縁的要素がはいってくることを、だれも不思議に思わない。 日本の社会には、なぜ、「希望退職」しかないのか ・血縁集団か地縁集団か判別がつかないものに、明治の藩閥がある。 ・藩閥は藩がなくなっても機能し、派閥という形でそれが継承されて、今なお機能している。 ・これが機能しているあいだは、実に強固に見える擬制の血縁集団というべき共同体に転化するというだけである。 ・機能しなくなれば崩壊し、また、機能する形で再構成される。だが、そこには組織といえる要素は皆無に近く、血縁集団のような形になることは否定できない。 ・そしてこのことは、日本の社会構造が変化を生じない限り、憲法が発布されようと、議会制度が導入されようと、変化は生じないし、生ずるはずもない。 東京が世界で一番安全な大都市である理由 ・「世間に相すまない」という発想は、日本の社会に大きな影響を及ぼしている。 ・犯罪学の宮沢浩一教授から聞いた話。慶応大学の不正入試が新聞に出たとき、慶応大学のある日吉の商店主が、近ごろ慶応の先生がみな、うつむいて肩身の狭そうなかっこうで町を歩いている、と言ったそうである。大学も機能集団であると同時に、共同体であるから、共同体の不名誉を自らの不名誉として「世間」に相対しているわけである。 ・このことは、また一面では、名誉ある共同体に所属することが、犯罪の抑制になりうるということである。日本は、近代化とともに、犯罪が、特に凶悪犯罪が減少している、世界で唯一の国といわれる。これには、以上のことが大きく作用しているであろう。 ・戦争直後の東京の人口は、戦災と疎開でゼロに等しかった。それが、一挙に人口一一五〇万という超巨大都市に膨張した。東京が世界最大の犯罪都市となり、夜の独り歩きなどは非常識といわれるような事態になっても、それは世界の通例どおりだというにすぎないであろう。それを防いで、世界で最も安全な都市にしているのは、機能集団がすぐ共同体に転化することにより、その全体的崩壊を防いでいるからである。 ・血縁集団は人工的に構成することは不可能だし、地縁集団は「第三の種族」化しなければ、共同体になりえない。この点、機能すれば共同体に転化し、一種の強固な擬制の血縁集団と化してしまう日本は、実に便利な国だといわなければならない。 「損失をあげる」ために機能する日本の企業 ・機能集団が共同体に転化してはじめて機能するという状態は、機能集団において自らが機能しようとすれば、まず、その共同体の一員となることが前提になる、ということである。それは、他の共同体に属しつつ、機能集団では個人として機能するということは不可能である、ということでもある。そこで自らが機能しようと思えば、逆に、自己を否定して共同体を優先させねばならないのだ。 ・この関係は、「あれは、できる男だが協調性に欠ける」とか「有能なんだけど、あいつはスタンドプレーが多くてね」といった言葉に表われている。いわば、機能集団の一員としては評価できるが、共同体の一員としては評価できない、の意味である。 ・この二面的評価は、機能集団における「功」が共同体の序列に転化する社会では、当然のことといえよう。これは、共同体にならねば機能しないという集団における一種の宿命ともいえる。 国鉄一家と高校生売春 ・「話し合い」の絶対化 ― 簡単にいえば、ある種の「話し合い」が超法規的・超倫理的に絶対化すると、たとえそれが違法であってもなんともできなくなる社会のもつ問題点である。 ・私はその例として「高校生売春」を取り上げた。売春をおこなった女子高校生が、補導されたときに述べる言葉は次のようなものである。 「相手も楽しいし、自分も楽しいし、世の中だれにも迷惑をかけていない。そのうえお金が入る。どうしてこれがいけないのか。」 これに対する反論は、なかなかむずかしい。 ・彼女たちの言っていることは、前提なしの無条件の話し合いに基づく合意が絶対であり、それを外部から拘束する法的、倫理的規範は一切認めないということであり、まさしく、超法規的、超倫理的な「話し合い」が絶対的な「義」であり、これに干渉する権利はだれにもないということなのである。 陸軍、総評にみる、日本が嫌われている理由 ・ <途中> |