
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2024年12月13日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
21 |
24.11 |
餓死した英霊たち 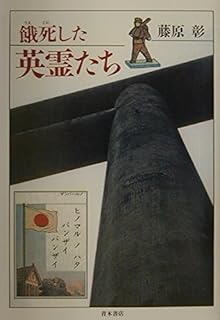 |
藤原 彰 |
青木書店 |
◎ |
第一章 餓死の実態 1 ガダルカナル島の戦い (1)無謀な陸軍投入 ・ガダルカナル島敗戦の責任はまったく大本営の作戦にある。 ・準備万端を整えて上陸してきた兵力も装備も優秀な米軍にたいして、何の情報収集もせずに、わずか一〇〇〇名の一木支隊先遣隊の十件突撃で飛行場を奪回しようという、およそ戦理に反した無茶な攻撃を実行させたこと、その後も兵力の逐次利用をつづけて、同じ失敗をくりかえとたこと、いずれも初歩的な戦術の誤りである。 ・一木支隊先遣隊が、米軍の優秀な火力に阻まれ、戦車に蹂躙されて、一瞬にして全滅したのに、何回でも同じ戦法をくりかえしたのである。 ・制海・制空権を失っているので、鼠輸送にしか頼れず、重火器が運べないので白兵突撃という戦法しか採れない。白兵だけでは優秀な火力装備に勝てないことは明らかなのに、「装備軽視という亡国的怠慢をもたらした」のである。 ・装備が運べないくらいだから、食糧も運べない。しかし人間は食糧がなければ生きていけないのである。 ・大本営の作戦当局者たちは、送り出した部隊の食糧の補給を一体どう考えていたのだろうか。 ・そもそもミッドウェー作戦にしても、占領後の補給という点からみれば成功は困難だったといえるが、ガダルカナル島の奪回など、補給の面からみれば絶対不可能の作戦だったのである。 (2)餓島の実情 ・降伏を許されず、死ぬまで戦うことを義務づけられた日本軍が、戦うための体力を失って、原始林の中で次々と餓死していったのである。 ・ガ島での第一戦部隊の食糧欠乏がもたらした凄惨な状況に陥っている第十七軍にたいしても、大本営は持久戦をせよと命令した。 ・陸軍のガダルカナル島に上陸した人員は三万一四〇〇名、そのうち、途中病気などで離島した者七四〇名、撤収作戦で九八〇〇名が収容されたので、二万八六〇名が失われたことになる。このうち、純戦死が五〇〇〇名から六〇〇〇名で、残り一万五〇〇〇名前後が栄養失調症、マラリア、下痢、脚気などによるものとされている。つまり純然たる戦死者の三倍、あるいはそれ以上が広義の餓死者だったのである。 (3)ガダルカナル戦が示したもの ・戦死者の何倍もの餓死者を出すというこの戦闘で、何よりも問題なのは、補給が困難なのが分かっているのに作戦の強行を命じた大本営の作戦当局者の責任である。 ・聯合艦隊がミッドウェー作戦を計画したとき、はじめは大本営海軍部が強硬に反対した。その反対理由の一つは、たとえ攻略はできたとしても、占領後の防備や補給輸送が難しいということだった。 ・陸軍部もはじめは反対で、補給が難しかろうというのがその理由であった。しかし海軍主体の作戦なので、陸軍はわずか歩兵一大隊主体の一木支隊(約三〇〇〇名)を派遣したのである。 ・支隊長の一木清直大佐は、盧溝橋事件を起こした支那駐屯歩兵第一聯隊の第三大隊長で、歩兵学校の教官を再度務めた歩兵戦闘の権威でもあり、銃剣突撃の信奉者でもあった。ミッドウェー戦のときも、飛行場占領までは銃剣突撃により、射撃を禁ずると指示していた。 ・大本営の作戦担当者は、この白兵第一主義を信頼し、ガダルカナル奪回の期待をかけるという時代錯誤の戦法をとったのである。 ・八月二〇日夜テナル河畔の米軍陣地を攻撃したが、重火器や戦車をそろえて待ちかまえた米軍にかなうはずはなかった。反日の戦いで全滅し、聯隊長は軍旗を焼いて自決した。 ・兵力の圧倒的な差はもちろん、銃剣突撃で米軍の弾幕に対抗できるはずはなかったのである。 ・また一木支隊の場合、米軍の弾幕の中に銃剣で突撃して、大部分が戦死したのだが、もし生き残ったとしても、補給がないのだから待っている運命は餓死だったのである。 ・一木支隊の攻撃失敗後大本営は、同じように川口支隊、第二師団、第十七軍と、兵力の逐次投入をくりかえした。 ・そのようなところに陸軍兵力を次々に送りこんだということは、圧倒的に優勢な米軍の火力装備に銃剣で勝てるという妄想を抱いていたからであろう。それにとどまらず、送りこんだ兵力への補給を無視していたことは、精神力で飢餓を克服できると本気で考えていたのだろうか。 ・歩兵の白兵突撃は優勢な米軍の火力に通用しないということをみせつけられたのに、同じことを敗戦までくりすえしていったのである。 (4)ガダルカナル以後のソロモン諸島 ・ガダルカナル撤退後のソロモン群島方面の状況は、ガ島の教訓を何も生かせず、補給困難な離島に兵力を送りこんで、飢餓の悲劇をくりかえすばかりであった。 ・ブーゲンビル島の日本軍は、まったく存在意義を失ってしまった。しかし第八方面軍司令官今村均大将は、「坐して餓死せんよりは戦って最後を全うす」という信念で、自らブーゲンビル島に赴いて第十七軍に攻撃を命じた。 ・第十七軍司令官神田正種中将もこれに従って、タロキナの米軍陣地を攻撃した。しかし圧倒的な米軍の火力に阻止され、この攻撃も失敗し、戦力をまったく喪失した。 ・以後はブーゲンビル島の第十七軍約三万二〇〇〇、第八艦隊約二万、計五万余の陸海軍将兵は飢餓と戦いつつ敗戦を迎えることとなるのである。 (5)孤立したラバウル ・四四年六月にはサイパン陥落、同一一月にはレイテ上陸が行われ、ラバウルの孤立無援はさらに決定的となった。 ・この時点でラバウルのあるニューブリテン島には陸軍六万五〇〇〇、海軍三万、ブーゲンビル島には一万五〇〇〇、合計一一万人の陸海兵力が存在していた。 ・連合軍側は、もはや飛行機も軍艦もないこの島の日本軍は、何の脅威でもなかったので、無駄な攻撃を避け、その自滅を待つ方針をとった。日本軍にとって飢餓との戦いがすべてとなったのである。 2 ポートモレスビー攻略戦 (1)無謀な陸路進攻計画 ・補給無視または軽視の作戦の例として、ポートモレスビー攻略作戦を挙げることができる。 ・ガダルカナルの戦いが、米軍の上陸によって生じた受動的な作戦であったのにたいして、これは日本陸軍が主体的に計画して実行した作戦である。 ・つまり作戦地の地誌も、後方補給の方法も、十分に検討した上で建てられた計画だったはずなのである。それなのに実際は補給皆無の飢餓地獄が発生した。 ・ニューギニア東南岸のポートモレスビーは、日本軍が第一段の南方攻略作戦につづいて計画した南太平洋での米濠遮断作戦(FS作戦)においても、最初の攻略目標となった要地であった。 ・ところが六月五日、ミッドウェー海戦で海軍の主力航空母艦四隻を失った。このため南太平洋遥かに広がる構想を持ったFS作戦自体が中止されることになった。 ・FS作戦は中止されたが、大本営はモレスビー攻略をあきらめたわけではなく、六月一二日の大陸指で第十七軍にたいし、ニューギニア北岸から陸路でモレスビーを攻略する作戦についての研究(リ号研究)を命じた。 ・六月三〇日、第十七軍司令官百武晴吉中将は、南海支隊長堀井富太郎少将をラバウルからダバオに招致した。南海支隊側は従来の調査に基づいて、陸路進攻はきわめて困難で、ほとんど不可能だという意見を述べた。 ・ところがこの第一線部隊の意見は、司令部からは消極的すぎるとみられ、無視されたのである。 ・大本営はミッドウェーの敗戦後の情勢を検討した結果、FS作戦の中止を決定し、七月一一日は大陸命を発令して第十七軍のニューカレドニア、フィジー、サモア攻略の任務を解き、モレスビー攻略の任務のみを残した。 ・だがこの大陸命では、攻略を陸路からするか海路からするかは示されてなく、それは「リ号研究」の結果に待つという態度に変わりがなかったのである。 ・ところが七月一五日、辻政信大本営陸軍参謀がこの大陸命伝達のためダバオに現れた。辻はこの大陸命交付後、次のような連絡を行った。 ・辻参謀は、大本営ではすでにモレスビーの陸路攻略が決定しているから、速やかに実行せよと伝えたのである。しかしこれは、ほかにもいくつもの例があるように完全に辻の独断であった。 ・だが、もともと陸路進攻に傾いていた第十七軍は、これを大本営の意向と受けとった。そして積極的にその意向を実現することとし、百武軍司令官は、七月一八日にダバオでモレスビー陸路攻略の軍命令を下達した。 ・この作戦では、三割が敵の弾による戦死、残る七割は病死だった。 ・このような悲惨な戦況をもたらした責任は現地の地形、気象などの実情を確かめないで、彼我の戦力を具体的に検討することもせず、ただ作戦上の必要からブナ地区の確保を命じた大本営にあるというべきであろう。 ・現地部隊の血のにじむような教訓資料は、大本営の作戦当局者には生かされなかった。依然として精神力の重要性を強調し、作戦の失敗を指揮官の精神的要素に原因があるとしている。 ・こうした大本営の精神主義むきだしの指導で、その後二年間にわたって東部ニューギニアで、同じような作戦がもっと大規模にくりかえされることになるのである。 3 ニューギニアの第十八軍 (1)現地を知らない大本営 ・ <途中> |