
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年11月03日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
76 |
17/09 |
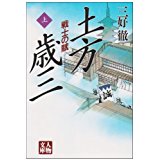 |
土方歳三<上> |
三好 徹 |
人物文庫 |
◎ |
梅一輪 ・福地源一郎は、 ―― 桜痴という雅号を使いはじめたが、その由来は吉原の桜路という遊女にいれげたことによる。桜路に惚れこんだ愚かもの、という自嘲をこめて、そのように称したのだ。 ・当時の日本における事実上の主権者である徳川将軍や、その政権の執行機関である幕府の政策は、尊皇攘夷の対極にあった。いいかえれば、尊皇攘夷は危険思想であった。 ・尊皇攘夷というのは、当時の日本では、ごく一般的なものであった。 ・もともと、徳川政権の基本的な方策は、鎖国だったのである。 ・国を ・その鎖国が、黒船という外圧によって崩されつつあった。怪しからぬ、追い払え、というのは、いわば憂国の至情にあり、幕府としては取り締まりにくい。 ・一方、尊王というのは、徳川政権の上にもう一つの権威を認めることであり、これは幕府にとっては許し難いものであった。 ・だが、幕府自体がそれを認めるような過失を犯した。実力をもって開国を迫る諸外国に対して、一時のがれの言いわけとして、条約が発効するには、勅許が必要である、といったのである。 ・朝廷、というのは、天子が政治を執り行うところ、の意だが、この時代に至るまで数百年のあいだ、実体としてそのようなものは存在しなかった。 ・京に天子がおわす、などということを知っている日本人は、百人に一人もいなかったであろう。 ・結果的に、みずから、自分たちの上に、もう一つの権威を認めたことになった。 ・その上、徳川ご三家のうち、水戸藩においては、尊王思想は必ずしも悪ではなかった。安政の大獄までは、藩主の水戸斉昭が尊皇攘夷派だった。 ・水戸の武士たちが、井伊大老を暗殺したのは、実質的には、主君の仇をとったにひとしいのである。 ・水戸浪士というが、藩に迷惑をかけないために、浪人していたといっていい。 ・この時期、幕府の力は強大である。みずからは、帝を持ち出したが、それを尊ぶものを弾圧することはできる。つまり、攘夷は大目にみるが、尊王は取り締まりの対象になる。 士道 ・切腹は武士だけのものである。農・工・商には、切腹という刑はないし、武士にとって、切腹は刑ではない。場合によっては、名誉ともなりうる。 血風 ・事なかれ主義は、幕府の伝統でもあった。 戦塵 ・松本良順曰く、 「医師は病気を治すことだけが仕事ではない。そんなことは、むしろ仕事の一部にすぎない。 人は誰しも、この世に生をうけたとき、天から寿命を授けられた。その天寿を全うできるように手助けしてやるのが医師の務めなのだ」 ・松本良順は、天保三年(一八三一)の生れ、佐倉藩の医師佐藤泰然の次男だが、十八歳のときに幕府の医官松本良甫の養子となり、養父のすすめで蘭学を修め、さらに幕命で長崎へ赴いて、オランダ人医師ポンペから西洋医学を修得した。 ・この長崎時代に、彼は関係者を説得して、長崎養生所を開設した。日本で最初の、洋式病院である。 ・文久二年(一八六二)に、江戸に戻り、将軍家茂の侍医に任ぜられ、翌年六月、緒方洪庵の没後に、西洋医学所頭取を継いだ。 ・のちに、日本陸軍最初の軍医総監をつとめ、軍の医療体系をととのえた。 謀士 ・勝は、神戸の海軍操練所を開設して、諸藩の子弟を教育していた。 ・学生は幕臣に限らなかった。坂本龍馬、陸奥宗光、伊藤 ・勝は、幕臣だったが、その目は、一徳川家にはなく、世界の中の日本を見つめていた。 ・西郷が大久保利通あての手紙に、 「じつに感服の次第に御座候」 と書いたのも、その巨視的な発想に心を惹かれたからである。 ・近藤「剣ができるばかりでは、これからの時代、もうどうにもならん」 土方「そうかもしれないが、剣ができなければ、役には立たんさ。剣というのはいつでも死ねるという覚悟のことだ」」 散る花 ・このころ、諸外国は幕府に兵庫開港を求めていた。幕府としては、頭の痛い問題であった国内問題が片付いておらず、それどころではなかった。そういう状態を見こしての、外圧である。 ・国内問題とは、長州藩処分についての幕府内部の意見不統一と、長州藩の巻き返しである。 ―― 完 ―― |
89 |
17/11 |
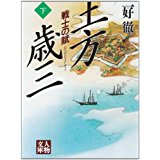 |
土方歳三<下> |
三好 徹 |
人物文庫 |
◎ |
甲陽鎮撫隊 ・徳川家においては身分や格式がいぜんとして幅をきかしている。家柄がいいというだけで、無能な人物が高い地位についている。 ・薩摩や聴衆においては、そうではない。事実上、薩摩藩を掌握している西郷は、過労や執政という家格の出身ではない。 ・また、鳥羽伏見で実力をみせた長州の諸隊も、多くは軽格の身分から出たものによって指揮されていたという。 ・徳川軍も会桑両藩も、指揮をとったものはすべて家格の高いものたちだった。 ・その能力によって高位を占めたものではなかった。 ・破れたのは、装備が旧式であるというだけの理由ではなかった。戦機をとらえ、兵を指揮する能力が劣っていたからだった。 ・いかに新式の装備をととのえたところで、それを活用する指揮官に人を得なければ、宝の持ち腐れにひとしい。 蝦夷の春 ・「武士は食わねど高楊枝」 というが、それは武士たるものの心意気をうたっているのである。空腹の兵は、たっぷりと食事をとった兵にはかなわない。 ―― 完 ―― |